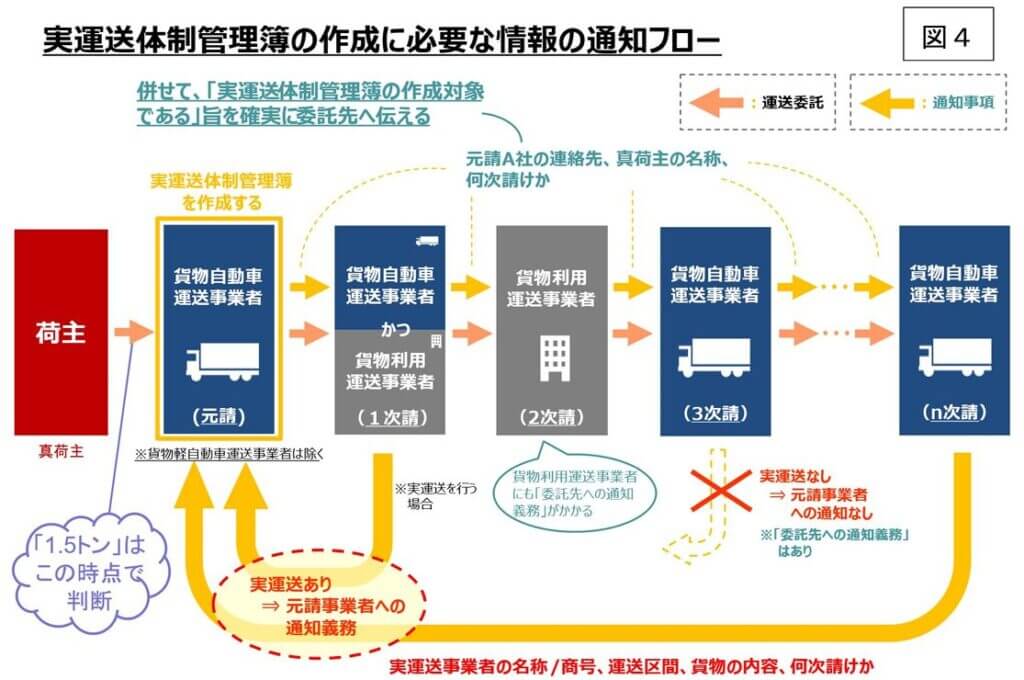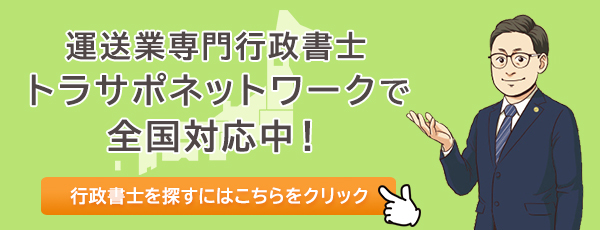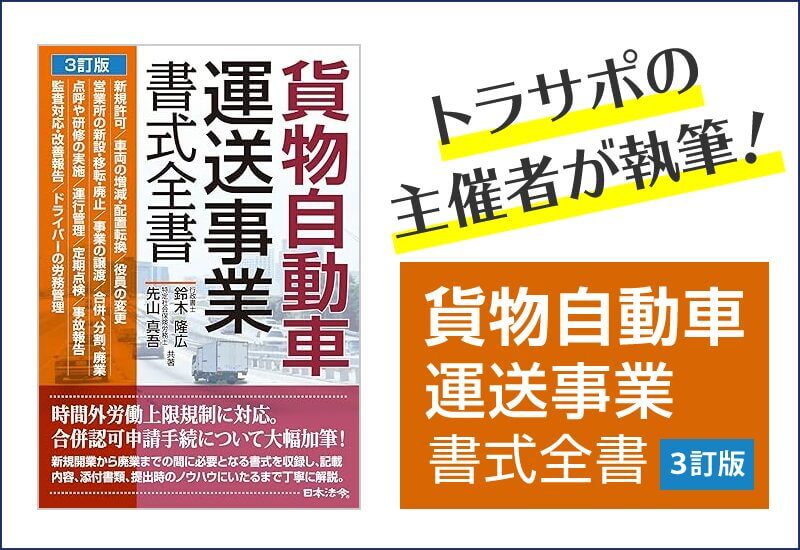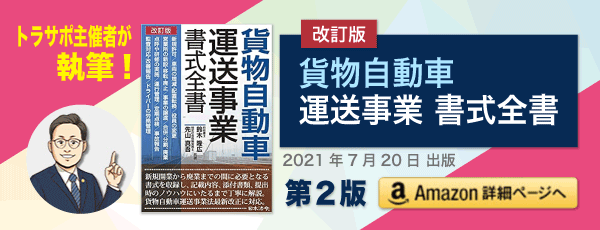【2025年2月最新】改正物流二法解説:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法
このページに関する質問は一切お受けしないのであらかじめご了承ください。
ネットにはあまりに情報が分散しているので、まとめる意味で作成したものです。
もし明らかに誤っている箇所があればそれについては根拠を添えて問合せフォームより教えていただけると助かります。(こうなのでは?という憶測については送られてもお返事できないのでご容赦ください)
はじめに
このページは2025年2月22日時点の情報に基づいて作成しています。
「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法」が「物資の流通の効率化に関する法律」に改名されます。
このページでは「物資の流通の効率化に関する法律」のことを「物流法」と略し、「貨物自動車運送事業法」のことを「貨物法」と略します。
今回の改正ではたくさんのことがありすぎて、簡潔にまとめようとしてもあまり意味が無いので、「この文章を読めばきっと全体がわかるはず」と網羅したものにしました。「荷主」「荷待ち時間」「荷役等時間」などが定義されたり、物流だけでなく消費者含めて経済全体について持続可能な流通を実現するという壮大な体系となっています。
トラサポは一般貨物専門なので、軽貨物については触れません。
基本的には、人口減少時代に経済発展を維持しようという方策です。従って、国土交通省だけでなく、経済産業省と農林水産省も一緒に策定しています。
中小企業規模の一般貨物自動車運送事業者にとって、実務的に最も関係してくるのは実運送体制管理簿に関わるところだと思います。それ以外の荷主、倉庫、元請運送会社などについてのルールがものすごく多く、中小企業規模の一般貨物自動車運送事業者についてのみ該当する箇所を探すのはとても難しいです。中小企業規模の運送会社は実運送体制管理簿の作成義務はありませんが、元請事業者に実運送体制管理簿の内容を通知しなければならないので、実質的には同等の情報を管理する必要があります。実運送体制管理簿が1.5トン以上の荷物についてのみ記載することとなっているのはおそらく宅配事業者の巨大な負担を考慮した結果だと思われます。
外注を使う場合は、運送の役務の内容(その利用する運送に附帯業務が含まれる場合にはその内容)及びその対価等について記載した書面を当該他の貨物自動車運送事業者等に対して交付する必要があります。
以下、大切そうな箇所を一部抜粋します。
・荷主等は、一回の受渡しごとの荷待ち時間等について、原則として目標時間を一時間以内と設定しつつ、業界の特性その他の事情によりやむを得ない場合を除き、二時間を超えないよう荷待ち時間等を短縮するものとする。
集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に到着した時刻から荷待ち時間のカウントがはじまる
・近年40パーセント以下の水準で推移してきた積載効率について、全国の貨物自動車による輸送のうち五割の車両で50パーセントを目指し、全体の車両で44パーセントへの増加を実現するものとする。
・返品の削減や欠品に対するペナルティの見直しについて
集貨・配達に係る運転者への負荷の低減のためには、納品期限の緩和や賞味期限の大括り化、外装等の汚破損基準の見直し等による返品の削減や、欠品に対するペナルティの見直しに向けた関係事業者の理解と実践が必要であり、そのためにも、最終購買者である消費者の理解の増進が必要である。
・「送料無料」表示の見直しについて
消費者の物流サービスに対するコスト意識の浸透と、集貨又は配達に携わる運転者に対する社会的な理解の醸成のため、商取引において物流サービスが無償で提供されているとの誤解を招かないよう「送料無料」等の表現は見直しが求められている。このため、「送料として商品価格以外の追加負担を求めない」旨の表示をする事業者は、その表示について説明責任を果たす必要がある。また、国は、消費者や事業者の理解を醸成するための取組を積極的に進める必要がある。
・ 令和10年度までに、日本全体のトラック輸送のうち5割の運行で荷待ち・荷役等時間を1時間削減することで、トラックドライバー1人当たり年間125時間の短縮を実現すること。
・ 国及び地方公共団体は、それぞれの立場から、再配達の削減や、路上を含め貨物集配中の車両が駐車できるスペースの確保等に取り組み、集貨・配達に係るトラックドライバーへの負荷の低減を図ること。
・ 荷主は、トラックドライバーの拘束時間を削減するため、有料道路利用料の適切な負担のもと、トラック事業者に高速道路の利用を促すこと。
・新物効法第47条及び第66条では、特定事業者のうち特定荷主及び特定連鎖化事業者に物流統括管理者(CLO26)の選任を義務付けている。
以下、文章がものすごく長いので、大事そうな箇所付近はマーカーを引いておきます。
【用語集】
荷主(物流法)
第一種荷主及び第二種荷主をいう。
荷主(貨物法)
一 貨物自動車運送事業者(第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下この項、第十二条、第二十四条の五及び第三十七条において同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者
二 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者(他人のために貨物を受け取る者を除き、その者に受け取らせる者を含む。)(前号に掲げる者を除く。)
三 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者(他人のために貨物を引き渡す者を除き、その者に引き渡させる者を含む。)(第一号に掲げる者を除く。)
第一種荷主(物流法)
自らの事業(貨物の運送の事業を除く。)に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び貨物利用運送事業法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)に貨物の運送を行わせることを内容とする契約(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約を除く。)を締結する者をいう。
第二種荷主(物流法)
イ 自らの事業(貨物の運送及び保管の事業を除く。ロにおいて同じ。)に関して継続して貨物(自らが貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託する貨物を除く。ロ及び第三十七条第四項において同じ。)を運転者(他の者に雇用されている運転者に限る。以下この号において同じ。)から受け取る者又は他の者をして運転者から受け取らせる者
ロ 自らの事業に関して継続して貨物を運転者に引き渡す者又は他の者をして運転者に引き渡させる者
貨物自動車関連事業者(物流法)
イ 倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下「倉庫業者」という。)
ロ 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に掲げる事業を経営する者であって、当該事業について運転者との間で貨物の受渡しを行うもの
ハ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであって、当該航空運送事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者
ニ 鉄道事業法第二条第二項の第一種鉄道事業又は同条第三項の第二種鉄道事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであって、当該第一種鉄道事業又は当該第二種鉄道事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者
特定荷主(物流法)
(第一種特定荷主)
荷主事業所管大臣は、第一種荷主のうち、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。次項及び第三項第二号において同じ。)を行わせた貨物について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第三項第二号において「基準重量」という。)以上(鈴木注:取扱貨物の重量9万トン以上)であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。
(第二種特定荷主)
荷主事業所管大臣は、第二種荷主のうち、次に掲げる貨物(当該第二種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該第二種荷主が貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができないものを除く。次項及び第七項第二号において同じ。)について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第七項第二号において「基準重量」という。)以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。
一 自らの事業に関して、運転者から受け取る貨物
二 自らの事業に関して、他の者をして運転者から受け取らせる貨物
三 自らの事業に関して、運転者に引き渡す貨物
四 自らの事業に関して、他の者をして運転者に引き渡させる貨物
真荷主(貨物法)
自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のもの
元請事業者(貨物法)
実運送体制管理簿を作成する義務のある一般貨物自動車運送事業者=真荷主から引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する事業者(要するに下請以降は実運送体制管理簿の作成義務は無い)
今のところ、おそらく下請構造は2次下請けまでに制限するというルールは決まっていないと思います。明確に決まっているのであれば教えてください。
| 真荷主 ↓ ←実運送体制管理簿作成義務無し 元請事業者(実運送体制管理簿作成義務あり。下請事業者に元請事業者連絡先、真荷主情報、その他実運送体制管理簿作成に必要な情報を通知) ↓ 一次下請け運送事業者(下請事業者に元請事業者連絡先、真荷主情報、その他実運送体制管理簿作成に必要な情報を通知。元請事業者に実運送体制管理簿の内容を通知) ↓ 二次下請け運送事業者(下請事業者に元請事業者連絡先、真荷主情報、その他実運送体制管理簿作成に必要な情報を通知。元請事業者に実運送体制管理簿の内容を通知) |
物流統括管理者(CLO)(物流法)
新物効法第47条及び第66条では、特定事業者のうち特定荷主及び特定連鎖化事業者(鈴木注:取扱貨物の重量9万トン以上)に物流統括管理者(CLO26)の選任を義務付けている。
物流全体の持続可能な提供の確保に向けた業務全般を統括管理する者。物流統括管理者(CLO)の選任義務のある特定貨物自動車運送事業者については保有車両台数150台以上等(案)
実運送体制管理簿(貨物法)
元請貨物事業者(元請けのみ)の義務 1.5トン以上の荷物を下請け使う場合
営業所に備え置くが、荷主に見せる義務は無いが真荷主は、貨物の運送を委託した元請事業者に対してその業務取扱時間内はいつでも閲覧要望できる。
一 真荷主から引き受けた貨物の運送について実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称
二 前号の貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間
三 第一号の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。)
この義務は以下の箇所は免除されます
| 一般貨物自動車運送事業者 ↓ ←実運送体制管理簿作成義務無し 第一種貨物利用運送事業者 ↓ 一般貨物自動車運送事業者 |
運送利用管理規程の作成・運送利用管理者(貨物法)
利用で出す荷物が年間100万トン以上(自社で運ぶのは無関係)
※100万トン=1日3600トンというのは結構な量だと思います。これに該当する事業者のことを特別一般貨物自動車運送事業者と言います
特別一般貨物自動車運送事業者(貨物法)
貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。その規模は、利用で出す荷物が年間100万トン以上(自社で運ぶのは無関係)です。※100万トン=1日3600トンというのは結構な量だと思います)
特別一般貨物自動車運送事業者は運送利用管理規程の作成・運送利用管理者選任が必要です。それより小規模の運送事業者は運送利用管理規程の作成と運送利用管理者の選任は不要です。
特定貨物自動車運送事業者(物流法)
国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等のうち、政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力が政令で定める輸送能力(次項及び第三項第二号において「基準能力」という。)以上であるものを、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を特に増加させる必要がある者として指定するものとする。
特定貨物自動車運送事業者(貨物法)
特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をする者
今回の改正で出てきたものではなく昔からありますが、物流法で全く同じ言葉が登場してしまったので、違いをここで明確にしておきました。
運送契約締結時等の書面交付義務関係
真荷主と貨物自動車運送事業者が運送契約するとき、貨物自動車運送事業者等が他の貨物自動車運送事業者々の行う運送を利用するときに必要
元請事業者の下請事業者への通知義務
一 当該元請事業者の連絡先(<※鈴木注>下請事業者はこれを使って元請事業者への通知を行う)
二 当該他の貨物自動車運送事業者が運送する貨物の真荷主の商号又は名称
三 その他国土交通省令で定める事項
一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)の下請け事業者への通知義務
一 当該貨物の運送に係る元請連絡事項
二 当該他の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該他の貨物自動車運送事業者が引き受けた貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。)<※鈴木注>要するに「あなたは○次請けだよ」と伝えるということ
三 その他国土交通省令で定める事項
下請事業者の実運送事業者
元請事業者に実運送体制管理簿の内容を通知しなければならない
改正貨物自動車運送事業法の概要
1.運送契約締結時等の書面交付義務関係
<第12 条関係>
○ 真荷主(※1)と貨物自動車運送事業者(※2)が運送契約を締結するときは、運送の役務の内容(運送契約に附帯業務が含まれる場合にはその内容)及びその対価等について記載した書面を相互に交付しなければならないこととする(※3)。
<第24 条第2項及び第3項関係>
○ 貨物自動車運送事業者等が他の貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用するとき(※4)は、運送の役務の内容(その利用する運送に附帯業務が含まれる場合にはその内容)及びその対価等について記載した書面を当該他の貨物自動車運送事業者等に対して交付しなければならないこととする(※3)。
※1 真荷主とは「自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のもの」をいう。以下同じ。
※2 当該貨物自動車運送事業者については、一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者が該当する。
※3 書面交付の相手方から承諾を得た場合は、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
※4 具体的には以下の4通りの場合に適用される。
① 一般貨物自動車運送事業者が他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合
② 特定貨物自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合
③ 第一種貨物利用運送事業者(下請構造の中にいる場合に限る。)が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合
④ 第一種貨物利用運送事業者(下請構造の中にいる場合に限る。)が他の第一種貨物利用運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合
2.健全化措置関係
<第24 条第1項関係>
○ 貨物自動車運送事業者等は、他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するとき(※5)は、当該他の貨物自動車運送事業者の健全な運営を確保するための措置(以下「健全化措置」という。)を講ずるよう努めなければならないこととする。
<第24 条の2~第24 条の4関係>
○ 一定の規模以上の貨物自動車利用運送を行う貨物自動車運送事業者(※6)は、運送利用管理規程(健全化措置の実施に関する規程)を定めるとともに、運送利用管理者(健全化措置の実施及びその管理の体制を確保するために選任される者)を選任し、国土交通大臣に届け出なければならないこととする。
※5 具体的には以下の3通りの場面に適用される。
① 一般貨物自動車運送事業者が他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合
② 特定貨物自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合
③ 第一種貨物利用運送事業者(下請け構造の中にいる場合に限る。)が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合
※6 当該貨物自動車運送事業者については、一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者が該当する。また、一定の規模以上の貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者を「特別一般貨物自動車運送事業者」、特定貨物自動車運送事業者を「特別特定貨物自動車運送事業者」という。
3.実運送体制管理簿の作成・保存義務関係
<第24 条の5関係>
○ 貨物自動車運送事業者(※7)は、真荷主から引き受けた一定の重量以上の貨物の運送について、他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用したときは、実運送事業者の商号又は名称等を記載した実運送体制管理簿を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から一年間、これを営業所に据え置かなければならないこととする。
※7 当該貨物自動車運送事業者については、一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者が該当する。
貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令案について
令和6年10 月 物流・自動車局貨物流通事業課
1.背景
第213 回国会において、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23 号。以下「改正法」という。)が成立し、令和6年5月15 日に公布された。
改正法第4条では、貨物自動車運送事業における多重下請構造の是正を図るため、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83 号。以下「法」という。)において、運送契約締結時等の書面交付義務、下請事業者の健全な事業運営の確保に資する取組を行う努力義務、当該取組に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務(一定規模以上の事業者に限る。)、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務等について規定し、当該規定については、改正法の公布後1 年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行するとされたところである。今般、上記について国土交通省令に委任された内容等を踏まえ、貨物自動車運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第21 号。以下「施行規則」という。)、国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成17 年国土交通省令第26 号。以下「e-文書法施行規則」という。)等について所要の改正を行う必要がある。
2.概要
(1)貨物自動車運送事業法施行規則の一部改正
<運送契約締結時等の書面交付義務関係>
①運送契約に係る書面への記載事項等(新設)
法第12 条第1項(第36 条第2項において準用する場合を含む。)及び第24条第2項(第35 条第6項及び第37 条第1項において準用する場合を含む。)規定により行う運送契約に係る書面(以下単に「書面」という。)の交付について、当該書面に記載すべき事項として、契約の当事者の氏名又は名称及び住所、有料道路の通行に係る料金・燃料価格の変動に伴い追加的に必要となる燃料費に係る料金(いわゆる燃料サーチャージ)その他の特別に生ずる費用に係る料金、運賃及び料金の支払の方法、書面を交付した年月日を定めるとともに、当該交付義務の例外事由として、災害その他緊急やむを得ない場合を定める。
また、当該書面の写しを書面の交付日から1年間保存しなければならないこととする。
②書面の交付に代えることができる電磁的方法(新設)
法第12 条第3項(第36 条第2項において準用する場合を含む。)及び第24条第3項(第35 条第6項及び第37 条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、書面の交付に代えることができる電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法のほか、電磁的記録媒体に記録する方法等とする。
③電磁的方法により書面に記載すべき事項を提供しようとする場合における書面交付の相手方の承諾を得る方法(新設)
電磁的方法により書面に記載すべき事項を提供しようとする場合における、書面交付の相手方の承諾を得るための情報通信の技術を利用する方法は、電子情報処理組織を使用する方法のほか、承諾をする旨を記録した電磁的記録媒体を交付する方法とする。
<運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任義務関係>
④運送利用管理規程の作成及び運送利用管理者の選任を行う貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模(新設)
法第24 条の2第1項(第35 条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づく運送利用管理規程の作成義務及び第24 条の3第1項(第35 条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づく運送利用管理者の選任義務の対象となる事業者が行う貨物自動車利用運送の規模は、前年度におけるその行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が100 万トン以上であることとする。
⑤運送利用管理規程の作成及び変更並びに運送利用管理者の選任及び解任の届出(新設)
法第24 条第1 項(第35 条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づく運送利用管理規程の作成及び変更の届出、並びに法第24 条の3第3項(第35 条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づく運送利用管理者の選任及び解任の届出について、その届出事項を定めるとともに、運送利用管理規程の作成の届出の期限を、その行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が100 万トン以上となった年度の翌年度の7月10 日までとする。
ただし、当該年度以前にすでに運送利用管理規程の作成の届出をしているときは、改めて届出をする必要がない旨を定める。
⑥運送利用管理規程の作成及び変更並びに運送利用管理者の選任及び解任の届出の受理に係る権限の委任(第42 条関係)
運送利用管理規程の作成及び変更並びに運送利用管理者の選任及び解任の届出の受理に係る権限を地方運輸局長に委任することとする。
<実運送体制管理簿の作成・保存義務関係>
⑦実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限等(新設)
法第24 条の5(第35 条第6項において準用する場合を含む。)の規定による実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量は、1.5 トン以上とする。また、実運送体制管理簿の作成は、貨物の運送が完了した後、遅滞なく、行うものとする。
⑧実運送体制管理簿を貨物の運送ごとに作成することを要しない場合(新設)
真荷主と元請事業者との間において、「元請事業者が実運送を行わない場合には常に同一の貨物自動車運送事業者が実運送を行う」旨の契約が締結されている場合は、実運送体制管理簿を貨物の運送ごとに作成することを要しないこととする。
上記により貨物の運送ごとに作成しない場合の実運送体制管理簿には、法24条の5第1項各号に掲げる事項のほか、当該契約の期間を記載するものとし、元請事業者は、当該実運送体制管理簿に記載した貨物の運送が完了した日から、当該契約が満了する日までの期間又は1年間のいずれか長い期間、これを営業所に備え置くものとする。
⑨電磁的記録に記録された事項を表示する方法(新設)
法第24 の5第6項第2号(第35 条第6項において準用する場合を含む。)に規定する、実運送体制管理簿が電磁的記録をもって作成されているときの当該電磁的記録に記録された事項を表示する方法は、当該事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
<その他>
⑩その他所要の改正
改正法施行に伴う条ズレの手当や準用規定の整備等所要の改正を行う。
(2)国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情
報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正
次に掲げる法令の規定をe-文書法施行規則別表第一に追加することで、当該規定に基づく保存を電磁的記録により行うことができることとする。
・法第24 条の5第1項(第35 条第6項において準用する場合を含む。)
・本省令案により貨物自動車運送事業法施行規則に新設される規定のうち、(1)
①の書面の保存に関する規定
(3)その他関係省令の一部改正
改正法施行に伴う条ズレの手当等所要の改正を行う。
3.今後のスケジュール(予定)
公 布:令和7年1月
施 行:改正法の施行の日(令和7年4月)
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案
第二一三回 閣第一九号
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案
(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正)
第一条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
物資の流通の効率化に関する法律
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条-第三条)
第二章 流通業務の総合化及び効率化
第一節 総則(第四条・第五条)
第二節 総合効率化計画の認定等(第六条-第九条)
第三節 流通業務総合効率化事業の促進(第十条-第二十八条)
第四節 雑則(第二十九条)
第三章 運転者の運送及び荷役等の効率化
第一節 総則(第三十条-第三十三条)
第二節 貨物自動車運送事業者等に係る措置(第三十四条-第三十六条)
第三節 荷主に係る措置(第三十七条-第四十条)
第四節 貨物自動車関連事業者に係る措置(第四十一条-第四十三条)
第五節 貨物自動車運送事業者に係る特別の措置等
第一款 第一種荷主との間で運送契約を締結する場合における貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者に係る特別の措置(第四十四条)
第二款 連鎖化事業者に係る措置(第四十五条-第四十八条)
第六節 雑則(第四十九条)
第四章 雑則(第五十条-第五十二条)
第五章 罰則(第五十三条・第五十四条)
附則
第一条中「労働力」の下に「、とりわけ必要な員数の運転者」を加え、「について定めることにより、流通業務の総合化及び効率化の促進」を「を定めるとともに、貨物自動車を用いた貨物の運送の役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し貨物自動車運送事業者等、荷主及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置等を定めることにより、物資の流通の効率化」に改める。
第二章から第六章までの章名を削る。
第三十一条中「第二十条の二第二項」を「第二十三条第二項」に改め、同条を第五十四条とする。
第三十条第一項中「第二十六条」を「第二十九条」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条を第五十三条とする。
第二十九条中「この法律による」を「第二章に規定する」に改め、「権限」の下に「並びに前章第三節に規定する荷主事業所管大臣及び同章第五節第二款に規定する連鎖化事業所管大臣の権限」を加え、同条を第五十二条とし、同条の次に次の章名を付する。
第五章 罰則
第二十八条中「この法律」を「第二章」に改め、同条を第五十一条とする。
第二十七条第一項中「この法律」を「第二章」に改め、同条第二項中「この法律」を「第二章」に改め、「主務省令は、」の下に「第一項に定める」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三十三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣とする。
第二十七条に次の二項を加える。
4 前章第三節における主務省令は、荷主事業所管大臣の発する命令とする。
5 前章第五節第二款における主務省令は、連鎖化事業所管大臣の発する命令とする。
第二十七条を第五十条とする。
第二十六条の見出しを削り、同条を第二十九条とし、同条の次に次の一章及び章名を加える。
第三章 運転者の運送及び荷役等の効率化
第一節 総則
(定義)
第三十条 この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 貨物自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車であって、貨物の運送の用に供するものをいう。
二 運転者 貨物自動車の運転者をいう。
三 荷待ち時間等 荷待ち時間及び荷役等時間をいう。
四 荷待ち時間 運転者が貨物自動車の運転の業務に従事した時間のうち、集貨若しくは配達を行うべき場所又はその周辺の場所において、荷主、当該場所の管理者その他国土交通省令で定める者の都合により貨物の受渡しのために待機した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。
五 荷役等時間 運転者が荷役その他貨物自動車の運転以外の業務として国土交通省令で定める業務(以下「荷役等」という。)に従事した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。
六 貨物自動車運送事業者等 貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者(以下「貨物自動車運送事業者」という。)及び同法第三十七条の二第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者をいう。
七 荷主 第一種荷主及び第二種荷主をいう。
八 第一種荷主 自らの事業(貨物の運送の事業を除く。)に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び貨物利用運送事業法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)に貨物の運送を行わせることを内容とする契約(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約を除く。)を締結する者をいう。
九 第二種荷主 次に掲げる者をいう。
イ 自らの事業(貨物の運送及び保管の事業を除く。ロにおいて同じ。)に関して継続して貨物(自らが貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託する貨物を除く。ロ及び第三十七条第四項において同じ。)を運転者(他の者に雇用されている運転者に限る。以下この号において同じ。)から受け取る者又は他の者をして運転者から受け取らせる者
ロ 自らの事業に関して継続して貨物を運転者に引き渡す者又は他の者をして運転者に引き渡させる者
十 貨物自動車関連事業者 次に掲げる者をいう。
イ 倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下「倉庫業者」という。)
ロ 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に掲げる事業を経営する者であって、当該事業について運転者との間で貨物の受渡しを行うもの
ハ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであって、当該航空運送事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者
ニ 鉄道事業法第二条第二項の第一種鉄道事業又は同条第三項の第二種鉄道事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであって、当該第一種鉄道事業又は当該第二種鉄道事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者
(国の責務)
第三十一条 国は、貨物自動車運送役務(貨物自動車を用いた貨物の運送の役務をいう。以下同じ。)の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化並びに輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に関する情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の援助並びに研究開発の推進に努めなければならない。
2 国は、広報活動その他の活動を通じて、集貨又は配達に係る運転者への負荷の低減に資する施策に関して国民の理解を深めるとともに、その施策の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
(事業者等の責務)
第三十二条 物資の流通に関する事業を行う者、その事業を利用する事業者及び物資の流通に関する施設を管理する者は、その事業の実施又はその施設の管理に関し、これらに伴う運転者への負荷の低減その他の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。
(基本方針)
第三十三条 主務大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の意義及び目標に関する事項
二 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する施策に関する基本的な事項
三 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し、貨物自動車運送事業者等、荷主及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項
四 集貨又は配達に係る運転者への負荷の低減に資する事業者の活動に関する国民の理解の増進に関する基本的な事項
五 その他貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関し必要な事項
3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関)に協議するものとする。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第二節 貨物自動車運送事業者等に係る措置
(貨物自動車運送事業者等の努力義務)
第三十四条 貨物自動車運送事業者等は、自らの事業に伴うその雇用する運転者への負荷の低減に資するよう当該運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、輸送網の集約、配送の共同化その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項)
第三十五条 国土交通大臣は、基本方針に基づき、国土交通省令で、前条に規定する措置に関し、貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(指導及び助言)
第三十六条 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等の第三十四条に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貨物自動車運送事業者等に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
第三節 荷主に係る措置
(荷主の努力義務)
第三十七条 第一種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。)には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 貨物の運送の委託の時から貨物を引き渡し、又は受け取るべき時までの間に、貨物自動車運送事業者等が他の貨物との積合せその他の措置により、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を増加させることができるよう、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を決定すること。
二 貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を決定するに当たっては、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないようにすること。
三 運転者に荷役等を行わせる場合にあっては、パレットその他の荷役の効率化に資する輸送用器具(貨物自動車に積み込むものに限る。第三項において同じ。)を運転者が利用できるようにする措置その他の運転者の荷役等を省力化する措置
2 前項の規定により第一種荷主が短縮すべき荷待ち時間等は、荷待ち時間にあっては次に掲げる施設又はその周辺の場所におけるものに、荷役等時間にあっては次に掲げる施設におけるものに限られるものとする。
一 当該第一種荷主が管理する施設
二 当該第一種荷主との間で当該貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設
3 第一項に規定する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加には、同項第三号に規定するパレットその他の荷役の効率化に資する輸送用器具を使用しないことにより増加した貨物の重量は含まれないものとする。
4 第二種荷主は、貨物を運転者から受け取り、若しくは他の者をして運転者から受け取らせ、又は運転者に引き渡し、若しくは他の者をして運転者に引き渡させる場合には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、次に掲げる措置(当該貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない場合にあっては、第三号に掲げる措置に限る。)を講ずるよう努めなければならない。
一 貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を運転者に指示するに当たっては、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないようにすること。
二 第一種荷主が第一項第一号に掲げる措置を円滑に実施するため貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯について協議したい旨を申し出た場合にあっては、これに応じて、必要な協力を行うこと。
三 運転者に荷役等を行わせる場合であり、かつ、運転者に荷役等の方法を指示することができる場合にあっては、貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査の効率的な実施その他の運転者の荷役等を省力化する措置
5 前項の規定により第二種荷主が短縮すべき荷待ち時間等は、荷待ち時間にあっては次に掲げる施設又はその周辺の場所におけるものに、荷役等時間にあっては次に掲げる施設におけるものに限られるものとする。
一 当該第二種荷主が管理する施設
二 当該第二種荷主との間で当該貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設
(荷主の判断の基準となるべき事項)
第三十八条 荷主の行う事業を所管する大臣(以下「荷主事業所管大臣」という。)は、基本方針に基づき、主務省令で、前条第一項及び第四項に規定する措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、運転者の荷待ち時間等及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(指導及び助言)
第三十九条 荷主事業所管大臣は、荷主の第三十七条第一項又は第四項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該荷主に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(国土交通大臣の意見)
第四十条 国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、前条の規定の運用に関し、荷主事業所管大臣に意見を述べることができる。
第四節 貨物自動車関連事業者に係る措置
(貨物自動車関連事業者の努力義務)
第四十一条 倉庫業者は、自ら管理する施設又はその周辺における運転者の荷待ち時間及び当該施設における運転者の荷役等時間の短縮を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 第一種荷主から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を運転者に伝達するに当たっては、当該第一種荷主が決定した貨物の受渡しを行うべき時間帯における当該施設の状況を考慮して、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないようにすること。
二 第二種荷主から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を運転者に伝達するに当たっては、当該第二種荷主が指示した貨物の受渡しを行うべき時間帯における当該施設の状況を考慮して、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないようにすること。
三 運転者に荷役等を行わせる場合にあっては、荷役等に係る停留場所の拡張、荷役等に先行する貨物の搬出又は荷役等に後続する貨物の搬入の迅速な実施その他の運転者が行う荷役等の円滑な実施を図るための措置
2 倉庫業者以外の貨物自動車関連事業者(第四十三条第二項において「貨物自動車関連輸送事業者」という。)は、自ら管理する施設における運転者の荷役等時間の短縮を図るため、前項第三号に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項)
第四十二条 国土交通大臣は、基本方針に基づき、国土交通省令で、前条に規定する措置に関し、貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、運転者の荷待ち時間等の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(指導及び助言)
第四十三条 国土交通大臣は、倉庫業者の第四十一条第一項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該倉庫業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
2 国土交通大臣は、貨物自動車関連輸送事業者の第四十一条第二項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貨物自動車関連輸送事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
第五節 貨物自動車運送事業者に係る特別の措置等
第一款 第一種荷主との間で運送契約を締結する場合における貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者に係る特別の措置
第四十四条 第一種荷主との間で運送契約を締結する貨物自動車運送事業者は、当該第一種荷主から引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合は、その利用する運送に係る貨物について当該第一種荷主からその実施する第三十七条第一項に規定する措置に関し協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。
2 第一種荷主との間で運送契約を締結する貨物利用運送事業者は、当該第一種荷主から引き受けた貨物の運送について貨物自動車運送事業者又は他の貨物利用運送事業者の行う運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合は、その利用する運送に係る貨物について当該第一種荷主からその実施する第三十七条第一項に規定する措置に関し協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。
第二款 連鎖化事業者に係る措置(鈴木注:連鎖化事業者というのはフランチャイザー事業者のことです。コンビニの本社などが想定されています)
(連鎖化事業者の努力義務)
第四十五条 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基づき、当該契約の相手方(以下この条において「連鎖対象者」という。)と運転者との間の貨物の受渡しの日及び時刻又は時間帯を運転者に指示することができるもの(以下「連鎖化事業者」という。)は、当該連鎖対象者が取り扱う貨物(当該連鎖対象者が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該連鎖化事業者が当該契約に基づき受渡しの日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができないものを除く。以下この款において同じ。)について、当該連鎖対象者が運転者から受け取り、又は他の者をして運転者から受け取らせる場合には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を運転者に指示するに当たっては、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないようにすること。
二 第一種荷主が第三十七条第一項第一号に掲げる措置を円滑に実施するため貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯について協議したい旨を申し出た場合にあっては、これに応じて、必要な協力を行うこと。
2 前項の規定により連鎖化事業者が短縮すべき荷待ち時間は、次に掲げる施設又はその周辺の場所におけるものに限られるものとする。
一 当該連鎖対象者が管理する施設
二 当該連鎖対象者との間で当該貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設
(連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項)
第四十六条 連鎖化事業者の行う事業を所管する大臣(以下「連鎖化事業所管大臣」という。)は、基本方針に基づき、主務省令で、前条第一項に規定する措置に関し、連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、運転者の荷待ち時間及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(指導及び助言)
第四十七条 連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者の第四十五条第一項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該連鎖化事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(国土交通大臣の意見)
第四十八条 国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、前条の規定の運用に関し、連鎖化事業所管大臣に意見を述べることができる。
第六節 雑則
第四十九条 国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化のために必要があると認めるときは、第三十五条第一項、第三十八条第一項、第四十二条第一項及び第四十六条第一項に規定する判断の基準となるべき事項について調査を行い、その結果を公表するものとする。
第四章 雑則
第二十五条を第二十八条とし、同条の次に次の節名を付する。
第四節 雑則
第二十四条を第二十七条とし、第二十一条から第二十三条までを三条ずつ繰り下げる。
第二十条の二第一項第一号中「資金の」の下に「出資及び」を加え、同条を第二十三条とする。
第二十条第二項の表第十八条第一項の項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「流通業務総合効率化促進法」を「物資流通効率化法」に、「第二十条第一項第一号」を「第二十二条第一項第一号」に改め、同表第十九条第一項の項中「流通業務総合効率化促進法第二十条第一項第一号」を「物資流通効率化法第二十二条第一項第一号」に改め、同表第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号の項中「流通業務総合効率化促進法第二十条第一項各号」を「物資流通効率化法第二十二条第一項各号」に改め、同表第二十五条第一項第三号の項中「流通業務総合効率化促進法」を「物資流通効率化法」に改め、同表第三十二条第二号の項及び第三十二条第三号の項中「流通業務総合効率化促進法第二十条第二項」を「物資流通効率化法第二十二条第二項」に改め、同条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とする。
第十八条第一項の表第三条第一項の項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「第十八条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条を第二十条とする。
第十七条を削る。
第十六条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(港湾法の特例)
第十九条 港湾法第三十八条の二第一項の規定は、認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画(第六条第三項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。第二十四条において「特定認定総合効率化計画」という。)に従って同法第三十八条の二第一項の規定による届出を要する行為をする場合については、適用しない。
第十五条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十七条とする。
第十四条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十六条とする。
第十三条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十五条とする。
第十二条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十四条とする。
第十一条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十三条とする。
第十条の前の見出しを削り、同条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十二条とし、同条の前に見出しとして「(貨物自動車運送事業法の特例)」を付する。
第九条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第四項中「をいう」の下に「。第三十条第八号において同じ」を加え、同条を第十一条とする。
第八条の前の見出しを削り、同条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第四項中「をいう」の下に「。第三十条第八号において同じ」を加え、同条を第十条とし、同条の前に見出しとして「(貨物利用運送事業法の特例)」を付する。
第七条第一項及び第二項中「第四条第四項第十二号」を「第六条第四項第十二号」に改め、同条第三項中「第四条(第五条第四項」を「第六条(第七条第四項」に、「第四条第四項」を「第六条第四項」に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の節名を付する。
第三節 流通業務総合効率化事業の促進
第六条を第八条とし、第五条を第七条とする。
第四条第三項第一号中「及び規模」を「並びに規模、構造及び設備」に改め、同条第七項から第十一項までの規定中「、あらかじめ」を削り、同条を第六条とする。
第三条に見出しとして「(基本方針)」を付し、同条第一項中「以下」の下に「この章において」を加え、同条を第五条とし、同条の次に次の節名を付する。
第二節 総合効率化計画の認定等
第二条中「この法律」を「この章」に改め、同条第一号中「輸送」を「輸送、荷役」に、「係る業務」を「関する行為であって、業として行われるもの」に改め、同条第二号中「輸送、」を「輸送、荷役、」に改め、同条第五号中「第六条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条を第四条とする。
第一条の次に次の二条、章名及び節名を加える。
(基本理念)
第二条 物資の流通の効率化のための取組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 物資の流通は我が国における国民生活及び経済活動の基盤であることに鑑み、その担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送されることを旨とすること。
二 物資の流通は物資の生産及び製造の過程と密接に関連し、かつ、多様な主体により担われていることに鑑み、物資の生産又は製造を行う者、物資の流通の担い手その他の関係者が相互に連携を図ることにより、その取組の効果を一層高めることを旨とすること。
三 物資の流通の過程において二酸化炭素の排出等による環境への負荷が生じていることに鑑み、当該負荷の低減を図ることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨とすること。
(国の責務)
第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
第二章 流通業務の総合化及び効率化
第一節 総則
(物資の流通の効率化に関する法律の一部改正)
第二条 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十六条」を「第四十一条」に、「第三十七条-第四十条」を「第四十二条-第五十一条」に、「第四十一条-第四十三条」を「第五十二条-第五十九条」に、「第四十四条」を「第六十条」に、「第四十五条-第四十八条」を「第六十一条-第七十条」に、「第四十九条」を「第七十一条」に、「第五十条-第五十二条」を「第七十二条-第七十四条」に、「第五十三条・第五十四条」を「第七十五条-第八十条」に改める。
第三十条第九号イ中「ロにおいて」を「ロ及び第四十五条第五項において」に、「第三十七条第四項」を「第四十二条第四項」に改める。
第五十四条を第七十九条とし、同条の前に次の一条を加える。
第七十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第五十三条第二項を削り、同条を第七十七条とし、第五章中同条の前に次の二条を加える。
第七十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第四十条第三項、第四十九条第三項、第五十八条第三項又は第六十八条第三項の規定による命令に違反したとき。
二 第四十七条第一項又は第六十六条第一項の規定に違反したとき。
第七十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十七条第二項、第四十五条第二項若しくは第六項、第五十五条第二項若しくは第六十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第三十八条、第四十六条、第五十六条又は第六十五条の規定による提出をしなかったとき。
三 第三十九条、第四十八条、第五十七条若しくは第六十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第四十一条第一項若しくは第二項、第五十条第一項若しくは第二項、第五十九条第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第四章中第五十二条を第七十四条とし、第五十一条を第七十三条とし、第五十条を第七十二条とする。
第四十九条中「第三十八条第一項、第四十二条第一項及び第四十六条第一項」を「第四十三条第一項、第五十三条第一項及び第六十二条第一項」に改め、第三章第六節中同条を第七十一条とする。
第四十八条中「前条」を「第六十三条及び第六十八条」に改め、第三章第五節第二款中同条を第七十条とする。
第四十七条中「第四十五条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同条を第六十三条とし、同条の次に次の六条を加える。
(特定連鎖化事業者の指定)
第六十四条 連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者のうち、次に掲げる貨物について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第三項第二号において「基準重量」という。)以上であるものを、運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。
一 当該連鎖化事業者の連鎖対象者が運転者から受け取る貨物
二 当該連鎖化事業者の連鎖対象者が他の者をして運転者から受け取らせる貨物
2 連鎖化事業者は、前項各号に掲げる貨物の重量について、同項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の合計の重量が基準重量以上であるときは、主務省令で定めるところにより、当該連鎖化事業者の連鎖対象者の貨物の受渡しの状況に関し、主務省令で定める事項を連鎖化事業所管大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された連鎖化事業者(以下「特定連鎖化事業者」という。)であるときは、この限りでない。
3 特定連鎖化事業者は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、主務省令で定めるところにより、連鎖化事業所管大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 連鎖化事業者に該当しなくなったとき。
二 第一項各号に掲げる貨物の重量について、同項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が基準重量を下回った場合において、同項の政令で定めるところにより算定する年度の貨物の合計の重量が再び当該基準重量以上となることがないと明らかに認められるとき。
4 連鎖化事業所管大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じたと認められるときも、同様とする。
(中長期的な計画の作成)
第六十五条 特定連鎖化事業者は、主務省令で定めるところにより、定期に、第六十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第六十一条第一項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、連鎖化事業所管大臣に提出しなければならない。
(物流統括管理者の選任)
第六十六条 特定連鎖化事業者は、第六十四条第一項の規定による指定を受けた後、速やかに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務を統括管理する者(以下この条において「物流統括管理者」という。)を選任しなければならない。
一 前条の中長期的な計画の作成
二 当該特定連鎖化事業者の連鎖対象者の事業に係る貨物の運送を行う運転者への負荷を低減し、及び輸送される物資の貨物自動車への過度の集中を是正するための事業の運営方針の作成及び事業の管理体制の整備に関する業務
三 その他運転者の運送の効率化のために必要な業務として主務省令で定める業務
2 物流統括管理者は、特定連鎖化事業者が行う事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者をもって充てなければならない。
3 特定連鎖化事業者は、第一項の規定により物流統括管理者を選任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を連鎖化事業所管大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(定期の報告)
第六十七条 特定連鎖化事業者は、第六十四条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、主務省令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を連鎖化事業所管大臣に報告しなければならない。
(勧告及び命令)
第六十八条 連鎖化事業所管大臣は、特定連鎖化事業者の第六十一条第一項に規定する措置の実施に関する状況が、第六十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 連鎖化事業所管大臣は、前項の勧告を受けた特定連鎖化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 連鎖化事業所管大臣は、第一項の勧告を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等の意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告徴収及び立入検査)
第六十九条 連鎖化事業所管大臣は、第六十四条第一項の規定による指定及び同条第四項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、連鎖化事業者に対し、その連鎖対象者の貨物の受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、連鎖化事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 連鎖化事業所管大臣は、前条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、特定連鎖化事業者に対し、第六十一条第一項に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定連鎖化事業者若しくは当該特定連鎖化事業者の連鎖対象者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該連鎖対象者の事務所その他の事業場に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該連鎖対象者の承諾を得なければならない。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四十六条を第六十二条とする。
第四十五条第一項中「この条において」を削り、同項第二号中「第三十七条第一項第一号」を「第四十二条第一項第一号」に改め、同条を第六十一条とする。
第四十四条中「第三十七条第一項」を「第四十二条第一項」に改め、第三章第五節第一款中同条を第六十条とする。
第四十三条第一項中「第四十一条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同条第二項中「第四十一条第二項」を「第五十二条第二項」に改め、第三章第四節中同条を第五十四条とし、同条の次に次の五条を加える。
(特定倉庫業者の指定)
第五十五条 国土交通大臣は、倉庫業者のうち、政令で定めるところにより算定した年度の貨物の保管量が政令で定める保管量(次項及び第三項第二号において「基準保管量」という。)以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。
2 倉庫業者は、前項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の保管量が基準保管量以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、貨物の保管量の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された倉庫業者(以下「特定倉庫業者」という。)であるときは、この限りでない。
3 特定倉庫業者は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 貨物の保管の事業を行わなくなったとき。
二 第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の保管量が基準保管量を下回った場合において、同項の政令で定めるところにより算定する年度の貨物の保管量が再び当該基準保管量以上となることがないと明らかに認められるとき。
4 国土交通大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じたと認められるときも、同様とする。
(中長期的な計画の作成)
第五十六条 特定倉庫業者は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第五十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第五十二条第一項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(定期の報告)
第五十七条 特定倉庫業者は、第五十五条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、第五十二条第一項に規定する措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
(勧告及び命令)
第五十八条 国土交通大臣は、特定倉庫業者の第五十二条第一項に規定する措置の実施に関する状況が、第五十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定倉庫業者に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた特定倉庫業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた特定倉庫業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、運輸審議会の意見を聴いて、当該特定倉庫業者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告徴収及び立入検査)
第五十九条 国土交通大臣は、第五十五条第一項の規定による指定及び同条第四項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、倉庫業者に対し、その貨物の保管量の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、倉庫業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 国土交通大臣は、前条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、特定倉庫業者に対し、第五十二条第一項に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定倉庫業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四十二条を第五十三条とする。
第四十一条第二項中「第四十三条第二項」を「第五十四条第二項」に改め、同条を第五十二条とする。
第四十条中「前条」を「第四十四条及び第四十九条」に改め、第三章第三節中同条を第五十一条とする。
第三十九条中「第三十七条第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同条を第四十四条とし、同条の次に次の六条を加える。
(特定荷主の指定)
第四十五条 荷主事業所管大臣は、第一種荷主のうち、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。次項及び第三項第二号において同じ。)を行わせた貨物について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第三項第二号において「基準重量」という。)以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。
2 第一種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物の重量について、前項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の合計の重量が基準重量以上であるときは、主務省令で定めるところにより、貨物の運送の委託の状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された第一種荷主(以下「特定第一種荷主」という。)であるときは、この限りでない。
3 特定第一種荷主は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、主務省令で定めるところにより、荷主事業所管大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 第一種荷主に該当しなくなったとき。
二 貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物の重量について、第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が基準重量を下回った場合において、同項の政令で定めるところにより算定する年度の貨物の合計の重量が再び当該基準重量以上となることがないと明らかに認められるとき。
4 荷主事業所管大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じたと認められるときも、同様とする。
5 荷主事業所管大臣は、第二種荷主のうち、次に掲げる貨物(当該第二種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該第二種荷主が貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができないものを除く。次項及び第七項第二号において同じ。)について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第七項第二号において「基準重量」という。)以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。
一 自らの事業に関して、運転者から受け取る貨物
二 自らの事業に関して、他の者をして運転者から受け取らせる貨物
三 自らの事業に関して、運転者に引き渡す貨物
四 自らの事業に関して、他の者をして運転者に引き渡させる貨物
6 第二種荷主は、前項各号に掲げる貨物について、同項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の合計の重量が基準重量以上であるときは、主務省令で定めるところにより、貨物の受渡しの状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された第二種荷主(以下「特定第二種荷主」という。)であるときは、この限りでない。
7 特定第二種荷主は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、主務省令で定めるところにより、荷主事業所管大臣に、第五項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 第二種荷主に該当しなくなったとき。
二 第五項各号に掲げる貨物の重量について、同項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が基準重量を下回った場合において、同項の政令で定めるところにより算定する年度の貨物の合計の重量が再び当該基準重量以上となることがないと明らかに認められるとき。
8 荷主事業所管大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第五項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じたと認められるときも、同様とする。
(中長期的な計画の作成)
第四十六条 特定第一種荷主及び特定第二種荷主(以下「特定荷主」という。)は、主務省令で定めるところにより、定期に、第四十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第四十二条第一項又は第四項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、荷主事業所管大臣に提出しなければならない。
(物流統括管理者の選任)
第四十七条 特定荷主は、第四十五条第一項又は第五項の規定による指定を受けた後、速やかに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務を統括管理する者(以下この条において「物流統括管理者」という。)を選任しなければならない。
一 前条の中長期的な計画の作成
二 自らの事業に係る貨物の運送を行う運転者への負荷を低減し、及び輸送される物資の貨物自動車への過度の集中を是正するための事業の運営方針の作成及び事業の管理体制の整備に関する業務
三 その他運転者の運送及び荷役等の効率化のために必要な業務として主務省令で定める業務
2 物流統括管理者は、特定荷主が行う事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者をもって充てなければならない。
3 特定荷主は、第一項の規定により物流統括管理者を選任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を荷主事業所管大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(定期の報告)
第四十八条 特定荷主は、第四十五条第一項又は第五項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、主務省令で定めるところにより、第四十二条第一項又は第四項に規定する措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に報告しなければならない。
(勧告及び命令)
第四十九条 荷主事業所管大臣は、特定荷主の第四十二条第一項又は第四項に規定する措置の実施に関する状況が、第四十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 荷主事業所管大臣は、前項の勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 荷主事業所管大臣は、第一項の勧告を受けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第六十八条第三項において同じ。)の意見を聴いて、当該特定荷主に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告徴収及び立入検査)
第五十条 荷主事業所管大臣は、第四十五条第一項及び第五項の規定による指定並びに同条第四項及び第八項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、荷主に対し、その貨物の運送の委託若しくは受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 荷主事業所管大臣は、前条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、特定荷主に対し、第四十二条第一項若しくは第四項に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三十八条を第四十三条とし、第三十七条を第四十二条とする。
第三章第二節中第三十六条の次に次の五条を加える。
(特定貨物自動車運送事業者等の指定)
第三十七条 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等のうち、政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力が政令で定める輸送能力(次項及び第三項第二号において「基準能力」という。)以上であるものを、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を特に増加させる必要がある者として指定するものとする。
2 貨物自動車運送事業者等は、前項の政令で定めるところにより算定した前年度の輸送能力が基準能力以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された貨物自動車運送事業者等(以下「特定貨物自動車運送事業者等」という。)であるときは、この限りでない。
3 特定貨物自動車運送事業者等は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 貨物自動車を用いた貨物の運送の事業を行わなくなったとき。
二 第一項の政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力が基準能力を下回った場合において、同項の政令で定めるところにより算定する年度の輸送能力が再び当該基準能力以上となることがないと明らかに認められるとき。
4 国土交通大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じたと認められるときも、同様とする。
(中長期的な計画の作成)
第三十八条 特定貨物自動車運送事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第三十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第三十四条に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(定期の報告)
第三十九条 特定貨物自動車運送事業者等は、第三十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、第三十四条に規定する措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
(勧告及び命令)
第四十条 国土交通大臣は、特定貨物自動車運送事業者等の第三十四条に規定する措置の実施に関する状況が、第三十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物自動車運送事業者等に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた特定貨物自動車運送事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた特定貨物自動車運送事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、運輸審議会の意見を聴いて、当該特定貨物自動車運送事業者等に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告徴収及び立入検査)
第四十一条 国土交通大臣は、第三十七条第一項の規定による指定及び同条第四項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、貨物自動車運送事業者等に対し、その輸送能力の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、貨物自動車運送事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 国土交通大臣は、前条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、特定貨物自動車運送事業者等に対し、第三十四条に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定貨物自動車運送事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
本則に次の一条を加える。
第八十条 第四十七条第三項若しくは第六十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(貨物自動車運送事業法の一部改正)
第三条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 指定試験機関(第四十六条-第五十八条)」を
「第四章 指定試験機関等
第一節 指定試験機関(第四十六条-第五十八条)
第二節 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等(第五十八条の二-第五十八条の十六)」
に、「第七十九条」を「第八十二条」に改める。
第四章の章名を次のように改める。
第四章 指定試験機関等
第四章中第四十六条の前に次の節名を付する。
第一節 指定試験機関
第五十七条第二項第一号中「この章」を「この節」に改める。
第四章中第五十八条の次に次の一節を加える。
第二節 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等
(登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録)
第五十八条の二 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
(登録の要件等)
第五十八条の三 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る貨物軽自動車安全管理者講習について、当該講習に必要な書籍その他の教材を用いて、次の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者に講義を行わせるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 十八歳以上であること。
二 過去二年間に第三項第三号に規定する講習事務に関し不正な行為を行った者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。
三 運行管理者資格者証の交付を受けている者であって、一年以上運行管理者として職務を行った経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第五十八条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 前条の登録は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 貨物軽自動車安全管理者講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録事項の変更の届出)
第五十八条の四 第五十八条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関」という。)は、前条第三項第二号及び第三号に掲げる事項の変更をするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録の更新)
第五十八条の五 第五十八条の二の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第五十八条の二及び第五十八条の三の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(講習事務の実施に係る義務)
第五十八条の六 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、公正に、かつ、第五十八条の三第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
(講習事務規程)
第五十八条の七 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習事務規程には、貨物軽自動車安全管理者講習の実施方法、貨物軽自動車安全管理者講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(帳簿の備付け等)
第五十八条の八 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第五十八条の九 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。同項及び第八十二条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 貨物軽自動車安全管理者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第五十八条の十 国土交通大臣は、貨物軽自動車安全管理者講習が第五十八条の三第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第五十八条の十一 国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が第五十八条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、同条の規定による貨物軽自動車安全管理者講習を行うべきこと又は講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(講習事務の休廃止)
第五十八条の十二 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録の取消し等)
第五十八条の十三 国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十八条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第五十八条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第五十八条の四、第五十八条の七、第五十八条の八、第五十八条の九第一項又は前条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がなく、第五十八条の九第二項各号の請求を拒んだとき。
四 第五十八条の十又は第五十八条の十一の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第五十八条の二の登録を受けたとき。
(国土交通大臣による講習事務の実施等)
第五十八条の十四 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
一 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関がいないとき。
二 第五十八条の十二の規定による講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき。
三 前条の規定により第五十八条の二の登録を取り消し、又は登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が天災その他の事由により講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき。
2 国土交通大臣が前項の規定により講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(公示)
第五十八条の十五 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。
一 第五十八条の二の登録をしたとき。
二 第五十八条の四の規定による届出があったとき。
三 第五十八条の十二の規定による届出があったとき。
四 第五十八条の十三の規定により第五十八条の二の登録を取り消し、又は講習事務に関する業務の停止を命じたとき。
(登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関)
第五十八条の十六 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者定期講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
2 第五十八条の三から前条までの規定は、前項の登録、貨物軽自動車安全管理者定期講習及び同項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」という。)に関する事務について準用する。この場合において、第五十八条の三第三項中「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿」とあるのは「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関登録簿」と、第五十八条の五第二項中「第五十八条の二」とあるのは「第五十八条の十六第一項」と読み替えるものとする。
第六十条第二項中「以下」を「第五項において」に改め、同条第三項中「指定試験機関に対し、試験事務」を「次の各号に掲げる者から当該各号に定める事務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 指定試験機関 試験事務
二 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関 貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務
三 登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関 貨物軽自動車安全管理者定期講習の実施に関する事務
第六十条第五項中「又は指定試験機関」を「、指定試験機関、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」に改める。
第六十一条第一項中「運行管理者試験を受けようとする者又は運行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 運行管理者試験を受けようとする者
二 運行管理者資格者証の交付又は再交付を受けようとする者
三 貨物軽自動車安全管理者講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
四 貨物軽自動車安全管理者定期講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
第七十四条を削る。
第七十三条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「違反して運行管理者を選任しなかった者」を「違反したとき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同条を第七十四条とし、第七十二条の次に次の一条を加える。
第七十三条 第五十八条の十三(第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第七十五条を削る。
第七十六条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号を削り、同条第二号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第九条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更したとき。
第七十六条第四号及び第五号中「者」を「とき。」に改め、同条第六号中「の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかった者」を「又は第三十四条第三項(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。」に改め、同条第七号中「又は第十八条第三項」を「若しくは第十八条第三項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第八号を削り、同条第七号の二中「(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)」を削り、「、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者」を「一般貨物自動車運送事業を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。」に改め、同号を同条第八号とし、同条第十一号中「含む」の下に「。以下この号において同じ」を、「又は」の下に「第六十条第四項の規定による」を加え、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十号とし、同号の前に次の一号を加える。
九 第三十五条第六項において準用する第三十二条の規定による届出をしないで特定貨物自動車運送事業を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
第七十六条を第七十五条とする。
第七十七条第二号中「又は」の下に「同項の規定による」を加え、同条を第七十六条とする。
第七十九条を第八十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第八十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 第五十八条の九第一項(第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
二 正当な理由がなく、第五十八条の九第二項各号(第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者
第七十八条中「、第七十三条」を削り、「第七十六条」を「第七十五条」に改め、同条を第八十条とし、同条の前に次の三条を加える。
第七十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
一 第五十四条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第五十六条第一項の規定に違反して試験事務の全部を廃止したとき。
三 第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第七十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
一 第六十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第六十条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第七十九条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第五十八条の八(第五十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第五十八条の十二の規定による届出をしないで貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第五十八条の十六第二項において準用する第五十八条の十二の規定による届出をしないで貨物軽自動車安全管理者定期講習の実施に関する事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
附則第一条の二に次の一項を加える。
8 地方実施機関は、当分の間、貨物自動車運送事業者に対する荷主の行為が違反原因行為に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、その事実を国土交通大臣に通知するものとする。
第四条 貨物自動車運送事業法の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 貨物自動車運送事業(第三条-第三十七条)」を
「第二章 一般貨物自動車運送事業(第三条-第三十四条)
第三章 特定貨物自動車運送事業(第三十五条)
第四章 貨物軽自動車運送事業(第三十六条・第三十六条の二)
第五章 貨物利用運送事業者に関する特例(第三十七条・第三十七条の二)」
に、「第三章」を「第六章」に、「第四章」を「第七章」に、「第五章」を「第八章」に、「第六章」を「第九章」に改める。
第二条第六項中「単に」を削り、同条第七項中「使用して行う貨物の運送に係るものに限る」を「使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く」に改め、同条に次の一項を加える。
8 この法律において「荷主」とは、次に掲げる者をいう。
一 貨物自動車運送事業者(第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下この項、第十二条、第二十四条の五及び第三十七条において同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者
二 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者(他人のために貨物を受け取る者を除き、その者に受け取らせる者を含む。)(前号に掲げる者を除く。)
三 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者(他人のために貨物を引き渡す者を除き、その者に引き渡させる者を含む。)(第一号に掲げる者を除く。)
第二章の章名を次のように改める。
第二章 一般貨物自動車運送事業
第十二条から第十四条までを次のように改める。
(書面の交付)
第十二条 真荷主(自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のものをいう。第二十四条の五において同じ。)及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。
一 運送の役務の内容及びその対価
二 当該運送契約に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容及びその対価
三 その他国土交通省令で定める事項
2 前項の規定は、第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第七条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合であって、当該第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者である場合における当該第一種貨物利用運送事業者及び当該一般貨物自動車運送事業者が締結する運送契約については、適用しない。
3 第一項の運送契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該運送契約の当事者は、当該書面を交付したものとみなす。
(輸送の安全性の向上)
第十三条 一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
(安全管理規程等)
第十四条 一般貨物自動車運送事業者(その事業用自動車の数が国土交通省令で定める数未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、貨物の運送を開始する日(貨物の運送を開始した後、事業用自動車の数が当該国土交通省令で定める数以上になる場合にあっては、その日)までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般貨物自動車運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定める基準に適合するものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(一般貨物自動車運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般貨物自動車運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下この条において同じ。)の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項に規定する基準に適合しないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、当該基準に適合するようこれを変更すべきことを命ずることができる。
4 一般貨物自動車運送事業者は、安全管理規程の届出後、速やかに、安全統括管理者を選任しなければならない。
5 一般貨物自動車運送事業者は、前項の規定により安全統括管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
6 一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠った場合であって、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
第十五条及び第十六条を削る。
第十七条第三項中「(以下「過積載による運送」という。)」を削り、「、過積載による」を「、当該」に、「対する過積載による」を「対する当該」に改め、同条を第十五条とする。
第十八条第一項中「一般貨物自動車運送事業者は」の下に「、第三条の許可を受けた後、速やかに」を加え、同条第三項中「ときは」の下に「、国土交通省令で定めるところにより」を加え、「その旨」を「その氏名」に改め、同条を第十六条とし、第十九条を第十七条とし、第二十条を第十八条とし、第二十一条を第十九条とする。
第二十二条第二項中「第十八条第二項」を「第十六条第二項」に改め、同条を第二十条とする。
第二十二条の二中「第十五条、第十六条第一項」を「第十三条、第十四条第一項」に、「第十七条第一項」を「第十五条第一項」に、「第十八条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第二十一条とする。
第二十三条中「第十六条第一項」を「第十四条第一項」に、「第十七条第一項」を「第十五条第一項」に、「第十八条第一項、第二十二条第二項」を「第十六条第一項、第二十条第二項」に改め、同条を第二十二条とし、第二十四条を第二十三条とする。
第二十四条の二の見出し中「かかわる」を「関わる」に改め、同条中「第二十三条」を「第二十二条」に、「かかわる」を「関わる」に改め、同条を第二十三条の二とする。
第二十四条の三(見出しを含む。)中「かかわる」を「関わる」に改め、同条を第二十三条の三とする。
第二十八条を削り、第二十七条を第二十八条とし、第二十六条を第二十七条とし、第二十五条を第二十六条とし、第二十四条の四を第二十五条とし、同条の前に次の五条を加える。
(他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合の措置)
第二十四条 一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。第三号において同じ。)を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するため、次に掲げる措置(次条及び第二十四条の三において「健全化措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。
一 その利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、当該概算額を勘案して利用の申込みをすること。
二 自らが引き受ける貨物の運送について荷主が提示する運賃又は料金が前号に規定する概算額を下回る場合にあっては、当該荷主に対し、運賃又は料金について交渉をしたい旨を申し出ること。
三 当該他の一般貨物自動車運送事業者が更に他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する場合に関し二以上の段階にわたる委託の制限その他の条件を付すること。
四 その他一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するためのものとして国土交通省令で定める措置
2 一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受けた貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、国土交通省令で定める場合を除き、当該他の一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者に対し、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第三条第一項の規定による書面の交付(同条第二項の規定により書面を交付したものとみなされた場合を含む。)をしたときは、当該書面に記載した事項については記載することを要しない。
一 運送の役務の内容及びその対価
二 その利用する運送に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容及びその対価
三 その他国土交通省令で定める事項
3 一般貨物自動車運送事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該他の一般貨物自動車運送事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
(運送利用管理規程の作成等)
第二十四条の二 貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。)は、健全化措置の実施に関する規程(以下「運送利用管理規程」という。)を定め、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 運送利用管理規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
一 健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項
二 健全化措置の内容に関する事項
三 健全化措置の管理体制に関する事項
四 次条第一項に規定する運送利用管理者の選任に関する事項
3 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程を遵守しなければならない。
(運送利用管理者の選任等)
第二十四条の三 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程の届出後、速やかに、その事業における健全化措置の実施及びその管理の体制を確保するため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから、運送利用管理者一人を選任しなければならない。
2 運送利用管理者は、次に掲げる職務を行う。
一 健全化措置を実施するための事業の運営の方針を決定すること。
二 健全化措置の実施及びその管理の体制を整備すること。
三 第二十四条の五第一項に規定する実運送体制管理簿を作成する場合にあっては、当該実運送体制管理簿の作成事務を監督すること。
3 特別一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運送利用管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(運送利用管理者の義務等)
第二十四条の四 運送利用管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者に対し、前条第二項各号に掲げる職務を行うため必要な権限を与えなければならない。
3 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
(実運送体制管理簿の作成等)
第二十四条の五 一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送(その運送に係る貨物の重量が国土交通省令で定める重量以上であるものに限る。第六項において同じ。)について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、災害その他緊急やむを得ない場合を除き、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した実運送体制管理簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項及び第五十八条の九において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から一年間、これを営業所に備え置かなければならない。ただし、当該利用の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定める場合は、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない。
一 真荷主から引き受けた貨物の運送について実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称
二 前号の貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間
三 第一号の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。)
四 その他国土交通省令で定める事項
2 前項の規定は、一般貨物自動車運送事業者が第一種貨物利用運送事業者から貨物の運送を引き受けた場合であって、当該第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者であるときにおける当該一般貨物自動車運送事業者については、適用しない。
3 第一項の規定により実運送体制管理簿を作成する一般貨物自動車運送事業者(以下この条において「元請事業者」という。)は、同項ただし書の場合を除き、その利用する運送を行う他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項(次項第一号において「元請連絡事項」という。)を通知しなければならない。
一 当該元請事業者の連絡先
二 当該他の貨物自動車運送事業者が運送する貨物の真荷主の商号又は名称
三 その他国土交通省令で定める事項
4 一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、前項の規定による通知を受けていない場合その他これらの事項を知ることができない場合は、この限りでない。
一 当該貨物の運送に係る元請連絡事項
二 当該他の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該他の貨物自動車運送事業者が引き受けた貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。)
三 その他国土交通省令で定める事項
5 貨物自動車運送事業者は、他の貨物自動車運送事業者から貨物の運送を引き受け、第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け、かつ、その引き受けた貨物の運送について実運送を行うときは、当該通知に係る元請事業者に対し、当該実運送に係る貨物の真荷主ごとに、第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
6 真荷主は、貨物の運送を委託した元請事業者に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第一項の実運送体制管理簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 第一項の実運送体制管理簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第三十一条第一項中「以下」を「次項において」に改める。
第七十条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第二十七条第一項」を「第二十八条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第二十七条第二項」を「第二十八条第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第二十七条第一項」を「第二十八条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「第二十七条第二項」を「第二十八条第二項」に、「者」を「とき。」に改める。
第七十一条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「者」を「とき。」に改める。
第七十四条第一号中「第十八条第一項」を「第十六条第一項」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改め、同条第二号中「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改める。
第七十五条第一号中「第十六条第三項」を「第十四条第三項」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に、「第二十三条」を「第二十二条」に、「第二十四条の四第二項」を「第二十五条第二項」に、「第二十五条第四項、第二十六条」を「第二十六条第四項、第二十七条」に改め、同条第五号中「第十六条第一項」を「第十四条第一項」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に、「第十六条第二項第二号」を「第十四条第二項第二号」に改め、同条第六号中「第十六条第四項」を「第十四条第四項」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に、「又は」を「、第二十四条の三第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)、」に、「の規定」を「又は第三十六条の二第一項の規定」に改め、同条第七号中「第十六条第五項若しくは第十八条第三項」を「第十四条第五項若しくは第十六条第三項」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改め、「含む。)」の下に「、第二十四条の三第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条の二第二項」を加え、同条第十二号中「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号中「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 第二十四条の二第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た運送利用管理規程(第二十四条の二第二項第二号及び第三号(これらの規定を第三十五条第六項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行ったとき。
第八十一条第三号中「第二十条」を「第十八条」に改め、同条第四号中「第二十四条」を「第二十三条」に、「及び第三十七条第三項」を「、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項」に改め、同条第五号中「第二十四条の三」を「第二十三条の三」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改め、同条第六号中「第三十五条第八項又は」を削る。
第六章を第九章とする。
第六十条の二中「第十六条第二項第一号」を「第十四条第二項第一号」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改める。
第六十八条を削り、第六十七条を第六十八条とし、第六十六条を第六十七条とし、第六十五条を第六十六条とする。
第六十四条第一項中「第十七条第一項」を「第十五条第一項」に、「第二十三条」を「第二十二条」に改め、同条を第六十五条とする。
第六十三条の二中「荷主」を「荷主(次に掲げる者を含む。次条において同じ。)」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第二条第八項第一号に掲げる者が貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業者、貨物利用運送事業法第二十四条第一項に規定する第二種貨物利用運送事業者及び同法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者をいう。)である場合にあっては、当該貨物利用運送事業者に運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)
二 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者であって、他人のために当該貨物を受け取るもの
三 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者であって、他人のために当該貨物を引き渡すもの
第六十三条の二を第六十四条とする。
第五章を第八章とする。
第五十八条の四中「第五十八条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「」及び「」という。)」を削る。
第五十八条の九第一項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)」を削り、「同項」を「次項」に改め、同条第二項第四号中「(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。)」を削る。
第五十八条の十六第二項中「同項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「」及び「」という。)」を削る。
第四章を第七章とする。
第三十九条第五号中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に改める。
第三十九条の二に次の二項を加える。
5 地方実施機関は、第一項の規定による調査の結果、当該申出の対象となった荷主の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知するものとする。
一 当該申出人が第二十四条第一項に規定する健全化措置を実施する上で支障となっていること。
二 国土交通大臣が物資の流通の効率化に関する法律第四十条の規定により意見を述べるに当たって参酌すべきものであること。
6 国土交通大臣は、前項の規定による通知に係る荷主の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項に規定する不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。
第三章を第六章とする。
第三十七条の見出し中「特則」を「特例」に改め、同条第一項中「第二十五条」を「第二十六条」に、「第二十七条」を「第二十八条」に改め、「(平成元年法律第八十二号)」を削り、同条第三項中「第十五条、第十六条、第十七条第一項」を「第十三条、第十四条、第十五条第一項」に、「第十八条、第二十二条第二項」を「第十六条、第二十条第二項」に、「第二十二条の二から第二十四条の四まで」を「第二十一条から第二十三条の三まで、第二十五条」に、「第十七条第五項及び第二十二条第三項」を「第十五条第五項及び第二十条第三項」に改め、第二章中同条を第三十七条の二とする。
第三十四条の次に次の章名を付する。
第三章 特定貨物自動車運送事業
第三十五条の見出しを削り、同条第六項中「第十五条、第十六条、第十七条第一項」を「第十三条、第十四条、第十五条第一項」に、「第十八条、第二十二条第二項」を「第十六条、第二十条第二項」に、「第二十二条の二から第二十四条の四まで、第二十七条、第三十二条並びに第三十三条」を「第二十一条から第二十四条の三まで、第二十四条の四第二項及び第三項、第二十四条の五第一項から第四項まで及び第六項、第二十五条、第二十八条並びに第三十条から第三十三条まで」に、「第十七条第五項及び第二十二条第三項」を「第十五条第五項及び第二十条第三項」に改め、「運行管理者について」の下に「、第二十四条の四第一項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運送利用管理者について」を、「第九条第二項」の下に「、第三十条第三項及び第三十一条第三項」を加え、同条第七項及び第八項を削り、同条の次に次の章名を付する。
第四章 貨物軽自動車運送事業
第三十六条の見出しを「(貨物軽自動車運送事業の届出等)」に改め、同条第二項中「第十五条、第十七条第一項」を「第十二条、第十三条、第十五条第一項」に、「第二十三条、第二十四条の四、第二十五条第一項」を「第二十二条から第二十三条の二まで、第二十四条の五第四項、第二十五条、第二十六条第一項」に、「第十七条第五項」を「第十五条第五項」に、「第三十四条」を「第三十四条第一項から第三項まで」に、「第二十三条中「第十六条第一項、第四項若しくは第六項、第十七条第一項から第四項まで、第十八条第一項、第二十二条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「第三十六条第二項において準用する第十七条第一項から第四項までの規定」」を「第二十二条中「が、第十四条第一項、第四項若しくは第六項」とあるのは「が」と、「、第十六条第一項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「の規定」と、「、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他」とあるのは「その他」」に改め、「命ずることができる」と」の下に「、第三十四条第一項中「自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標」とあるのは「車両番号標」と、同条第二項中「自動車登録番号標」とあるのは「車両番号標」と、同条第三項中「自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)」とあるのは「車両番号標」と、「自動車登録番号標を」とあるのは「車両番号標を」と、「取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受け」とあるのは「表示し」と」を加え、同条第五項中「、相続人」の下に「(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該貨物軽自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)」を加え、同条の次に次の一条、章名及び一条を加える。
(貨物軽自動車安全管理者の選任等)
第三十六条の二 貨物軽自動車運送事業者(四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条において同じ。)は、前条第一項前段の規定による届出後、速やかに、営業所ごとに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、貨物軽自動車安全管理者一人を選任しなければならない。
一 第五十八条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関」という。)が実施する同条に規定する貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前二年以内に修了した者
二 前号に規定する貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、第三項に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前二年以内に修了した者
三 当該貨物軽自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する場合にあっては、第十六条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により運行管理者として選任されている者
2 貨物軽自動車運送事業者は、前項の規定により貨物軽自動車安全管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 貨物軽自動車運送事業者は、第一項の貨物軽自動車安全管理者(第十六条第一項の規定により現に運行管理者として選任されている者を除く。)に、その選任の日から二年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第五十八条の十六第一項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」という。)が実施する同項に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を受けさせなければならない。
第五章 貨物利用運送事業者に関する特例
(第一種貨物利用運送事業者に関する特例)
第三十七条 第二十四条並びに第二十四条の五第四項及び第五項の規定は、第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者である場合において、当該第一種貨物利用運送事業者が当該貨物の運送について一般貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合について準用する。この場合において、第二十四条中「一般貨物自動車運送事業者は」とあるのは「第一種貨物利用運送事業者は」と、同条第二項及び第三項中「他の一般貨物自動車運送事業者」とあるのは「一般貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者」と、同条第二項ただし書中「行う一般貨物自動車運送事業者」とあるのは「行う一般貨物自動車運送事業者又は第一種貨物利用運送事業者」と、第二十四条の五第四項中「一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)」とあるのは「第一種貨物利用運送事業者」と、「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「一般貨物自動車運送事業者又は他の第一種貨物利用運送事業者」と、同条第五項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「第一種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。
2 第二十四条の五第四項及び第五項の規定は、第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者である場合において、当該第一種貨物利用運送事業者が当該貨物の運送について特定貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)」とあるのは「第一種貨物利用運送事業者」と、「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「特定貨物自動車運送事業者」と、同条第五項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「第一種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。
附則第一条の二第一項中「を荷主」の下に「(第六十四条各号に掲げる者を含む。以下この条において同じ。)」を加え、同条第四項ただし書中「第六十四条第一項」を「第六十五条第一項」に改め、同条第七項中「(昭和二十二年法律第五十四号)」を削り、同条第八項に次のただし書を加える。
ただし、第三十九条の二第五項の規定による通知をした場合は、この限りでない。
第五条 貨物自動車運送事業法の一部を次のように改正する。
第二十四条の四中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 運送利用管理者は、その職務(前条第二項第二号に掲げるものに限る。)を行うに当たっては、その特別一般貨物自動車運送事業者の運送契約の相手方が物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十七条第一項に規定する物流統括管理者を選任している場合には、当該物流統括管理者と連携しなければならない。
第三十五条第六項中「第二十四条の四第二項及び第三項」を「第二十四条の四第三項及び第四項」に改め、「第二十四条の四第一項」の下に「及び第二項」を加える。
第三十九条第五号中「(平成十七年法律第八十五号)」を削る。
第三十九条の二第五項第二号中「第四十条」を「第五十一条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第三項第一号の改正規定及び附則第七条の規定 公布の日
二 第一条中流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二十条の二第一項第一号の改正規定並びに附則第六条の規定及び附則第十三条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十五条第一項の改正規定(「、貸付け」を「、出資の決定及び貸付け」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第三条中貨物自動車運送事業法附則第一条の二に一項を加える改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条の規定及び附則第十一条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百二十五号の改正規定(「流通業務総合効率化促進法第十条第一項」を「物資流通効率化法第十二条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に改める部分を除く。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
五 第二条及び第五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(実運送体制管理簿の作成等に関する経過措置)
第二条 第四条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法(以下この条及び附則第四条において「新貨物自動車法」という。)第二十四条の五第一項(新貨物自動車法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者がこの法律の施行の日(次条及び附則第十五条において「施行日」という。)以後に他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用した場合について適用する。
(特定貨物自動車運送事業者に係る権利義務の承継に関する経過措置)
第三条 施行日前に貨物自動車運送事業法第三十五条第一項の許可を受けた者(以下この条において「施行日前許可事業者」という。)が当該許可に係る特定貨物自動車運送事業を施行日前に譲渡した場合又は施行日前許可事業者について施行日前に合併、分割若しくは相続があった場合における施行日前許可事業者に係る同項の許可に基づく権利義務の承継については、なお従前の例による。
(貨物軽自動車安全管理者の選任等に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に貨物軽自動車運送事業を経営している者についての新貨物自動車法第三十六条の二第一項の規定の適用については、同項中「前条第一項前段の規定による届出後」とあるのは「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第▼▼▼号)の施行の日後」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、この限りでない」とする。
(登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等の罰則に関する経過措置)
第五条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第三条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第七十三条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(道路運送法等の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「第二十五条第一項」を「第二十六条第一項」に改める。
一 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十二条第二項
二 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二十三第二項
三 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十七条の十八第三項
(中小企業基本法及び国土交通省設置法の一部改正)
第十条 次に掲げる法律の規定中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に改める。
一 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二十九条第三項
二 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第十五条第一項
(登録免許税法の一部改正)
第十一条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一第百二十号中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「「流通業務総合効率化促進法」を「「物資流通効率化法」に、「第十三条第一項」を「第十五条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第十四条第一項」を「物資流通効率化法第十六条第一項」に改め、同表第百二十三号中「流通業務総合効率化促進法第十五条第一項」を「物資流通効率化法第十七条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に改め、同表第百二十五号中「道路運送事業の許可又は事業計画の変更の認可」を「道路運送事業の許可若しくは事業計画の変更の認可又は登録貨物軽自動車安全管理者講習機関若しくは登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の登録」に、「流通業務総合効率化促進法第十条第一項」を「物資流通効率化法第十二条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に改め、同号に次のように加える。
(六) 貨物自動車運送事業法第五十八条の二(登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録)の登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
(七) 貨物自動車運送事業法第五十八条の十六第一項(登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の登録)の登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
別表第一第百三十三号中「流通業務総合効率化促進法第十二条第一項」を「物資流通効率化法第十四条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に改め、同表第百三十九号中「流通業務総合効率化促進法第八条第一項」を「物資流通効率化法第十条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第五条第一項」を「物資流通効率化法第七条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第九条第一項」を「物資流通効率化法第十一条第一項」に改め、同表第百四十号中「流通業務総合効率化促進法第十六条第一項」を「物資流通効率化法第十八条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第四条第一項」を「物資流通効率化法第六条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第五条第一項」を「物資流通効率化法第七条第一項」に改める。
(貨物利用運送事業法の一部改正)
第十二条 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第三十二条、第三十三条第三号及び第四十九条中「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改める。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)
第十三条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を次のように改正する。
第十条第一項第二号中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「第二十条の二第一項第一号」を「第二十三条第一項第一号」に改める。
第十三条第一項第十号中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二十条の二第一項」を「物資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項」に改める。
第十五条第一項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二十条の二第一項第一号」を「物資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項第一号」に、「、貸付け」を「、出資の決定及び貸付け」に改める。
(海上運送法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二条の見出しを「(物資の流通の効率化に関する法律の一部改正)」に改め、同条中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)」に改め、同条のうち流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条の改正規定中「第二条」を「第四条」に改める。
(海上運送法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第十五条 前条の規定は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が施行日前である場合には、適用しない。
理 由
物資の流通の効率化を図るため、基本理念及び国の責務並びに貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し講ずべき措置等を定めるとともに、貨物自動車運送事業における下請構造に対応するため、一般貨物自動車運送事業者が他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する場合の措置等を定めるほか、貨物軽自動車運送事業の安全対策を強化するため、貨物軽自動車運送事業者に対し貨物軽自動車安全管理者の選任を義務付ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令
(貨物自動車運送事業法施行規則の一部改正)第一条 貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(書面の交付) 第十三条の三
法第十二条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 災害その他緊急やむを得ない場合
二 真荷主が郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物の運 送を委託する場合
2 法第十二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとお りとする。
一 運送契約の当事者の氏名又は名称及び住所
二 有料道路の通行に係る料金、燃料価格の変動に伴い追加的に必要 となる燃料費に係る料金その他の特別に生ずる費用に係る料金
三 運賃及び料金の支払の方法四 書面を交付した年月日(書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項(以下「記載事項」という。)を電磁的方法により提供し た場合にあっては、その提供した年月日)
3 真荷主及び一般貨物自動車運送事業者は、法第十二条第一項の規定により書面を交付した場合は、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては確認することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第一項第二号及び第十三条の七第三項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)を一年間保存しなければならない
(情報通信の技術を利用する方法)第十三条の四 法第十二条第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 送信者等(送信者又は送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。以下この条、次条及び第十三条の八において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は受信者との契約により受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該受信者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法
二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第十三条の六第一項第二号及び第十三条の九第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。二 前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三 前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
(法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十三条の五 貨物自動車運送事業法施行令(令和七年政令第〇〇〇号。以下「令」という。)第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)第十三条の六 令第一条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に令第一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて送信者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない
(書面の交付)第十三条の七 法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、災害その他緊急やむを得ない場合とする。
2 法第二十四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 その利用する運送に係る契約の当事者の氏名又は名称及び住所
二 有料道路の通行に係る料金、燃料価格の変動に伴い追加的に必要となる燃料費に係る料金その他の特別に生ずる費用に係る料金
三 運賃及び料金の支払の方法
四 書面を交付した年月日(書面の交付に代えて、記載事項を電磁的方法により提供した場合にあっては、その提供した年月日)
3 一般貨物自動車運送事業者は、法第二十四条第二項の規定により書面を交付した場合は、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)を一年間保存しなければならない。
(法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十三条の八 令第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第十三条の四第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
第十三条の九 令第二条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に令第二条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて送信者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない
(運送利用管理規程を定める一般貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模)
第十三条の十 法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、前年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間(次条において「年度」という。)であって、直前のものをいう。)に行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が百万トンであることとする
(運送利用管理規程の届出)第十三条の十一
法第二十四条の二第一項の規定により運送利用管理規程の作成の届出をしようとする者は、その行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が初めて前条に規定する合計量以上となった年度の翌年度の七月十日までに、次に掲げる事項を記載した運送利用管理規程作成届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二 運送利用管理規程を定めた日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 作成した運送利用管理規程
二 その他運送利用管理規程に関し必要な事項を記載した書類
3 法第二十四条の二第一項の規定により運送利用管理規程の変更の届出をしようとする者は、当該運送利用管理規程の変更後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した運送利用管理規程変更事後届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 運送利用管理規程を変更した日
三 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
四 変更を必要とした理由
4 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更後の運送利用管理規程
二 その他変更後の運送利用管理規程に関し必要な事項を記載した書類
(運送利用管理者の選任及び解任の届出)第十三条の十二
一般貨物自動車運送事業者は、法第二十四条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した運送利用管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 選任し、又は解任した運送利用管理者の氏名及び生年月日
三 選任し、又は解任した年月日四 解任の届出の場合にあっては、その理由
2 前項の運送利用管理者選任届出書には、選任した運送利用管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあることを証する書類を添付しなければならない
(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)第十三条の十三
法第二十四条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、一・五トンとする
(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)第十三条の十四
法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から法第二十四条の五第一項第一号の貨物自動車運送事業者のうち請負階層が最も大きいものに至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合とする。
貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案(仮称)について
令和6年12月 物流・自動車局
1.背景
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号。以下「改正法」という。)による改正後の物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号。以下「法」という。)第35条第1項において、国土交通大臣は、法第33条第1項の基本方針に基づき国土交通省令で、貨物自動車運送事業者等※が運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るために講ずべき措置に関し、貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとされている。
このため、国土交通省令において、運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るために貨物自動車運送事業者等が取り組むべき具体的内容を示す必要がある。
なお、当該内容については、令和6年6月から開催された「交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議」(以下「三省合同会議」という。)において、有識者委員による議論が行われてきたところであり、三省合同会議の取りまとめの内容に即して定めるものである。
2.概要
(1)運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加のための措置の実施の原則(第1条関係)
貨物自動車運送事業者等は、法第33条第1項の基本方針に定められた貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の目標を達成するため、その運送する貨物の特性、従業者の安全の確保の必要性その他の必要な事情に配慮した上で、運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加のための措置を計画的かつ効率的に実施するものとする。
(2)運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加(第2条関係)
貨物自動車運送事業者等は、以下に定めるところにより、法第34条に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、次に定めるところによらないことが同条に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。
① 一の貨物自動車に複数の荷主の貨物を積み合わせて運送することその他の措置により、輸送網を集約すること。
② 荷主、連鎖化事業者、他の貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者と協議を行うことその他の措置により、複数の貨物自動車運送事業者等が委託を受けた集荷又は配達を一の運転者に行わせること。
③ 帰路において車両に貨物を積載することその他の措置により、貨物自動車の走行距離に占める貨物を車両に積載した状態における走行距離の割合を増加させること。
④ 配車、運行等に関する情報システムの導入その他の措置により、配車計画又は運行経路の最適化を行うこと。
※ 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者及び特定第二種貨物利用運送事業者をいう(法第30 条第6号)。
⑤ 輸送する貨物の量に応じた大型車両の導入その他の措置により、運転者一人当たりの一回の運送ごとに輸送することができる貨物の重量を増加させること。
(3)実効性の確保(第3条関係)
貨物自動車運送事業者等は、(2)の措置の実効性を確保するため、以下に掲げる措置を講ずるものとする。
① 運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況並びに貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化(以下単に「効率化」という。)のために実施した取組及びその効果を適切に把握すること。
② 必要に応じて取引先その他の関係事業者に対し、複数の荷主の貨物を積み合わせて運送することその他の措置を実施するために必要な運賃の設定、パレットその他の輸送用器具の利用その他の効率化に資する措置の提案を行うこと。
③ 物資の流通に係るデータの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。)を実施することその他の措置により、多様な主体との連携を通じた効率化のための取組の実施の円滑化を図ること。
④ 効率化のための取組を効果的に行うため、国、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図ること。その際、必要に応じて取引先に対し協力を求めること。
⑤ テールゲートリフター(貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。)の導入、貨物の積卸しのための施設の整備その他の措置を講ずることにより、(2)の措置を講ずることに伴い増加する運転者の負荷の低減に配慮すること。
⑥ 関係法令を遵守し、過積載による運送その他の輸送の安全を阻害する行為を防止すること。
※ なお、三省合同会議の取りまとめにおいて記載があるものの、本省令案で規定することとしていない内容については、今後策定予定の解説書等において記載する予定。
3.今後のスケジュール(予定)
公 布:令和7年2月
施 行:改正法の施行の日(令和7年4月予定)
貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案(仮称)について
令和6年12月物流・自動車局
1.背景
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号。以下「改正法」という。)による改正後の物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号。以下「法」という。)第42条第1項※において、国土交通大臣は、法第33条第1項の基本方針に基づき国土交通省令で、貨物自動車関連事業者(倉庫業者、港湾運送事業者、航空運送事業者及び鉄道事業者をいう。以下同じ。)が運転者の荷待ち時間等の短縮を図るために講ずべき措置に関し、貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとされている。
このため、国土交通省令において、運転者の荷待ち時間等の短縮を図るために貨物自動車関連事業者が取り組むべき具体的内容を示す必要がある。
なお、当該内容については、令和6年6月から開催された「交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議」(以下「三省合同会議」という。)において、有識者委員による議論が行われてきたところであり、三省合同会議の取りまとめの内容に即して定めるものである。
2.概要
(1)運転者の荷待ち時間等の短縮のための措置の実施の原則(第1条関係)
(ⅰ)倉庫業者は、法第33条第1項の基本方針に定められた貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の目標((ⅱ)において単に「目標」という。)を達成するため、その取り扱う貨物の特性、従業者の安全の確保の必要性その他の必要な事情に配慮した上で、運転者の荷待ち時間等の短縮を図るための措置を計画的かつ効率的に実施するものとする。
(ⅱ)貨物自動車関連輸送事業者(倉庫業者以外の貨物自動車関連事業をいう。以下同じ。)は、目標を達成するため、その取り扱う貨物の特性、従業者の安全の確保の必要性その他の必要な事情に配慮した上で、運転者の荷役等時間の短縮を図るための措置を計画的かつ効率的に実施するものとする。
(2)運転者の荷待ち時間の短縮(第2条関係)
(ⅰ)倉庫業者は、以下に定めるところにより、法第41条第1項第1号に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、以下に定めるところによらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。
① 第一種荷主から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を運転者に伝達するに当たっては、当該第一種荷主が決定した貨物の受渡しを行うべき時間帯における自ら管理する施設の状況を考慮して、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないよう配慮すること。
※ 改正法のうち、公布の日から1年以内に施行する部分が施行した後の条番号。以下法の条番号について同じ。
2
② 到着時刻表示装置(当該倉庫業者が管理する施設における貨物の搬入及び搬出の状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業者等から提供された当該施設に到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムを使用して当該予定時刻に係る情報を表示する装置をいう。(ⅱ)②において同じ。)の導入を行い、及びこれを適切に活用することその他の措置により、貨物自動車の到着時刻を調整すること。
(ⅱ)倉庫業者は、以下に定めるところにより、法第41条第1項第2号に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、以下に定めるところによらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。
① 第二種荷主から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻を運転者に伝達するに当たっては、当該第二種荷主が指示した貨物の受渡しを行うべき時間帯における当該施設の状況を考慮して、停留場所の数その他の条件により定める荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないよう配慮すること。
② 到着時刻表示装置の導入を行い、及びこれを適切に活用することその他の措置により、貨物自動車の到着時刻を調整すること。
(3)運転者の荷役等時間の短縮(第3条関係)
貨物自動車関連事業者は、以下に定めるところにより、法第41条第1項第3号に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、以下に定めるところによらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。
① 荷役等に係る停留場所を拡張すること又は貨物の量に応じて適正に確保することにより、荷役等の円滑な実施ができる環境を整えること。
② 荷役等に先行する貨物の搬出又は荷役等に後続する貨物の搬入に関するマニュアルの作成又は周知その他の措置により、当該搬出又は搬入を迅速に実施すること。
③ フォークリフト又は荷役等を行う人員を適切に配置すること、発送先の荷主ごとに貨物を仕分けた状態で引き渡すこと、荷主から一貫パレチゼーション(輸送、荷役又は保管の各段階において同一のパレットを使用することをいう。)の実現のためにパレットを使用したい旨の申し出があった場合には、パレットの使用に協力することその他の措置により、荷役等の効率化を図ること。
④ 貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査(以下④において単に「検査」という。)を効率的に実施するための機器を導入することその他の措置により、検査の効率化を図ること。
(4)実効性の確保(第4条関係)
貨物自動車関連事業者は、(2)及び(3)の措置の実効性を確保するため、以下に掲げる措置を講ずるものとする。
① 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化(以下単に「効率化」という。)を図るため、効率化のための取組に関する責任者の選任その他の必要な体制の整備を行うとともに、その従業員に対し、効率化のための取組に関する研修の実施その他の措置を講ずること。
② 運転者の荷待ち時間等(貨物自動車関連輸送事業者にあっては、運転者の荷役等時間)及び効率化のために実施した取組及びその効果を適切に把握すること。
③ 取引先その他の関係事業者に対し、(2)及び(3)の措置の実施その他の効率化のための措置に関し提案を行うことができる場合にあっては、当該提案を行うこと。
④ 物資の流通に係るデータの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。)を実施することその他の措置により、多様な主体との連携を通じた効率化のための取組の実施の円滑化を図ること。
⑤ 無人搬送車(自動的に走行し、貨物を搬送する機能を有する車両をいう。)を導入することその他の措置により、貨物自動車関連事業者の管理する施設における作業の自動化を図ること。
⑥ 効率化のための取組を効果的に行うため、国、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図ること。その際、必要に応じて取引先に対し協力を求めること。
※ なお、三省合同会議の取りまとめにおいて記載があるものの、本省令案で規定することとしていない内容については、今後策定予定の解説書等において記載する予定。
3.今後のスケジュール(予定)
公 布:令和7年2月
施 行:改正法の施行の日(令和7年4月予定)
国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部を改正する省令案について
令和6年12月 物流・自動車局
1.背景
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号。以下「改正法」という。)により、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号。以下「法」という。)に物流効率化のための規制的措置を新設するほか、題名改正等の所要の改正を行うこととしている。
規制的措置の新設に伴い、改正法による改正後の法第30条第4号及び第5号において「荷待ち時間」及び「荷役等時間」の算定方法等を国土交通省令で定めることとされていることから、国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則(平成17年国土交通省令第100号。以下「規則」という。)において規定するとともに、規則を含む国土交通省所管の省令中、法の題名の改正等所要の改正を行う必要がある。
なお、「荷待ち時間」及び「荷役等時間」の算定方法等については、令和6年6月から開催された「交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議」(以下「三省合同会議」という。)において、有識者委員による議論が行われてきたところであり、三省合同会議の取りまとめの内容に即して定めるものである。
2.概要
(1)題名改正等
改正法により、法の題名が「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」から「物資の流通の効率化に関する法律」に改正されることに伴い、規則の題名についても「国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則」から「国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則」に改正することとするほか、改正法による法の条項ずれに伴う所要の改正を行う。
(2)「荷待ち時間」の算定方法等(規則第5条(新設)関係)
改正法による改正後の法第30条第4号に規定する「荷待ち時間」については、「…荷主、当該場所の管理者その他国土交通省令で定める者の都合により貨物の受渡しのために待機した時間…」と規定されているが、当該国土交通省令で定める者は、「連鎖化事業者」とする。
また、「荷待ち時間」は、以下のとおり算定される時間とする。
①
運転者が集貨若しくは配達を行うべき場所又はその周辺の場所(以下「集貨場所等」という。)に到着した時刻(到着後速やかに受付その他これに類する行為を行った場合にあっては、その時刻)から荷役等を開始した時刻までの時間(荷主、集貨場所等の管理者又は連鎖化事業者の都合以外の事情により待機した時間を除く。)とする。
②
ただし、決定された貨物の受渡しを行う時刻若しくは時間帯又は運転者が指示若しくは伝達された貨物の受渡しを行う時刻若しくは時間帯の開始時刻よりも前に集貨場所等に到着した場合にあっては、これらの時刻又は時間帯の開始時刻から荷役等を開始した時刻までの時間(荷主、集貨場所等の管理者又は連鎖化事業者の都合以外の事情により待機した時間を除く。)とする。
2
(3)「荷役等時間」の算定方法等(規則第6条(新設)関係)
改正法による改正後の法第30条第5号に規定する「荷役等」に含まれる荷役以外の業務については、「貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの検査、貨物の荷造り、入庫、出庫、保管、仕分又は陳列、ラベルの貼付け、代金の取立て又は立替え、立会いその他の通常貨物自動車の運転の業務に附帯する業務」とし、同号の「荷役等時間」の算定方法については、「運転者が荷役等を開始した時刻から終了した時刻までの時間(荷役等に従事していない時間を除く。)」とする。
(4)その他
規則及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令(平成15年国土交通省令第102号)において引用されている法の題名の改正、改正法による法の条項ずれに伴う所要の改正を行う。
3.今後のスケジュール(予定)
公 布:令和7年2月
施 行:改正法の施行の日(令和7年4月予定)
貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針案(仮称)について
1.背景
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号。以下「改正法」という。)による改正後の物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号)第33条第1項に基づき、主務大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針を定めるものとされている。
当該基本的な方針の内容については、令和6年6月から開催された「交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議」(以下「三省合同会議」という。)において、有識者委員による議論が行われてきたところであり、三省合同会議の取りまとめの内容に即して定めるものである。
2.概要
別紙のとおり。
3.今後のスケジュール(予定)
公 布:令和7年2月
施 行:改正法の施行の日(令和7年4月予定)
貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針案(仮称)
第一 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の意義及び目標に関する事項
1 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の意義
物流は、我が国の国民生活や経済活動、地方創生を支える不可欠な社会基盤であり、我が国経済の力強い成長や、より豊かな国民生活の実現等のため、その機能を十分に発揮させていく必要がある。
しかしながら、物流業界は、運転者の長時間の荷待ちや契約にない附帯作業等による長時間労働に加え、価格競争に伴う厳しい取引環境及び雇用環境に置かれているといった課題が深刻化しており、これらが運転者をはじめとする物流業界における人手不足の原因となっている。
また、商取引及び物流取引における商慣習、多層的な取引構造等が要因となって、物流サービスに伴い生じる物流負荷が可視化及び価格化されてこなかったこと等を背景に、荷主企業や消費者において物流業界における課題が認識されにくい状況が固定化している。
このような中、物流産業を魅力ある職場とするため、令和六年度から、自動車運転者の時間外労働の上限規制等が適用されることとなり、人手不足の中、何も対策を講じなければ深刻な輸送力不足に陥るおそれがあるという問題に直面している。
加えて、物流の過程において二酸化炭素の排出等による環境への負荷が生じていることに鑑み、物流業界は脱炭素化に向けた取組への対応も求められている。
物流業界が直面しているこれらの諸課題は、喫緊の課題であると同時に、年々深刻化していく構造的な課題であって、これに対応するため、物流は大きな変革が求められている。
すなわち、物流はその担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送される必要があり、貨物自動車運送事業や倉庫業等の物流を担う事業者に加え、荷主及び消費者を含む物流に関わる者が、それぞれの立場で担うべき役割を再考し、物流の効率化のための取組を行うことが必要不可欠である。
また、その取組を行うに当たっては、物流が物資の生産や製造の過程、消費と密接に関連しており、かつ、物流には、物流事業者(貨物自動車運送事業者、倉庫業者、鉄道事業者、内航及び外航海運事業者、港湾運送事業者、航空運送事業者、貨物利用運送事業者等の物流業務を行う事業者をいう。以下同じ。)、荷主、施設管理者、消費者等の多様な主体が関わっていることを踏まえ、これらのサプライチェーン全体の関係者が連携を図り、その取組の効果を一層高める必要がある。
さらに、物流の効率化のための取組として、貨物自動車による輸送の効率化や共同輸配送、モーダルシフトの推進等を行うことを通じて物流の過程において生じている環境への負荷の低減を図ることにより、脱炭素社会の実現に寄与することが必要である。
我が国の物流において貨物自動車運送役務がその中核的な役割を担っていることを鑑みれば、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に向けて運転者の運送及び荷役等の効率化を推進することは、大きな意義を持つものである。
2 運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の目標
貨物自動車運送役務の持続可能な提供を確保するためには、運転者の業務のうち、運送を効率化することに加えて、運送以外の不必要な荷待ち時間等を短縮することについて、荷主、貨物自動車関連事業者及び連鎖化事業者がそれぞれの立場から取組を行うことが必要である。
また、貨物自動車運送役務の実運送を担う貨物自動車運送事業者等において、輸送網の集約、配送の共同化等により、運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加(以下「積載効率の向上等」という。)を図ることも重要である。荷主及び連鎖化事業者は、貨物自動車運送事業者等がこれらの措置に取り組めるよう、適切なリードタイムの確保等の措置を行うことにより、積載効率の向上等を図る必要がある。
さらに、国及び地方公共団体、港湾管理者、空港管理者、卸売市場開設者、ショッピングセンター等の物流に関する施設を管理する者並びに運送契約や貨物の受渡しに直接関わりを持たないものの商取引に影響を持つ者においても、自らの事業等の実施に伴う運転者への負荷の低減に資する取組を行うことが求められる。
したがって、物資の流通の効率化に関する法律(以下「法」という。)では、荷主、貨物自動車運送事業者等、貨物自動車関連事業者及び連鎖化事業者に対し、運転者の荷待ち時間等の短縮及び積載効率の向上等を図るための措置を講ずる努力義務を課すとともに、これらの事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、当該措置に関する中長期的な計画の作成等を義務付けることとしている。また、物資の流通に関する事業を行う者、その事業を利用する事業者及び物資の流通に関する施設を管理する者(以下「施設管理者等」という。)については、その事業の実施や施設の管理に伴う運転者への負荷の低減その他の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する措置を講ずる責務を明確化している。
貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に当たっては、安全性の確保を前提とし、国、地方公共団体、荷主、貨物自動車運送事業者等、貨物自動車関連事業者、連鎖化事業者、施設管理者等の物流に関わる様々な関係者が協力して、法に基づく枠組みの活用等により、次に掲げる事項を達成することを目標とする。
① 運転者の荷待ち時間等の短縮
令和十年度までに、全国の貨物自動車による輸送のうち五割の運行で荷待ち時間等を一時間短縮することで、運転者一人当たりの荷待ち時間等を年間百二十五時間短縮することを実現するものとする。
このためには、現状、運転者の一運行の平均拘束時間のうち、荷待ち及び荷役等にかかる時間が合計約三時間と推計されていることを踏まえ、この一運行当たりの荷待ち時間等が合計二時間以内となるよう荷待ち時間等を削減する必要がある。また、これを踏まえ、荷主等は、一回の受渡しごとの荷待ち時間等について、原則として目標時間を一時間以内と設定しつつ、業界の特性その他の事情によりやむを得ない場合を除き、二時間を超えないよう荷待ち時間等を短縮するものとする。なお、一回の受渡しごとの荷待ち時間等が一時間以内である荷主等にあっては、その継続及び改善に努めるものとする。
② 運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加
令和十年度までに、近年四十パーセント以下の水準で推移してきた積載効率について、全国の貨物自動車による輸送のうち五割の車両で五十パーセントを目指し、全体の車両で四十四パーセントへの増加を実現するものとする。また、トラック輸送一運行当たりの輸送効率の向上に当たっては、重量ベースだけでなく、容積ベースでも改善を図るものとする。
③ 関連する施策への貢献
①及び②の目標の達成に向けた取組を通じて、効率的な共同輸配送、共同拠点利用等を図るフィジカルインターネット(規格化された容器に詰められた貨物を、複数企業の倉庫、貨物自動車等をネットワークとして活用し輸送する共同輸配送システムをいう。以下同じ。)の実現を図るとともに、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第八条第一項に基づく地球温暖化対策計画に対策及び施策として位置付けられている脱炭素物流の推進に貢献するものとする。
第二 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する施策に関する基本的な事項
国及び地方公共団体は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化並びに輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に関し、次に掲げるところにより、自ら措置を実施するとともに、情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の援助並びに研究開発の推進に努めるものとする。これに加え、広報活動その他の活動を通じて、集貨又は配達に係る運転者への負担の低減に資する施策に関して国民の理解を深めるとともに、その施策の実施に関する国民の協力を求めるよう努めるものとする。
1 荷主として国及び地方公共団体自らが講ずべき事項
国及び地方公共団体は、自らが荷主となる場合は、率先して運転者の運送及び荷役等の効率化に資する措置を講ずるよう努めるものとする。
2 施設管理者として国及び地方公共団体自らが講ずべき事項
国及び地方公共団体は、自らが港湾管理者、空港管理者、卸売市場開設者である場合、荷主に対して行政財産の使用許可等を根拠に施設の一部を使用させている場合等、施設管理者となる場合は、その施設の管理に関し、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する措置を講ずるよう努めるものとする。
3 設備投資等に対する支援
国は、運転者の運送及び荷役等の効率化に資する設備投資、デジタル化、物流標準化等に取り組む事業者を支援するため、調査、助言その他の必要な援助を講ずるとともに、これらの援助に関する十分な情報の提供を行うよう努めるものとする。
4 モーダルシフト等に対する支援
国は、輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に資するモーダルシフト等に取り組む事業者を支援するため、鉄道、海運等の輸送経路の拡充や輸送品質の向上等に向けた調査、助言その他の必要な援助を講ずるとともに、これらの援助に関する十分な情報の提供を行うよう努めるものとする。
5 技術開発等に対する支援
国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資するよう、貨物自動車以外の大量輸送機関による貨物輸送の促進に向けた技術開発、自動運転貨物自動車や無人航空機(ドローン等)による輸送の実用化を推進し、これらの成果の普及等に努めるものとする。
6 物流標準化に対する支援
国は、フィジカルインターネットの実現に向けて、物流現場における自動化又は機械化、デジタル化、省人化等の前提となる物流標準化を推進するため、官民連携により、納品伝票、外装表示、パレット又は外装の規格、商品、事業所等のコード体系、物流用語等の標準化に向けて取り組み、これらの成果の普及等に努めるものとする。
7 高度物流人材の確保・育成
国は、物流統括管理者として物流改善の取組を推進できる人材の確保及び育成を支援するため、物流統括管理者の役割の普及、啓発その他の必要な措置を講ずるとともに、これらの人材を支える高度物流人材の確保及び育成に取り組むよう努めるものとする。
8 貨物自動車運送役務の職場環境等の整備
国は、貨物自動車運送役務の持続的発展に向けて担い手を確保していくため、多様な人材にとって快適で働きやすい職場環境を整備するとともに、その意義、魅力等について積極的な発信を行うよう努めるものとする。
9 国民に対する広報等
国は、物流が果たしている役割の重要性を物流事業者のみならず社会全体の共通認識として位置付けるため、「ホワイト物流」推進運動等の広報活動を通じて、荷主と物流事業者とが物流サービスに要する費用を考慮した価格や標準的な配送条件を協議しやすい環境を整備するとともに、物流の危機的状況や物流に携わる労働者の社会的価値等について、国民の理解を深めるよう努めるものとする。
10 関連する施策との連携
国は、地球温暖化対策をはじめとする環境政策、国土政策、社会資本整備に関する政策等と十分に連携しつつ、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化のために必要な措置を効果的に講ずることができるよう努めるものとする。
第三 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し、貨物自動車運送事業者等、荷主及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項
貨物自動車運送事業者等、荷主、貨物自動車関連事業者及び連鎖化事業者は、第一の2に定められた目標を達成するため、その輸送する貨物、取り扱う貨物又は事業の特性、従業者の安全の確保の必要性その他の必要な事情に配慮した上で、1から4までに掲げる措置を基本とし、それぞれの実情に合わせて、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する取組を計画的かつ効率的に実施することが必要である。
1 貨物自動車運送事業者等が講ずべき措置
⑴ 輸送網の集約、配送の共同化、復荷(帰路において貨物自動車に積載する貨物をいう。以下同じ。)の確保等により、積載効率の向上等を図ること。
⑵ 関係事業者が行う運転者の運送及び荷役等の効率化のための取組に協力すること。
⑶ 積載効率の向上等に伴う運転者の負荷の低減に取り組むこと。
⑷ ⑴から⑶までの措置の実効性を確保するため、取組状況及びその効果の把握、関係事業者との連携及び協力等を行うこと。
2 荷主が講ずべき措置
⑴ 複数荷主の貨物の積合せ、配送の共同化、復荷の確保に向けた適切なリードタイムの確保、運行効率向上のための発送量及び納入量の適正化等により、積載効率の向上等を図ること。
⑵ 適切な貨物の出荷又は入荷日時の設定、トラック予約受付システムの導入等により、運転者の荷待ち時間を短縮すること。
⑶ パレット等の導入、検品の効率化、バース等の荷捌き場所の確保等により、運転者の荷役等時間を短縮すること。
⑷ ⑴から⑶までの措置の実効性を確保するため、責任者の選任等の実施体制整備、取組状況及びその効果の把握、標準的な運賃(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)附則第一条の三第一項の規定に基づき、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃として令和六年国土交通省告示第二百九号において定められたものをいう。以下同じ。)の活用、関係事業者との連携及び協力等を行うこと。
3 貨物自動車関連事業者が講ずべき措置(貨物自動車関連輸送事業者にあっては、荷役等時間の短縮に係る措置に限る。)
⑴ 適切な貨物の入荷又は出荷時間の調整、トラック予約受付システムの導入等により、運転者の荷待ち時間を短縮すること。
⑵ 検品の効率化、バース等の荷捌き場所の確保等により、運転者の荷役等時間を短縮すること。
⑶ ⑴及び⑵の措置の実効性を確保するため、責任者の選任等の実施体制整備、取組状況及びその効果の把握、関係事業者との連携及び協力等を行うこと。
4 連鎖化事業者が講ずべき措置
⑴ 適切なリードタイムの確保等により、積載効率の向上等を図ること。
⑵ 適切な貨物の入荷又は出荷日時の設定等により、運転者の荷待ち時間を短縮すること。
⑶ ⑴及び⑵の措置の実効性を確保するため、責任者の選任等の実施体制整備、取組状況及びその効果の把握、関係事業者との連携及び協力等を行うこと。
第四 集貨又は配達に係る運転者への負荷の低減に資する事業者の活動に関する国民の理解の増進に関する基本的な事項
1 再配達の削減や多様な受取方法の普及促進等について
集貨又は配達に係る運転者への負荷の低減のためには、急いで受け取る必要のない荷物についてゆとりをもった配送日時を指定したり、再配達を避けて多様な受取方法を活用したりする等、配送サービスを日常的に利用する消費者である国民一人一人の理解と実践が不可欠である。また、事業者から消費者への物流だけでなく、事業者から事業者への物流においても、再配達の削減に向けた関係事業者の理解と実践が必要である。
国は、「再配達削減PR月間」をはじめとする広報活動等を通じて、配送時間帯指定等に関する国民の理解を深めるとともに、コンビニやガソリンスタンドでの受取り、マンション、民間不動産、駅、公共施設等における宅配ボックスの設置、置き配等の取組を推進し、多様な受取方法の普及を図る必要がある。
また、国及び地方公共団体は、それぞれの立場から、再配達の削減や、路上を含む貨物集配中の車両が駐車できるスペースの確保等に取り組み、集貨又は配達に係る運転者への負荷の低減を図る必要がある。
さらに、eコマースモールの運営事業者及び通販事業者は、物流事業者、宅配事業者等と連携しながら、物流負荷の低い多様な受取方法の選択、配送日時指定の活用等を利用者に促す仕組みの社会実装に取り組み、再配達削減に向けた消費者の行動変容を促す必要がある。
2 返品の削減や欠品に対するペナルティの見直しについて
集貨・配達に係る運転者への負荷の低減のためには、納品期限の緩和や賞味期限の大括り化、外装等の汚破損基準の見直し等による返品の削減や、欠品に対するペナルティの見直しに向けた関係事業者の理解と実践が必要であり、そのためにも、最終購買者である消費者の理解の増進が必要である。
3 「送料無料」表示の見直しについて
消費者の物流サービスに対するコスト意識の浸透と、集貨又は配達に携わる運転者に対する社会的な理解の醸成のため、商取引において物流サービスが無償で提供されているとの誤解を招かないよう「送料無料」等の表現は見直しが求められている。
このため、「送料として商品価格以外の追加負担を求めない」旨の表示をする事業者は、その表示について説明責任を果たす必要がある。
また、国は、消費者や事業者の理解を醸成するための取組を積極的に進める必要がある。
第五 その他貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関し必要な事項
1 物流に関わる多様な主体の役割について
物流は、それに先行又は後続して行われる物資の生産や製造の過程、消費と密接に関連し、かつ、物流事業者、荷主、施設管理者、消費者等の多様な主体により担われており、これらの多様な主体がそれぞれ次に掲げる役割を果たすことで、運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の効果を一層高めることが重要である。
⑴ 国は、地方支分部局と連携しながら、荷主、貨物自動車運送事業者等、貨物自動車関連事業者及び連鎖化事業者に対する規制的措置の執行に万全を期す必要がある。また、規制的措置の執行に当たっては、業界の特性、災害の発生その他の事情に配慮するとともに、業界団体等が策定した自主行動計画に即した取組について考慮する必要がある。
⑵ 地方公共団体は、積載効率の向上等に資する共同輸配送等の取組の実施やそのための拠点づくりに向けて地域の関係者の合意形成に積極的に関与し、又は参加するほか、地域の産業振興、まちづくり等と連携しながら、荷捌き施設及び休憩場所の確保等の取組を推進することに努める必要がある。
⑶ 元請貨物自動車運送事業者等及び貨物利用運送事業者は、運転者の運送及び荷役等の効率化のための取組について第一種荷主から協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努める必要がある。また、第二種荷主、連鎖化事業者、運送依頼先の貨物自動車運送事業者、実運送事業者等から協力を求められたときも、その求めに応ずることが望ましい。
⑷ 荷主は、運転者の拘束時間を削減するため、有料道路利用料の適切な負担のもと、貨物自動車運送事業者に高速道路の利用を促す必要がある。
⑸ 港湾、空港、卸売市場、ショッピングセンター、中古車オークション会場等の施設管理者、タワーマンション、オフィスビル、商業施設等を開発又は運営する事業者、商社、eコマースモールの運営事業者、物流マッチングサービス提供事業者等の、運送契約及び貨物の受渡しに直接関わりを持たないものの商取引に影響がある者も含め、経済界全体で、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保の重要性に関する理解を深めるとともに、その実現に資する措置を講ずるよう努める必要がある。
⑹ レンタルパレット事業者は、荷役の効率化に資する「標準仕様パレット」の利用(官民物流標準化懇談会パレット標準化推進分科会最終とりまとめ(令和六年六月)で定められた規格と運用に基づき、標準規格のパレット(11型等)を、標準化された方法で運用することをいう。)の拡大に向けた発信の継続や取組の充実、共同での利用及び回収の促進を図るとともに、契約への必要事項の明記に係る働きかけを含め、パレットの紛失防止対策を適切に実施する必要がある。また、レンタルパレットを利用する事業者は、当該パレットをレンタルパレット事業者との契約に定める範囲で適切に使用する必要がある。
⑺ パレット製造事業者は、標準規格のパレットの製造、販売及びレンタルパレット市場への投入を拡大するとともに、安定的に供給可能な生産体制整備等を実施する必要がある。
⑻ 消費者である国民一人一人は、物流事業者の負担となる短いリードタイムの是正のために製造業者、卸売業者、小売店等の製造から販売までの関係事業者が行った取組の結果として、商品売場での品揃えや納品時期に影響が及ぶ場合があることについて理解を深める必要がある。
2 運転者の運送及び荷役等の効率化の前提となる事項
運転者の運送及び荷役等の効率化を行うに当たっては、国、地方公共団体及び民間事業者は、次に掲げる事項を実施し、運転者の運送及び荷役等の効率化の前提となる環境を整えることで、運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の効果を一層高めることが重要である。
⑴ 運転者の労働環境の改善に向けて、国、地方公共団体及び関係事業者は、それぞれの立場から、サービスエリア、パーキングエリア、道の駅等において休憩環境の整備を進めるとともに、運転者の日帰り運行を可能とするための中継輸送拠点や、ダブル連結貨物自動車、自動運転貨物自動車等の運行のための拠点の整備を推進する必要がある。
⑵ 運転者の適正な労働時間と適正な賃金の両立に向けて、国は、契約内容の明確化や標準的な運賃の更なる浸透及び適切な見直し、国や地方公共団体等が荷主となる場合の活用の徹底等を図り、官民一体となって賃上げ原資となる適正運賃を収受できる環境整備を進める必要があるとともに、貨物自動車運送事業者は、運転者の賃上げを促進する必要がある。
⑶ 運転者の運送及び荷役等の効率化に当たっては、貨物自動車運送事業者等の法令遵守が前提となる。国は、貨物自動車運送事業者等の法令違反の原因となるおそれのある行為をしている悪質な荷主、元請貨物自動車運送事業者、貨物利用運送事業者等に対して、トラック・物流Gメンによる是正指導等を徹底するとともに、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)又は下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)に違反するおそれがある場合も含め、悪質な荷主、貨物自動車運送事業者、貨物利用運送事業者等に対する処分の厳格化を図る必要がある。また、荷主による法令遵守も不可欠である。国は、運送事業の許可を得ずに違法に運送を行う事業者の排除、運送責任の不明確化につながる行き過ぎた多重下請構造の是正やそのための実運送体制管理簿の積極的な活用、運転者に対するハラスメントの防止等を図ることが必要である。
合同会議取りまとめ
2024年11月27日
交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・
産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・
食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議 1
目次
Ⅰ はじめに ……………………………………………………………………………………………………………………………………….2
Ⅱ 公布の日から1年以内に施行される規定関係……………………………………………………………………………………3
1.基本方針について ………………………………………………………………………………………………………………………3
2.荷主・物流事業者等の判断基準等について …………………………………………………………………………………10
3.荷主等の取組状況に関する調査・公表について …………………………………………………………………………..16
4.「荷待ち時間」と「荷役等時間」の算定方法について …………………………………………………………………..17
5.物流に関係する事業者等の責務について …………………………………………………………………………………….19
Ⅲ 公布の日から2年以内に施行される規定関係………………………………………………………………………………….20
1.特定事業者の指定基準等について ………………………………………………………………………………………………20
2.中長期計画・定期報告の記載事項について …………………………………………………………………………………23
3.物流統括管理者(CLO)の業務内容について ……………………………………………………………………………..27
4.荷主・物流事業者等の物流改善の評価・公表について …………………………………………………………………29
5.その他 …………………………………………………………………………………………………………………………………….30
(別紙1)交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会合同会議 委員名簿 ……………………31
(別紙2) 合同会議における検討経過 ………………………………………………………………………………………………332
Ⅰ はじめに
物流は、国民生活や経済活動、地方創生を支える不可欠な社会インフラである。物流産業を魅力ある職場とするため、2024年4月から、トラックドライバーに時間外労働の上限規制が適用される一方、人手不足の中で、何も対策を講じなければ物流の停滞を生じかねないという、いわゆる物流の「2024年問題」に直面している。この物流の「2024年問題」は、喫緊の課題であると同時に、年々深刻化していく構造的な課題でもあるため、継続的に対応していく必要がある。
こうした背景のもと、物流の大きな変革を迫られている今こそ、運送事業や倉庫事業等を担う物流事業者のみならず、着荷主を含む荷主企業や消費者も一緒になって、それぞれの立場で担うべき役割を再考し、物流が直面している諸課題の解決に向けた取組を進め、持続可能な物流の実現につなげることが必要不可欠である。このような観点から、「持続可能な物流の実現に向けた検討会」が設置され、本検討会における議論を経て、2023年8月31日に最終とりまとめが行われた。また、政府においては、荷主企業、物流事業者(運送・倉庫等)、一般消費者が協力して我が国の物流を支える環境の整備について、関係行政機関が連携し、政府一体となって総合的な検討を行うべく、「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」が同年3月31日に設置・開催された。同年6月2日には、①物流の効率化、②商慣行の見直し、③荷主・消費者の行動変容を柱とする抜本的・総合的な対応として「物流革新に向けた政策パッケージ」が取りまとめられた。当該政策パッケージでは、「荷主企業・物流事業者間における物流負荷の軽減、物流産業における多重下請構造の是正、荷主企業の経営者層の意識改革・行動変容等に向けた規制的措置について、2024年通常国会への法案提出を視野に具体化する」こととされた。これを受け、政府において法制化の検討が行われた後、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号。以下「物流改正法」という。)が第213回国会に提出され、国会での審議を経て同年4月に成立し、同年5月15日に公布されたところである。
物流改正法による改正後の物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号。以下「新物効法」という。)の施行に向けては、今後、新物効法に基づく政令、省令、告示等において基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等が定められることとなる。同法に基づく荷主・物流事業者等に対する規制的措置を実効性のあるものとし、物流事業者、荷主企業・消費者、経済社会が「三方良し」となる社会を実現するためには、これらの具体的な内容に現場の実態や物流に関する専門的知見を反映していく必要がある。
このため、国土交通省における交通政策審議会交通体系分科会物流部会、経済産業省における産業構造審議会商務流通情報分科会流通小委員会、農林水産省における食料・農業・農村政策審議会食料産業部会物流小委員会の合同会議を立ち上げ、各種業界団体からのヒアリングやパブリックコメントを行いつつ、基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等の内容について審議し、本合同会議の取りまとめを行った。政府においては、物流の「2024年問題」の解決に向けて、各種関係法令の遵守に万全を期した上で、人手不足に対応した更なる物流効率化を推進するため、本取りまとめを踏まえた政省令の策定等の制度の施行に向けた準備を着実に進めることが望まれる。その上で、新物効法に基づく取組が実効性のあるものとなるよう、その効果的な運用と見直しに不断に取り組んでいくことを期待したい。 ※3
Ⅱ 公布の日から1年以内に施行される規定関係
1.基本方針について
〇 新物効法第33条第2項1では、トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に向けて、トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進に関する基本方針を国が定めることとされており、基本方針においては以下の事項を定めることとされている。
1 物流改正法による最終改正後の条番号。条番号について以下同じ。
2 「官民物流標準化懇談会 モーダルシフト推進・標準化分科会 新たなモーダルシフトに向けた対応方策(令和6年11月)」に基づく、陸・海・空のあらゆる輸送モードを総動員したトラックドライバー不足や物流網の障害などに対応するための新たなモーダルシフト(新モーダルシフト)をいう。
① 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の意義及び目標に関する事項
② 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する施策に関する基本的な事項
③ 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し、貨物自動車運送事業者等、荷主及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項
④ 集貨又は配達に係る運転者への負荷の低減に資する事業者の活動に関する国民の理解の増進に関する基本的な事項
⑤ その他貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関し必要な事項
〇 これらの具体的な内容として、それぞれ以下の事項を定める必要がある。
(1)貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の意義及び目標に関する事項(第33条第2項第1号)
トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資するトラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進の意義については、以下の事項を盛り込むこととする。
・ 物流は、国民生活や経済活動、地方創生を支える不可欠な社会インフラであり、その担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送される必要があること。
・ 物流は、物資の生産や製造の過程、消費と密接に関連し、かつ、荷主(発荷主・着荷主)、物流事業者(トラック、倉庫、鉄道、内航・外航海運、港湾運送、航空運送、貨物利用運送)、施設管理者、消費者などの多様な主体により担われていることに鑑み、物資の生産や製造を行う者、物資の流通の担い手その他のサプライチェーン全体の関係者が連携を図り、その取組の効果を一層高める必要があること。
・ 物流の過程において二酸化炭素の排出等による環境への負荷が生じていることに鑑み、その負荷の低減を図るため、トラック輸送の効率化や共同輸配送、モーダルシフト※2の推進等を通じて、脱炭素社会の実現に寄与することが求められていること。
・ これらの課題の解決に向けた取組を進めるに当たって、我が国の物流において中核的な役割を担うトラック運送サービスの持続可能な提供の確保に向けてトラックドライバーの ※4 運送・荷役等の効率化を推進することは、何も対策を講じなければ深刻な輸送力不足に陥るおそれもある中で、大きな意義を持つものであること。
こうした意義を踏まえ、トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進の目標については、安全性の確保を前提に、荷主、物流事業者、施設管理者をはじめとする物流に関わる様々な関係者が協力して、以下の事項を達成することを目標とする。
・ 令和10年度までに、日本全体のトラック輸送のうち5割の運行で荷待ち・荷役等時間を1時間削減することで、トラックドライバー1人当たり年間125時間の短縮を実現すること。
・ このためには、現状、トラックドライバーの1運行の平均拘束時間のうち、荷待ち・荷役作業等にかかる時間は計約3時間と推計されていることを踏まえ、この1運行当たりの荷待ち・荷役等時間が全国平均で計2時間以内となるよう荷待ち・荷役等時間を削減する必要があること。また、これを踏まえ、荷主等は、1回の受渡しごとの荷待ち・荷役等時間について、原則として目標時間を1時間以内と設定しつつ、業界特性その他の事情によりやむを得ない場合を除き、2時間を超えないよう荷待ち・荷役等時間を短縮すること。なお、1回の受渡しごとの荷待ち・荷役等時間がすでに1時間以内である荷主等については、その継続・改善に努めること。
・ 令和10年度までに、近年40パーセント以下の水準で推移してきた積載効率3について、日本全体のトラック輸送のうち5割の車両で50パーセントを目指し、全体の車両で44パーセントへの増加を実現すること。また、トラック輸送1運行当たりの輸送効率の向上に当たっては、重量ベースだけでなく、容積ベースでも改善を図ること。
3 積載効率=積載率×実車率。自動車輸送統計年報(国土交通省)より国土交通省において算出(輸送トンキロ/能力トンキロ(空車時のデータを含む。))。積載率=積載重量/最大積載重量。貨物の形状等によっては、容積ベースで考える場合もある。
4 規格化された容器に詰められた貨物を、複数企業の倉庫やトラック等をネットワークとして活用し輸送する共同輸配送システム。
・ これらの目標の達成に向けた取組を通じて、効率的な共同輸配送・共同拠点利用の仕組みであるフィジカルインターネット※4の実現を図るとともに、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第8条第1項に基づく地球温暖化対策計画(令和3年10月22日閣議決定)に対策・施策として位置付けられている脱炭素物流の推進に貢献すること。
(2)貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する施策に関する基本的な事項(第33条第2項第2号)
トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資するトラックドライバーの運送・荷役等の効率化に関する施策にかかる基本的な事項については、以下の事項を盛り込むこととする。
・ 国及び地方公共団体は、自らが荷主となる場合は、率先してトラックドライバーの運送・荷役等の効率化に資する措置を講ずるよう努めること。
・ 国及び地方公共団体は、自らが港湾管理者、空港管理者、卸売市場開設者である場合や、荷主に対して行政財産の使用許可等を根拠に施設の一部を使用させている場合といった施設管理者※5となる場合は、その施設の管理に関し、トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資する措置を講ずるよう努めること。
・ 国は、トラックドライバーの運転・荷役等の効率化に資する設備投資、デジタル化、物流標準化等に取り組む事業者を支援するため、調査・助言その他の必要な援助を講ずるよう努めるとともに、これらの援助に関する十分な情報の提供を行うこと。
・ 国は、輸送される物資のトラックへの過度の集中の是正に資するモーダルシフト等に取り組む事業者を支援するため、鉄道・海運等の輸送経路の拡充や輸送品質の向上等に向けた調査・助言その他の必要な援助を講ずるよう努めるとともに、これらの援助に関する十分な情報の提供を行うこと。
・ 国は、トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資するよう、トラック以外の大量輸送機関による貨物輸送の促進に向けた技術開発、自動運転トラックやドローン物流等の実用化を推進し、これらの成果の普及等に努めること。
・ 国は、フィジカルインターネットの実現に向けて、物流現場の自動化・機械化、デジタル化、省人化等の前提となる物流標準化を推進するため、官民連携により、納品伝票、外装表示、パレット・外装サイズ、商品や事業所等のコード体系・物流用語などの項目の標準化に向けて取り組み、これらの成果の普及等に努めること。
・ 国は、物流統括管理者として物流改善の取組を推進できる人材の確保・育成を支援するため、物流統括管理者の役割の普及・啓発などの必要な措置を講ずるよう努めるとともに、これらの人材を支える高度物流人材の確保・育成に取り組むこと。
・ 国は、トラック運送サービスの持続的発展に向けて担い手を確保していくため、多様な人材にとって快適で働きやすい職場環境を整備するとともに、その意義や魅力等について積極的な発信を行うこと。
・ 国は、物流が果たしている役割の重要性を物流事業者だけでなく社会全体の共通認識として位置付けるため、「ホワイト物流」推進運動5等の広報活動を通じて、荷主等に対して物流コストの転嫁や標準的な配送条件を販売先などに提示しやすい環境を整備するとともに、物流の危機的状況や物流に携わる労働者の社会的価値等について、国民の理解を深めるよう努めること。
5 深刻化が続くトラックドライバー不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に役立つことを目的として、①トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化、②女性や高齢ドライバー等も働きやすいより「ホワイト」な労働環境の実現を目指す取組。平成30年度から実施し、令和6年10月時点で2,933社(荷主企業1,228社、物流事業者1,705社)が賛同し、自主行動宣言を提出済み。
・ 国は、地球温暖化対策をはじめとする環境政策、国土政策、社会資本整備に関する政策等と十分に連携しつつ、トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資するトラックドライバーの運送・荷役等の効率化のために必要な措置を効果的に講ずることができるよう努めること。
(3)貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し、貨物自動車運送事業者等、荷主及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項(第33条第2項第3号)
トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資するトラックドライバーの運送・荷役等の効率化に関し、貨物自動車運送事業者等、荷主(発荷主・着荷主)及び貨物自動車関連事業者(倉庫、港湾運送、航空運送、鉄道)が講ずべき措置に関する基本的な事項について ※6
は、業界特性等の事業者の実情に合わせて取り組むことを前提としつつ、その具体的な取組方法を定める判断基準の方向性を示すものとして、以下の事項を盛り込むこととする。
① 荷主が講ずべき措置については、以下の事項とする。
・ 複数の荷主の貨物の積合せ、配送の共同化、帰り荷(復荷)の確保に向けた適切なリードタイムの確保や、運行効率向上のための発送量・納入量の適正化等により、トラックの積載効率の向上等※6を図ること。
6 新物効法第34条などに努力義務として規定されている「運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加」を達成する上では、積載率・実車率の向上だけでなく、車両の大型化等も有効であることから、本合同会議取りまとめにおいては、これらを示す語句として「積載効率の向上等」と記載している。
7 トラック事業者が自社の適正な運賃を算出し、荷主との運賃交渉に臨むに当たっての指標として、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)附則第1条の3第1項の規定に基づき、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃として令和6年国土交通省告示第209号において定められたものであり、個建運賃、有料道路料金、燃油サーチャージ等について規定されている。
・ 適切な貨物の入出荷日時の設定、トラック予約受付システムの導入等により、トラックドライバーの荷待ち時間を短縮すること。
・ パレット等の導入、検品の効率化、バース等の荷捌き場所の確保等により、トラックドライバーの荷役等時間を短縮すること。
・ これらの実効性確保のため、責任者の選任等の実施体制整備、取組状況・効果の把握、「標準的運賃」※7の活用、関係事業者との連携・協力等を行うこと。
② 連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの「本部」)が講ずべき措置については、以下の事項とする。
・ 適切なリードタイムの確保等により、トラックの積載効率の向上等を図ること。
・ 適切な貨物の入出荷日時の設定等により、トラックドライバーの荷待ち時間を短縮すること。
・ これらの実効性確保のため、責任者の選任等の実施体制整備、取組状況・効果の把握、関係事業者との連携・協力等を行うこと。
③ 貨物自動車運送事業者等が講ずべき措置については、以下の事項とする。
・ 輸送網の集約、配送の共同化、帰り荷(復荷)の確保等により、トラックの積載効率の向上等を図ること。
・ 関係事業者が行うトラックドライバーの運転・荷役等の効率化のための取組に協力すること。
・ 積載効率の向上等に伴うトラックドライバーへの負荷の低減に取り組むこと。
・ これらの実効性確保のため、取組状況・効果の把握、関係事業者との連携・協力等を行うこと。
④ 貨物自動車関連事業者が講ずべき措置については、以下の事項とする。なお、港湾運送、航空運送、鉄道事業者に対しては、荷役等時間の短縮についてのみ努力義務が課されることとなる。
・ 適切な貨物の入出荷時間の調整、トラック予約受付システムの導入等により、トラックドライバーの荷待ち時間を短縮すること。
・ 検品の効率化、バース等の荷捌き場所の確保等により、トラックドライバーの荷役等時間を短縮すること。※7
・ これらの実効性確保のため、取組状況・効果の把握、関係事業者との連携・協力等を行うこと。
(4)集貨又は配達に係る運転者への負荷の低減に資する事業者の活動に関する国民の理解の増進に関する基本的な事項(第33条第2項第4号)
集貨・配達に係るトラックドライバーへの負荷の低減に資する事業者の活動に関する国民の理解の増進に関する基本的な事項については、以下の事項を盛り込むこととする。
① 再配達の削減や多様な受取方法の普及促進等については、以下の事項とする。
・ 集貨・配達に係るトラックドライバーの負荷の低減のためには、急いで受け取る必要のない荷物についてゆとりをもった配送日時を指定したり、再配達を避けて多様な受取方法を活用したりするなど、配送サービスを日常的に利用する消費者である国民一人一人の理解と実践が不可欠であること。また、B to C物流だけでなく、B to B物流においても、再配達の削減に向けた事業者の理解と実践が必要であること。
・ 国は、「再配達削減PR月間」をはじめとする広報活動等を通じて、配送時間帯指定等に関する国民の理解を深めるとともに、コンビニ・ガソリンスタンドでの受取り、マンションや民間不動産、駅、公共施設等における宅配ボックスの設置、置き配が進む取組等を推進し、多様な受取方法の普及を図ること。
・ 国及び地方公共団体は、それぞれの立場から、再配達の削減や、路上を含め貨物集配中の車両が駐車できるスペースの確保等に取り組み、集貨・配達に係るトラックドライバーへの負荷の低減を図ること。
・ ECモールの運営事業者と通販事業者は、物流事業者・宅配事業者等と連携しながら、物流負荷の低い多様な受取方法の選択や配送日時指定の活用等を利用者に促す仕組みの社会実装に取り組み、再配達削減に向けた消費者の行動変容を促すこと。
② 返品の削減や欠品に対するペナルティの見直しについては、以下の事項とする。
・ 集貨・配達に係るトラックドライバーへの負荷の低減のためには、納品期限の緩和や賞味期限の大括り化、外装等の汚破損基準の見直し等による返品の削減や、欠品に対するペナルティの見直しに向けた関係事業者の理解と実践が必要であり、そのためにも、最終購買者である消費者の理解の増進が必要であること。
③ 「送料無料」表示の見直しについては、以下の事項とする。
・ 消費者の物流サービスに対するコスト意識の浸透と集貨・配達に携わるトラックドライバーに対する社会的な理解の醸成のため、商取引において物流サービスが無償で提供されていると誤解を招かないよう「送料無料」等の表現は見直しが求められており、「送料として商品価格以外の追加負担を求めない」旨の表示をする事業者は、その表示について説明責任を果たすこと。国は、消費者や事業者の理解醸成の取組を積極的に進めること。
(5)その他貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関し必要な事項(第33条第2項第5号)
その他トラック運送サービスの持続可能な提供の確保に資するトラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進に関し必要な事項については、以下の事項を盛り込むこととする。
① 物流に関わる多様な主体の役割については、以下の事項とする。 ※8
・ 消費者である国民一人一人は、物流事業者の負担となる短いリードタイムの是正のためにメーカー、卸売業者、小売店等の製造・販売事業者が行った取組の結果として、商品売場での品揃えや納品時期に影響が及ぶ場合があることについて理解を深めることが求められること。
・ 国は、地方支分部局と連携しながら、荷主、物流事業者等に対する規制的措置の執行に万全を期すこと。また、規制的措置の執行に当たっては、業界の特性、災害の発生その他の事情に配慮するとともに、業界等が策定した自主行動計画に即した取組について考慮すること。
・ 地方公共団体は、積載効率の向上等に資する共同輸配送等の取組の実施やそのための拠点づくりに向けて地域の関係者の合意形成に積極的に関与・参加するほか、地域の産業振興やまちづくり等と連携しながら荷捌き施設や休憩場所の確保等の取組を推進することが望ましいこと。
・ 港湾、空港、卸売市場、ショッピングセンター、中古車オークション会場等の施設管理者や、タワーマンション、オフィスビル、商業施設等を開発・運営するデベロッパー、商社やECモールの運営事業者、物流マッチングサービス提供事業者など、運送契約や貨物の受け渡しに直接関わりを持たないものの商取引に影響がある者も含め、経済界全体で、トラック運送サービスの持続可能な提供の確保の重要性に関する理解を深めるとともに、その実現に資する措置を講ずるよう努める必要があること。
・ 荷主は、トラックドライバーの拘束時間を削減するため、有料道路利用料の適切な負担のもと、トラック事業者に高速道路の利用を促すこと。
・ 元請トラック事業者及び貨物利用運送事業者8は、トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のための取組について第一種荷主※9から協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努める必要があること。また、第二種荷主※10や連鎖化事業者、運送依頼先のトラック事業者、実運送事業者等から協力を求められたときも、その求めに応ずることが望ましいこと。
8 貨物利用運送事業を行っているいわゆる3PL(third party logistics)事業者も含まれる。
9 自らの事業(貨物の運送の事業を除く。)に関して継続してトラック事業者に貨物の運送を行わせることを内容とする契約を締結する者(新物効法第30条第8号)であり、主に発荷主が該当する。
10 自らの事業(貨物の運送及び保管の事業を除く。)に関して継続して貨物(自らがトラック事業者に運送を委託する貨物を除く。)をトラックドライバー(他の者に雇用されている者に限る。)から受け取る者又は他の者をして受け取らせる者/引き渡す者又は他の者をして引き渡させる者(新物効法第30条第9号)であり、主に着荷主が該当する。
11 「官民物流標準化懇談会 パレット標準化推進分科会 最終とりまとめ(令和6年6月)」で定められた規格と運用に基づき、標準規格のパレット(11型等)を、標準化された方法で運用すること。
・ レンタルパレット事業者は、荷役作業の効率化に資する「標準仕様パレット」※11の利用拡大に向けた発信の継続や取組の充実、共同利用・共同回収の促進を図るとともに、契約への必要事項の明記に係る働きかけを含め、パレットの紛失防止対策を適切に実施することが求められること。また、レンタルパレットを利用する事業者は、当該パレットをレンタルパレット事業者との契約に定める範囲で適切に使用すること。
・ パレット製造事業者は、標準規格のパレット(11型等)の製造・販売、レンタルパレット市場への投入を拡大するとともに、安定的に供給可能な生産体制整備等を実施することが求められること。 ※9
② トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の前提となる事項については、以下の事項とする。
・ トラックドライバーの労働環境の改善に向けて、国、地方公共団体及び民間事業者は、それぞれの立場から、SA・PAや道の駅等において休憩環境の整備を進めるとともに、トラックドライバーの日帰り運行を可能とするための中継輸送拠点や、ダブル連結トラック・自動運転トラック等の運行のための拠点の整備を推進する必要があること。
・ 国は、トラックドライバーの適正な労働時間と適正な賃金の両立に向けて、契約内容の明確化とともに「標準的運賃」の更なる浸透や適切な見直し、国や地方公共団体等が荷主となる場合の活用の徹底を図るなど、官民一体となって賃上げ原資となる適正運賃を収受できる環境整備を進めるとともに、トラック事業者はトラックドライバーの賃上げを促進すること。
・ トラックドライバーの運送・荷役等の効率化に当たっては、トラック事業者の法令遵守が大前提である。国は、トラック事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為をしている悪質な荷主・元請トラック事業者・貨物利用運送事業者等に対して、トラック・物流Gメンによる是正指導等を徹底するとともに、独占禁止法又は下請法に違反するおそれがある場合も含め、悪質な荷主・トラック事業者・貨物利用運送事業者に対する処分の厳格化を図ること。また、荷主による法令遵守も不可欠である。国は、運送事業の許可を得ずに違法に運送を行う事業者の排除、運送責任の不明確化につながる行き過ぎた多重下請構造の是正やそのための実運送体制管理簿※12の積極的な活用、トラックドライバーに対するハラスメント等の防止を図ること。
12 物流改正法による改正後の貨物自動車運送事業法第24条の5に基づき元請事業者が作成する、実運送事業者に関する情報を記載・記録したもの。真荷主から引き受けた一定の重量以上の貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用したときに作成する。 ※10
2.荷主・物流事業者等の判断基準等について
○ 新物効法では、荷主、連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの「本部」)、貨物自動車運送事業者等及び貨物自動車関連事業者(倉庫、港湾運送、航空運送、鉄道)に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置については国が省令で判断基準を定めることとされている。また、事業者の理解増進の観点からは、取組事例等を記した判断基準の解説書の作成も重要である。これらについて、基本方針に定められた目標の達成のため、業界特性その他の事情を踏まえて取り組むこととした上で、それぞれ以下の事項を取組の例として示す必要がある。
(1)荷主の判断基準等について(新物効法第43条)
荷主(発荷主・着荷主)の判断基準・解説書については、以下の事項を取組の例として盛り込むこととする。なお、以下の事項による取組が目標達成に対し業界特性や作業員等の安全性の確保その他の事情により有効でない場合は、これによらないことも可能とする必要がある。
① 積載効率の向上等に関する事項については、以下の事項とする。
・ トラック事業者が複数の荷主の貨物の積合せ、共同配送、帰り荷(復荷)の確保等に積極的に取り組めるよう、実態に即した適切なリードタイムの確保や荷主間の連携に取り組むこと。
・ トラック事業者の運行効率向上のため、年単位・月単位・週単位等の繁閑差の平準化や納品日の集約等を通じた発送量・納入量の適正化や、配車システムの導入等を通じた配車・運行計画の最適化に取り組むこと。なお、繁閑差の平準化が容易ではない場合は、納入単位・回数の集約等に取り組むこと。
・ 社内の関係部門(物流・調達・販売等)の連携を促進することにより、適切なリードタイムの確保や発送量・納入量の適正化を図ること。
② 荷待ち時間の短縮に関する事項については、以下の事項とする。
・ トラックが一時に集中して到着することがないよう、トラック予約受付システムの導入や混雑時間を回避した日時指定等により、貨物の出荷・納品日時を分散させること。なお、トラック予約受付システムについては、単にシステムを導入するだけではなく、関係事業者の配送スケジュールに配慮した予約時間の調整や利用率の向上など、現場の実態を踏まえ実際に荷待ち時間の短縮につながるような効果的な活用を行うこと。
・ 寄託先の倉庫に対する受発注の前倒しを行うこと等により、倉庫業者の適切な作業時間を確保するとともに、貨物の出荷・納品日時を分散させること。
③ 荷役等時間※13の短縮に関する事項については、以下の事項とする。
13 トラックドライバーに荷役等を行わせる場合に限る(新物効法第42条第1項第3項等)。
・ パレット、ロールボックスパレット(カゴ車)等の輸送用器具の導入により、荷役等の効率化を図ること。なお、パレットを使用する場合は、発荷主・着荷主等の関係事業者間で協力して、発注数や納品数の調整を行うとともに、一貫パレチゼーションの実現 ※11に向けて「標準仕様パレット」やこれに適合する包装資材の導入等のパレット標準化に向けた取組を行うこと※14。
14 「官民物流標準化懇談会 パレット標準化推進分科会 最終とりまとめ(令和6年6月)」においては、製品の特性上標準仕様パレットを活用できない場合等、標準仕様パレットの導入が当分の間困難な場合においては、「設備改修等のタイミングも勘案しつつ、将来的な標準仕様パレットの導入を期待する。」とされている。
・ バーコード等の商品を識別するタグの導入、検品・返品水準の合理化、管理単位の統一等により、検品の効率化を図ること。また、食品流通の効率化に資する賞味期限の大括り化等に取り組むこと。
・ 事前出荷情報の活用により、伝票レス化・検品レス化を図ること。
・ バース等の荷捌き場について、貨物の物量に応じて適正に確保し、荷役作業が行える環境を整えること。
・ フォークリフトや荷役作業員の適切な配置等により、トラックドライバーの負担軽減と積卸し作業の効率化を図ること。
・ 貨物の出荷を行う際には、出荷荷積み時の順序や荷姿を想定した生産・荷造り等を行うことにより、荷役等の効率化を図ること。
④ 上記①~③の実効性確保に関する事項については、以下の事項とする。
・ 発荷主・着荷主間において連携を図ること。
・ 寄託先の倉庫における荷待ち・荷役等時間の短縮の達成のために、当該倉庫・発荷主・着荷主間において、事前出荷情報や、それに付随する容積、数量、重量、寸法等の情報、寄託者、運送事業者に関する情報を事前に伝達すること。また、入出庫日程・量の調整や定時便の設定などに関する寄託先の倉庫からの提案に応じるなど、当該倉庫等と必要に応じた協力・連携を行うこと。
・ 貨物の入出庫に当たって、トラックドライバーに寄託者、貨物や施設等の詳細に関する情報を適切に伝達すること。
・ 責任者の選任や社内教育等の実施体制整備を行うこと。
・ やむを得ない遅延に対するペナルティの見直しなど、荷主が指示した時刻・時間帯よりも必要以上に早くトラックドライバーが集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に到着することがないよう配慮すること。
・ 荷待ち・荷役等時間の状況や取組の効果を適切に把握すること。これらの状況や効果の把握に当たっては、デジタル技術の活用等により効率的に行うよう努めること。
・ レンタルパレットを使用する場合は、関係事業者との間で適正な費用分担等を徹底すること。
・ 物流情報標準ガイドラインへの準拠などの物流データの標準化に取り組むこと。
・ 貨物の運送を委託する際は、モーダルシフト等により、輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に努めること。
・ 異常気象時(台風・豪雨・豪雪等)に無理な運送を行わせないこと、荷役等を行わせる際の作業安全の確保等、トラックドライバーの安全・休憩環境の確保に配慮すること。
・ トラック事業者との運送契約の締結の協議の際に、物流効率化にも資する正当な対価の基準である「標準的運賃」を活用すること。
・ 発荷主・着荷主・物流事業者間の取引における物流コストの可視化を通じて、物流サービスに応じた価格設定の仕組みを導入すること。 ※12
・ 契約内容に関する交渉の場や物流現場の課題に関する相談や協議の窓口を設けるなど、関係事業者間での連携を図るとともに、必要に応じて取引先に対して協力を求めること。また、取組や費用負担等について必要に応じて契約内容の見直し※15を行うこと。
15 例えば、運送事業者と契約関係にない着荷主の責による荷待ち時間や契約にない附帯作業などの対価については、発荷主と着荷主との契約において適切に整理すること等が必要である。
(2)連鎖化事業者の判断基準等について(新物効法第62条)
連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの「本部」)の判断基準・解説書については、以下の事項を取組の例として盛り込むこととする。なお、以下の事項による取組が目標達成に対し業界特性や作業員等の安全性の確保その他の事情により有効でない場合は、これによらないことも可能とする必要がある。
① 積載効率の向上等に関する事項については、以下の事項とする。
・ 商品の発注先等が運送委託のタイミングから連鎖対象者における貨物の受渡しまでの間に適切なリードタイムを確保できるよう、適切なリードタイムを確保した発注をする等の協力を行うこと。
・ トラック事業者の運行効率向上のため、年単位・月単位・週単位等の繁閑差の平準化や納品日の集約等を通じた納入量の適正化や、配車システムの導入等を通じた配車・運行計画の最適化に取り組むこと。なお、繁閑差の平準化が容易ではない場合は、納入単位・回数の集約等に取り組むこと。
・ 社内の関係部門(物流・調達・販売等)の連携を促進することにより、適切なリードタイムの確保や納入量の適正化を図ること。
② 荷待ち時間の短縮に関する事項については、以下の事項とする。
・ トラックが一時に集中して到着することがないよう、混雑時間を回避した日時指定等により、貨物の納品日時を分散させること。
③ 上記①及び②の実効性確保に関する事項については、以下の事項とする。
・ 発荷主・連鎖化事業者間において連携を図ること。
・ 責任者の選任や社内教育等の実施体制整備を行うこと。
・ やむを得ない遅延に対するペナルティの見直しを行うなど、連鎖化事業者が指示した時刻・時間帯よりも必要以上に早くトラックドライバーが集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に到着することがないよう配慮すること。
・ 荷待ち時間の状況や取組の効果を適切に把握すること。これらの状況や効果の把握に当たっては、デジタル技術の活用等により効率的に行うよう努めること。
・ 物流情報標準ガイドラインへの準拠などの物流データの標準化に取り組むこと。
・ 関係事業者間での連携を図るとともに、必要に応じて取引先に協力を求めること。また、取組や費用負担等について必要に応じて契約内容の見直しを行うこと。
(3)貨物自動車運送事業者等の判断基準等について(新物効法第35条)
貨物自動車運送事業者等の判断基準・解説書については、以下の事項を取組の例として盛り込むこととする。なお、以下の事項による取組が目標達成に対し業界特性や作業員等の安全性の確保その他の事情により有効でない場合は、これによらないことも可能とする必要がある。 ※13
① 積載効率の向上等に関する事項については、以下の事項とする。
・ 複数の荷主の貨物の積合せを行うこと等により、輸送網を集約すること。
・ 荷主、連鎖化事業者、貨物利用運送事業者、他のトラック事業者と必要に応じて協議を実施し、配送の共同化に取り組むこと。
・ 求貨求車システム等を活用した帰り荷(復荷)の確保により、実車率の向上を図ること。
・ 配車システムの導入等により、配車・運行計画の最適化を行うこと。
・ 輸送量に応じた大型車両の導入等により、運送ごとの貨物の総量を増加させること。
② 上記①及び関係事業者(荷主、倉庫業者等)の取組の実効性確保に関する事項については、以下の事項とする。
・ トラックドライバーの荷待ち・荷役等時間や取組の効果を適切に把握すること。また、荷主等が荷待ち・荷役等時間を把握することが難しい場合に協力・情報提供すること。なお、トラックドライバーの荷待ち・荷役等時間の把握に当たっては、デジタルタコグラフ等のデジタル技術の活用等により効率的に行うよう努めること。
・ 貨物の受渡しに当たっては、寄託者や貨物に関する詳細な情報を適切に把握すること。
・ 関係事業者がトラック予約受付システムを導入している場合は、そのシステムを利用すること。
・ 荷主、連鎖化事業者が指示した時刻・時間帯に遅延する場合は荷主や寄託倉庫にその状況を報告するとともに、理由なく必要以上に早くトラックドライバーが集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に到着しないよう、効率的な配車・運行に努めること。
・ 取引先に対して、標準仕様パレットの活用、共同輸配送のための個建て運賃の導入、リードタイムに応じた運賃設定などの提案を行うこと。
・ 関係事業者間での連携を図るとともに、必要に応じて取引先に協力を求めること。また、取組や費用負担等について必要に応じて契約内容の見直しを行うこと。
・ 物流情報標準ガイドラインへの準拠など物流データの標準化に取り組むこと。
・ テールゲートリフターの導入、荷捌き施設の整備など積載効率の向上等に伴うトラックドライバーの積卸し作業の負荷低減を図ること。
・ 積載効率の向上等に当たっては、トラックの過積載など事業の正常な運営が阻害されないよう、関係法令を遵守すること。
(4)貨物自動車関連事業者の判断基準等について(新物効法第53条)
貨物自動車関連事業者(倉庫、港湾運送、航空運送、鉄道)の判断基準・解説書については、以下の事項を取組の例として盛り込むこととする。なお、以下の事項による取組が目標達成に対し業界特性や作業員等の安全性の確保その他の事情により有効でない場合は、これによらないことも可能とする必要がある。
① 荷待ち時間の短縮については、以下の事項とする※16。
16 倉庫業者のみ努力義務が課される。
・ トラックが一時に集中して到着しないよう、トラック予約受付システムの導入や混雑時間を回避した日時指定等により、トラックの到着時間を調整すること。なお、トラック予約受付システムについては、単にシステムを導入するだけではなく、関係事業者の ※14
配送スケジュールに配慮した予約時間の調整や利用率の向上など、現場の実態を踏まえ実際に荷待ち時間の短縮につながるような効果的な活用を行うこと。
② 荷役等時間の短縮については、以下の事項とする※17。
17 全ての貨物自動車関連事業者に努力義務が課される。
18 荷待ち時間の把握については倉庫業者のみ、荷役等時間の把握については全ての貨物自動車関連事業者が対象となる。
・ 荷主から一貫パレチゼーション実現のためにパレットでの納品について提案された際には、パレット費用の適正な価格転嫁が確認できれば、その提案に協力を行うこととし、荷役等の効率化を図ること。
・ 倉庫から着荷主向けの配送車両への荷積みについて、倉庫業者の作業費用の適正な価格転嫁が確認できれば、納品先単位に仕分けた状態で貨物をトラックドライバーに引き渡し、荷役等の効率化を図ること。
・ 検品を効率的に実施するための機器を導入すること等により、検品作業の時間を短縮すること。
・ バース等の荷捌き場について、貨物の物量に応じて適正に確保し、荷役作業が行える環境を整えること。
・ フォークリフトや荷役作業員の適切な配置等により、トラックドライバーの負担軽減と積卸し作業の効率化を図ること。
・ 荷役前後の搬出入の実施に関するマニュアルの作成や周知等により、搬出入を迅速に行うこと。
③ 上記①及び②の実効性確保に関する事項については、以下の事項とする。
・ トラックドライバーの荷待ち・荷役等時間18や取組の効果を適切に把握すること。これらの状況や効果の把握に当たっては、デジタル技術の活用等により効率的に行うよう努めること。また、荷主等が荷待ち・荷役等時間を把握することが難しい場合に協力・情報提供すること。
・ 寄託者である荷主に対し物流改善の提案を行うなど、必要に応じた協力・連携を行うこと。
・ 責任者の選任や社内教育等の実施体制整備を行うこと。
・ 無人搬送車、ピッキングロボット等の導入等により、自動化・機械化を図ること。
・ 物流情報標準ガイドラインへの準拠など物流データの標準化に取り組むこと。
・ 関係事業者間での連携を図るとともに、必要に応じて取引先に協力を求めること。また、取組や費用負担等について必要に応じて契約内容の見直しを行うこと。
○ このほか、本合同会議委員及びヒアリングを行った業界団体からは、各事業者の取組の促進の観点から、以下の事項を解説書等に記載すべきとの意見があった。
・ 第一種荷主や第二種荷主に該当する荷主の具体例について、パターンに分けて解説すること。
・ 1運行2時間ルールの達成に向けて、重点的に改善する運行例を具体的に明示すること。
・ 偽装請負防止のため、荷待ち・荷役等時間の短縮を目的とした荷主とトラックドライバー、荷主と倉庫業者とのコミュニケーション事例を解説書で示すこと。 ※15
・ 物流に必要な労働に適正な対価を支払うという観点から、荷主の業界団体と連携しながら、業界・分野別に、運賃、荷役、高速道路料金等をどのように負担するか記載した標準的な運送契約書のひな形を作成すること。 ※16
3.荷主等の取組状況に関する調査・公表について
〇 新物効法第71条では、国は、トラック運送サービスの持続的な提供の確保に資するトラックドライバーの運送・荷役等の効率化のために必要があると認めるときは、荷主等の判断基準に関して調査を行い、その結果の公表を行うこととされている。
〇 この調査・公表の具体的な方法については、以下のとおりとする必要がある。
(1)トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のための取組の実施状況について荷主等を対象とした網羅的な調査を行うことは、事業者数の多さや業種の多様性を考慮すると困難であるため、これらの荷主等との間で貨物のやりとりを行っている物流事業者(トラック、倉庫等)を対象として、優良な取組状況の把握や物流改善の促進を目的とした定期的なアンケート調査を実施する。なお、当該アンケート調査は、荷主と物流事業者間の関係性を崩さずに実態を聴取できるようなものとすることが求められる。
(2)定期的なアンケート調査の実施に当たっては、物流事業者からの回答に基づいて主要な荷主等を抽出した上で、当該荷主等の取組状況について荷待ち・荷役等時間の短縮、積載効率の向上等に関する項目別に把握するとともに、これらの回答を点数化し、点数の高い者・低い者も含め公表する。なお、点数の低い荷主等の公表の検討に当たっては、当該荷主等が実際に行っている物流効率化に向けた取組状況をヒアリングするなど適切に実態を把握し、その実態を踏まえ、必要に応じて点数を見直すこととする。
(3)アンケート調査の結果、荷主等において長時間の荷待ち、契約にない附帯業務、無理な運送依頼等が常態化しているなど悪質な事例を捕捉した場合には、当該事例の実態やそれに対する荷主等の取組状況について、必要に応じて荷主等からのヒアリング調査等を行い、これらの調査結果については、トラック・物流Gメンや公正取引委員会等による働きかけや要請等につなげていく。 ※17
4.「荷待ち時間」と「荷役等時間」の算定方法について
〇 新物効法第30条第4号及び第5号では、荷主・物流事業者等が物流効率化のために取り組むべき措置の実施状況の評価の前提となる「荷待ち時間」と「荷役等時間」の算定方法を国が省令で定めることとされている。
○ 「荷待ち時間」と「荷役等時間」の具体的な算定方法は以下のとおりとする必要がある。
(1)荷待ち時間については、以下のとおりとする。
① 到着時刻・時間帯の指示がない場合
トラックドライバーが集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に到着した時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)から荷役等の開始時刻までとする。
② 到着時刻・時間帯の指示があった場合
トラックドライバーが集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に、指示された到着時刻・時間帯の始期よりも前に到着した場合は、指示時刻等から荷役等の開始時刻までとする。
トラックドライバーが集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に、指示された到着時刻・時間帯内に到着した場合は、当該到着時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)から荷役等の開始時刻までとする。
トラックドライバーが集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に、指示時刻・時間帯の終期よりも後に到着した場合は、当該到着時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)から荷役等の開始時刻までとする。ただし、トラック事業者やトラックドライバーの都合で指示時刻等を過ぎたことにより生じた待機時間については、荷待ち時間として計測しない。
(2)荷役等時間については、以下のとおりとする。
① トラックドライバーが行う荷役、検品、荷造り、入庫・出庫、棚入れ・棚出し、仕分け、商品陳列、ラベル貼り、代金の取立て・立替えなど、運転業務に附帯する業務の開始時間から終了時間までとする。
② 荷卸しと荷積みを並行して行うケースや帰り荷(復荷)の積込みを行うケース、輸送用機器を持ち帰るケースなど、1つの施設内で荷卸しと荷積みの両方を行う場合は、積載効率の向上等に向けた事業者の取組を阻害しないよう、荷卸しと荷積みを別々に計測することも許容することとする。
○ また、荷待ち時間等(荷待ち時間+荷役等時間)については、トラックドライバーが集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に到着した後速やかに受付等を行わずに業務上の指示等により休憩する時間は除外するが、迅速に車両を動かせるような状態での待機や荷役作業中の立ち会いが要求されているなど、業務から完全に離れることができず、実質的に休憩がとれていない時間は、これらの計算から除外しないことを明確化して運用する。
○ なお、トラックドライバーによる荷待ち時間等の計測については、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第8条において大型トラック(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上※18)が対象とされている荷待時間・荷役作業等の記録の義務付けについて、義務付けの範囲が拡大される予定である※19。
19 令和6年10月1日に公布された自動車事故報告規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第90号)が、物流改正法の施行の日から施行される予定である。 ※19
5.物流に関係する事業者等の責務について
○ 新物効法第32条においては、物資の流通に関する事業を行う者、その事業を利用する事業者及び物資の流通に関する施設を管理する者は、その事業の実施又はその施設の管理に関し、これらに伴う運転者への負荷の低減その他の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する措置を講ずるよう努めることとされている。
○ 荷主、物流事業者等については判断基準を定めて取り組むべき事項を示すこととなるが、これらに該当しない、港湾、空港、卸売市場、ショッピングセンター、中古車オークション会場等の施設管理者や、タワーマンション、オフィスビル、商業施設等を開発・運営するデベロッパー、商社やECモールの運営事業者、物流マッチングサービス提供事業者など、運送契約や貨物の受け渡しに直接関わりを持たないものの商取引に影響がある者については、取り組むべき事項が明らかとなっていないため、これらの者に係る取組方針や事例等を示すことについて検討を行う必要がある。
○ また、港湾、空港、鉄道駅においては、新物効法に基づく荷役等時間の短縮の努力義務の対象である港湾運送事業者、航空運送事業者、鉄道事業者の取組に加え、これらの施設等において現に生じているトラックドライバーの待機に影響を与えている者に対しても、必要な取組方針等を示すことが求められる。 ※20
Ⅲ 公布の日から2年以内に施行される規定関係
1.特定事業者の指定基準等について
○ 新物効法では、一定の基準以上の荷主、連鎖化事業者、貨物自動車運送事業者等及び倉庫業者に、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、努力義務について判断基準に照らし実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施することとされている。
○ 上記の基準については、特定事業者(特定荷主、特定連鎖化事業者、特定貨物自動車運送事業者等及び特定倉庫業者)として全体への寄与がより高いと認められる大手の事業者が指定されるよう、国が政令で定めることとされており、以下のとおりの基準とする必要がある。なお、以下の指定基準値については、大手の事業者から順に、日本全体の貨物量などの半分程度となる事業者を指定するという基本的な考え方の下で設定したが、特定事業者に係る制度の施行後の事業者への浸透状況や今後の状況変化等を踏まえ、必要に応じて見直すことも考えられる。
(1)特定荷主及び特定連鎖化事業者(第45条第1項及び第5項並びに第64条第1項)
① 指定基準値
取扱貨物の重量9万トン以上とする※20。ここで、取扱貨物の重量は、事業者としての全体の重量ではなく、第一種荷主、第二種荷主又は連鎖化事業者それぞれの立場での重量を指す。
20 上位3,200社程度が該当する見込み。
21 なお、例えば、自社拠点間の運送においてmトンの貨物を「自社工場→自社施設→自社物流センター」というフローで運送している場合は、mトンの貨物を2回運送させているため、当該フロー全体における「取扱貨物の重量」は2mトンとなる(ただし、自社工場や自社施設等の施設が同一拠点内になる場合、同一拠点内の施設間の運送は計測対象に含めない。)。
22 同上。
23 同上。
② 指標の算定方法
特定第一種荷主については、各年度において、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物の合計の重量※21とする。
特定第二種荷主については、各年度において、次に掲げる貨物の合計の重量22とする。ただし、当該第二種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの並びに当該第二種荷主が貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができないものを除く。
(ⅰ)自らの事業に関して、運転者から受け取る貨物
(ⅱ)自らの事業に関して、他の者をして運転者から受け取らせる貨物
(ⅲ)自らの事業に関して、運転者に引き渡す貨物
(ⅳ)自らの事業に関して、他の者をして運転者に引き渡させる貨物
連鎖化事業者については、各年度において、次に掲げる貨物の合計の重量※23とする。ただし、当該連鎖化事業者の連鎖対象者が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に※21運送を委託するもの並びに当該連鎖化事業者が連鎖対象者との定型的な約款による契約に基づき受渡しの日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない貨物を除く。
(ⅰ)当該連鎖化事業者の連鎖対象者が運転者から受け取る貨物
(ⅱ)当該連鎖化事業者の連鎖対象者が他の者をして運転者から受け取らせる貨物
なお、軽い重量の貨物を取り扱う発荷主となる業種や、卸売業、小売業などの着荷主となるケースが多い特殊性を有する業種においては、重量を把握することに多大なコストがかかることが想定されるため、重量の算定に当たっては、例えば、下記の算定方法を用いることを可能とする。
・ 商品マスタ等において重量のデータを集計することが可能な場合にあっては、当該システムに登録されている重量を元に換算する
・ 容積を把握している場合においては、1立方メートルあたり280kgとして換算する
・ 輸送するトラックの最大積載量を貨物の重量として換算する
・ 売上金額や仕入金額を元に貨物の重量を換算する 等
③ 指定基準値の根拠
国土交通省「全国貨物純流動調査(物流センサス)報告書」(令和5年3月)及び総務省・経済産業省「令和3年経済センサス–活動調査」(令和5年6月27日)を元に試算し、第一種荷主、第二種荷主及び連鎖化事業者の取扱貨物の重量が多い順に対象とし、全体の50%をカバーする基準値及び対象事業者数を算出した。
(2)特定倉庫業者(第55条第1項)
① 指定基準値
貨物の保管量70万トン以上とする※24。
24 上位70社程度が該当する見込み。
25 上位790社程度が該当する見込み。
② 指標の算定方法
倉庫業者が寄託を受けた物品を保管する倉庫において入庫された貨物の年度の合計の重量とする。
③ 指定基準値の根拠
各倉庫業者から提出された「受寄物入出庫高及び保管残高報告書」(令和4年1月~12月分)を元に試算し、貨物の保管量が多い順に対象とし、全体の50%をカバーする基準値及び対象事業者数を算出した。
(3)特定貨物自動車運送事業者等(第37条第1項)
① 指定基準値
保有車両台数150台以上とする25。
② 指標の算定方法
年度末において保有する事業用自動車の台数とする。 ※22
③ 指定基準値の根拠
国土交通省「令和4年度 貨物自動車運送事業輸送実績調査」を元に、元請としての輸送能力を加味した上で試算し、輸送能力が多い順に対象とし、全体の50%をカバーする基準値及び対象事業者数を算出した。 ※23
2.中長期計画・定期報告の記載事項について
○ 新物効法では、特定荷主、特定連鎖化事業者、特定貨物自動車運送事業者等及び特定倉庫業者に、中長期計画の作成や定期報告等を義務付けることとされている(新物効法第38条、第39条、第46条、第48条、第56条、第57条、第65条及び第67条)。
○ 中長期計画及び定期報告の記載事項は、事業者の取組状況把握に当たっての有力な端緒情報となるため、事業者における「取組の実効性の担保」と「業務負荷の軽減」を両立する観点から、具体的な記載事項等は、以下の内容とする必要がある。
(1)中長期計画について
新物効法では、特定事業者は、定期に判断基準を踏まえた措置の実施に関する中長期的な計画を作成することとされており、その作成期間及び記載内容は以下のとおりとする必要がある。
①作成期間
毎年度提出することを基本としつつ、中長期的に実施する措置を記載することを踏まえ、計画内容に変更がない限りは、5年に1度提出することとする。
②記載内容
判断基準で示す取組事項を踏まえ、「運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加」、「運転者の荷待ち時間の短縮」、「運転者の荷役等時間の短縮」に関し、(ⅰ)実施する措置、(ⅱ)具体的な措置の内容・目標等、(ⅲ)実施時期等、(ⅳ)参考事項を記載することとする。
(2)定期報告について
新物効法では、特定事業者は、特定事業者として指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、努力義務の実施の状況に関し報告しなければならないこととされており、その具体的な内容は以下のとおりとする必要がある。
①記載内容
事業者の判断基準の遵守状況(チェックリスト形式を想定)、関連事業者との連携状況等の判断基準と関連した取組に関する状況(自由記述欄を想定)、荷待ち時間等の状況を記載することとする。
②荷待ち時間等の状況について
(ⅰ)前提
特定荷主等(特定荷主、特定連鎖化事業者及び特定倉庫業者)自身が荷待ち時間等の現状を把握し、どの程度改善する必要があるかを認識することができるような記載事項とするが、「取組の実効性の担保」と「業務負荷の軽減」の双方の観点から合理的な方法とすることが求められる。
(ⅱ)具体的方法の考え方 ※24
特定荷主等は、自らが管理する施設等における荷待ち時間等を計測し、報告することとする。
他方、全ての施設の全ての運行において、荷待ち時間等を計測することが費用や作業負担等の観点から必ずしも合理的でないケースも想定されることから、取組の実効性の担保を前提としたサンプリング等の手法の実施や、業務負荷の軽減のために荷待ち時間等が一定時間以内である場合等の報告省略を可能とする。その上で、荷待ち時間等の計測に当たっては、デジタル技術の活用等により効率的な把握を実施し、より多くの施設における物流改善につなげていくことが望ましい。
(ⅲ)計測方法について
荷待ち時間等(荷待ち時間+荷役等時間)について、荷待ち時間と荷役等時間の発生原因やその改善に向けた対応策は異なることから、1回の受渡しごとの荷待ち時間と荷役等時間の状況を把握した上で、それぞれ改善を行っていく必要がある。このため、原則としては、荷待ち時間と荷役等時間を分けてそれぞれ計測することとする。他方、実態として切り分けられない場合等は「荷待ち時間等」として「荷待ち時間」と「荷役等時間」を分けないで計測することも可能とする。
また、1つの事業所(工場等)内にトラックの停留場所を備えた施設が複数箇所あり、1回の運送で複数の施設を回って貨物の積込み又は積卸し等を行う場合は、原則、各施設における荷待ち時間等を計測することとする。他方、1つの事業所全体を1施設として、入構から出構までの時間を「1回の受渡しに係る荷待ち時間等」として計測した場合、事業所内を走行する時間が荷待ち時間等に含まれてしまい、荷待ち時間等を過大に評価してしまう可能性があるが、実態として切り分けられない場合等は、事業所全体を1施設として計測することも可能とする。
(ⅳ)計測対象施設等について
【対象施設について】
新物効法では、荷主が短縮すべき荷待ち時間等(連鎖化事業者の場合は荷待ち時間)については、
(ア) 荷主(又は連鎖化事業者)が管理する施設
(イ) 荷主(又は連鎖化事業者)との間で貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設
におけるもの(荷待ち時間については当該施設の周辺の場所も含む。)と規定している。
荷主(又は連鎖化事業者)においては、上記(イ)の施設についても荷待ち時間等の短縮の努力義務が課されているため、当該施設における荷待ち時間等の状況を把握した上でその改善につなげていくことが望ましい。他方、上記(イ)を全面的に荷待ち時間等の計測対象とすると、場合によっては倉庫業者等との寄託契約の変更が必要なケースがあり、当該契約の変更ができない場合には当該施設における荷待ち時間等の報告ができず、定期報告の義務を履行できない。
このため、上記(ア)を荷待ち時間等の計測対象とした上で、上記(イ)の施設の荷待ち時間等の改善に向けては、寄託契約を締結した者が管理する施設の名称を定期報告に記載し、荷待ち時間等の短縮に向けて、寄託先と連携しながら具体的にどのような取組を行っているか等について定期報告に記載することとする。また、契約に基づき※25寄託先の倉庫業者等から荷待ち時間等の状況やそれを踏まえた改善の提案等を受けることができる場合においては、これらを把握した上で改善につなげていくこととする。
【サンプリングについて】
特定荷主等自身が管理する全ての施設において荷待ち時間等を計測することは、費用や作業負担等の観点から、必ずしも合理的でないケースがあることが想定される。
このため、可能な場合は全施設全運行の荷待ち時間等を計測することとするが、全施設全運行での荷待ち時間等の計測が難しい特定荷主等においては、取組の実効性の担保を前提としたサンプリング等の手法を用いて報告することを許容することとする(※1)。このサンプリングについては、特定荷主等自身が荷待ち時間等の現状や課題を認識するために行うものであり、全体の改善につなげていく観点で適切な手法を示す必要がある。
【報告省略について】
荷待ち時間等の計測対象となる施設数については、サプライチェーンの上流に位置する荷主企業(メーカー等)と下流に位置する荷主企業(小売業等)では大きく異なり、特に地区ごとに複数の店舗や集貨・分荷のための拠点を持つ小売業、卸売業等では非常に多いと考えられる。
当該特定荷主等(主に特定第二種荷主)の負荷軽減のため、1回の受渡しに係る荷待ち時間等が一定時間以内又は業界特性や環境を踏まえて更なる短縮が難しい場合については、報告の省略を可能とすることとする(※2)。
なお、当該運用については、特定荷主等の種類にかかわらず、全ての施設に適用することで、1回の受渡しに係る荷待ち時間等を一定時間以内にまで短縮するインセンティブとし、荷待ち時間等の短縮のための取組を促すこととする。
【報告方法について】
計測した荷待ち時間等の平均時間を、施設ごとに報告することとする。
(※1)サンプリング等の手法については、①どの程度のサンプリングを許容するか、②どのように客観性の担保をするか、といった点から継続的に検討を行う必要があるが、以下の方向性が考えられるのではないか。
・ 計測対象施設、計測期間、計測対象運行ごとに、抽出の最低数値を示すこと。
・ 特定荷主等においては、示された最低数値以上の施設、期間、運行を自ら選定し、計測を実施し、報告することとすること。
・ 最低値としては以下の方向性が考えられるのではないか。
対象施設:取り扱う貨物重量の半分程度を把握することを念頭に、特定荷主等自身が管理する全ての施設から、年間において取扱貨物の重量が大きい施設
対象期間:四半期ごとに任意の連続した5営業日以上(前年度の実績に照らして、各四半期中最も売上金額が低いと見込まれる月は対象外)
対象運行:原則として対象施設で計測した全ての運行 ※26
(※2)報告の省略を可能とする場合は、以下の場合としてはどうか。
・ 荷待ち時間等が1時間以内である場合(荷待ち時間と荷役等時間を分けて計測し、その合計が1時間以内である場合を含む。)
※連鎖化事業者においては荷待ち時間が30分以内である場合
・ 荷役等の業務に要する時間が安全性又は衛生等の観点から短縮することが難しく、例えば、以下に該当すると認められる場合
① 特殊車両を用い、洗浄等の附帯作業が必須となる
② 危険物を扱うことから、安全確認のため時間を要する
③ 重量物を扱うことから、安全確認のため時間を要する 等
・ なお、上記(※1)及び(※2)の詳細については、各業界の特性や業務負荷等にも留意しつつ、制度施行までの間に引き続き検討をしていく必要がある。 ※27
3.物流統括管理者(CLO)の業務内容について
〇 新物効法第47条及び第66条では、特定事業者のうち特定荷主及び特定連鎖化事業者に物流統括管理者(CLO26)の選任を義務付けている。
26 CLO:Chief Logistics Officer
○ 物流統括管理者は、物流全体の持続可能な提供の確保に向けた業務全般を統括管理する者である。
物流統括管理者の業務を遂行するためには、運送(輸送)、荷役といった物流の各機能を改善することだけではなく、調達、生産、販売等の物流の各分野を統合して、流通全体の効率化を計画するため、関係部署間の調整に加え、取引先等の社外事業者等との水平連携や垂直連携を推進することなどが求められ、これらの観点から事業運営上の決定を主導することとなる。
このため、ロジスティクスを司るいわゆるCLOとしての経営管理の視点や役割も期待されていることから、その立場としては、基本として、重要な経営判断を行う役員等の経営幹部から選任されることが必要である。
○ こうした中、新物効法上の物流統括管理者は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者をもって充て、以下の業務を統括管理することとされており、これらのうち、下記③の業務の具体的な内容については、省令で定めることとされている。
① 中長期計画の作成
② トラックドライバーの負荷低減と輸送される物資のトラックへの過度の集中を是正するための事業運営方針の作成と事業管理体制の整備
③ その他トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のために必要な業務
〇 物流統括管理者は、新物効法に基づく義務等に対して全社的な責任を持って対応する必要があることから、上記③の業務として、以下の業務を規定する必要がある。
(ⅰ) 定期報告の作成
(ⅱ) 貨物運送の委託・受渡しの状況に関する国からの報告徴収に対する当該報告の作成
(ⅲ) 事業運営上の重要な決定に参画する立場から、リードタイムの確保、発注・発送量の適正化等のための社内の関係部門(開発・調達・生産・販売・在庫・物流等)間の連携体制の構築
(ⅳ) トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のための設備投資、デジタル化、物流標準化に向けた事業計画の作成、実施及び評価
(ⅴ) トラックドライバーの運送・荷役等の効率化に関する職員の意識向上に向けた社内研修等の実施
〇 上記に加え、フィジカルインターネットの実現に向けた水平連携や垂直連携の推進のためには、他の荷主や物流事業者をはじめとする様々な関係者と連携しながら、商慣行の見直しやオペレーションの調整、物流標準化などに取り組む必要があることから、以下の業務も規定する必要がある。 ※28
(ⅵ) 物資の保管・輸送の最適化に向けた物流効率化のため、調達先及び納品先等の物流統括管理者や物流事業者等の関係者との連携・調整
○ また、物流統括管理者は、物流改善に向けた現状の把握や分析等に当たって、デジタル技術を効果的かつ効率的に活用し、業務を行うことが望ましい。
○ なお、物流統括管理者の選任が義務付けられている特定荷主等の理解の促進に資するよう、物流統括管理者の新物効法上の業務と期待される役割等の整理について、今後、ガイドライン等で分かりやすく示すとともに、定期的な研修等を通じて、物流統括管理者に選任される人材の知識の涵養や資質の向上を図っていくことが求められる。 ※29
4.荷主・物流事業者等の物流改善の評価・公表について
○ 「物流革新に向けた政策パッケージ」を踏まえると、荷主企業・物流事業者による物流改善の取組や実施状況等についてランク評価等による見える化を行い、企業の努力が消費者や市場からの評価につながる仕組みの創設に向けて、新物効法の枠組みとあわせて具体化する必要がある。
○ 省エネ法の工場規制では、事業者クラス分け評価制度が存在し、省エネ法の定期報告書等を提出した特定事業者をS・A・B・Cの4段階へクラス分けし、クラスに応じたメリハリのある対応を実施するものとなっている。この制度を参考に、新物効法でも類似の評価制度を創設し、荷主・物流事業者等が提出した定期報告書等の内容を確認の上、判断基準に基づく取組の実施状況について優良な事業者、更なる努力が期待される事業者、停滞している事業者、注意を要する事業者のランク評価等による見える化を行い、消費者や市場からの評価につなげる必要がある。
なお、評価に際しては、以下の事項に留意する必要がある。
・ 荷主・物流事業者等の物流改善の取組について、優良事例を他の事業者に横展開するとともに、業界を超えたサプライチェーン全体の効率化につなげることができるような方策とすること。
・ 物流効率化が既に進んでいる事業者の不利とならないような方策とすること。
・ 関係事業者との連携についても評価すること。
・ 自社の取組に影響を及ぼす取引先等の取組状況も含め総合的に勘案できるような方策とすること。
・ 評価結果の公表は、事業者に与える影響等が大きいことから、適正に決定すること。
・ 定期報告書等の提出が義務となっていない特定事業者以外の企業が評価を希望した場合、その評価を行う体制を整えるなど、特定事業者とならない規模の事業者の取組のインセンティブとなる仕組みとすること。
・ 成熟度に応じた評価を設定し、各事業者の取組の進み具合を確認できるような仕組みとすること。 ※30
5.その他
○ 本合同会議において、委員や各種業界団体から提示された以下の意見については、物流の効率化をより一層進めていく観点から、引き続き検討を進めていく必要がある。
【より活用しやすい制度運用及び制度の周知・浸透について】
・ 今後、制度の施行の状況を注視しながら、グループ企業において物流部門と販売部門を所管する企業が別々の場合などについて、グループ企業の親会社等が一括して物流統括管理者の選任や中長期計画・定期報告の作成等を行うことができるようにしていくべきではないか。
・ 積載効率の向上等については、幹線やラストマイルなどの区分でのそれぞれの目標や積載率と実車率のそれぞれの目標を示していく必要があるのではないか。
・ 特定事業者に指定されるべき事業者に対する基準の周知や、特定事業者に指定されない規模の事業者に対する努力義務の遵守に向けた広報の強化など、制度の実効性を確保するための効果的な周知・浸透の在り方について、説明会の開催等も含め検討する必要があるのではないか。
・ 制度に関する事業者からの問合せ等に対応するための体制を整備する必要があるのではないか。
【地方の物流について】
特に、物流の「2024年問題」の影響が大きい農産物等をはじめとし、地方における物流の維持・確保に向けた方策について検討を行う必要があるのではないか。
【物流改善に資するデジタル化の推進について】
判断基準等の遵守や荷待ち時間等の計測に資するデジタル技術について、個々の技術の導入を推進するとともに、デジタル技術の導入によって目指すべき物流の全体像を作っていくべきではないか。また、デジタル技術の導入に当たっては、優良事例の横展開や設備投資を促すための支援措置が必要ではないか。
○ また、今般の法改正は、物流の輸送力不足の解消に向けて、令和5年6月に策定された「物流革新に向けた政策パッケージ」に基づく重要な施策の一つであり、その効果等については、本取りまとめを踏まえ法律・政省令等が施行された後に、政府において適時適切なタイミングで継続的にフォローアップしていくことが求められる。 31
(別紙1)交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会合同会議 委員名簿
(敬称略・五十音順)
<交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会>
大串おおぐし 葉子ようこ 同志社大学大学院 教授
大島おおしま 弘明ひろあき 流通経済大学流通情報学部 教授
小林こばやし 潔司きよし 京都大学経営管理大学院 特任教授
住野すみの 敏彦としひこ 全日本交通運輸産業労働組合協議会 前議長
根本ねもと 敏則としのり 敬愛大学 特任教授
二村ふたむら 真理子まりこ 東京女子大学現代教養学部 教授
若林わかばやし 亜あ理り砂さ 駒澤大学法科大学院 教授
<産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会>
小野塚おのづか 征まさ志し 株式会社ローランド・ベルガー パートナー
北川きたがわ 寛樹ひろき ボストン・コンサルティング・グループ
マネージング・ディレクター&パートナー
首藤しゅとう 若菜わかな 立教大学経済学部 教授
高岡たかおか 美佳みか 立教大学経営学部 教授
橋本はしもと 雅まさ隆たか 明治大学グローバル・ビジネス研究科 専任教授
<食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会>
飴あめ野の 仁子ひろこ 関西大学商学部 教授
加藤かとう 弘ひろ貴たか 公益財団法人流通経済研究所 専務理事
河野こうの 康子やすこ 一般財団法人日本消費者協会 理事
北條ほうじょう 英まさる 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 理事
矢野やの 裕児ゆうじ 流通経済大学流通情報学部 教授 32
<事務局>
国土交通省 物流・自動車局 物流政策課
国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課
経済産業省 商務・サービスグループ 消費・流通政策課 物流企画室
農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 食品流通課
<オブザーバー>
警察庁 生活安全局生活安全企画課
総務省 大臣官房総務課
財務省 理財局総務課たばこ塩事業室
国税庁 課税部酒税課団体企業係
文化庁 国語課
厚生労働省 医政局医薬産業振興・医療情報企画課
環境省 環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課
環境再生・資源循環局廃棄物規制課
自然環境局総務課動物愛護管理室
水・大気環境局モビリティ環境対策課 33
(別紙2) 合同会議における検討経過日時内容
2024年6月28日 第1回合同会議を開催し、規制的措置の施行に向けた検討を開始。
<議題>
(1)合同会議 座長の互選
(2)物流を取り巻く現状と取組状況について
(3)改正物流効率化法に基づく基本方針、判断基準、指定基準等について
(4)今後の検討の進め方について
2024年7月以降 事務局にて各種業界団体と意見交換
(荷主関係55団体、物流事業者9団体 等)
2024年8月26日 第2回合同会議を開催し、合同会議取りまとめ素案の提示や業界団体からのヒアリング等を実施。
<議題>
(1)合同会議におけるこれまでの議論等について
(2)取りまとめ素案及び追加論点について
(3)業界団体からのヒアリングについて
(4)意見交換
(5)今後の検討の進め方について
2024年9月26日 第3回合同会議を書面開催し、合同会議取りまとめ案について審議。
<議題>
○ 合同会議取りまとめ案について
2024年9月27日~
10月26日 合同会議取りまとめ案についてパブリックコメントを実施。
(意見提出件数 合計875件)
2024年11月11日 第4回合同会議を開催し、パブリックコメントの結果を踏まえ、合同会議取りまとめ案について審議。
<議題>
○ 合同会議取りまとめ案について
標準約款の改正予定
改正法第4条では、貨物自動車運送事業における多重下請構造の是正を図るため、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「法」という。)において、運送契約締結時等の書面交付義務、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務等について規定し、当該規定については、令和7年4月1日から施行するとされたところである。
2.改正内容
(1)運賃・料金及び附帯業務等を記載した書面の交付 「運送約款」及び「軽運送約款」における、運賃、料金及び附帯業務等を記載した書面(電磁的方法を含む。)の交付に係る規定について、改正法及び改正省令の内容を反映させる。また、「霊きゅう約款」については、運賃、料金及び附帯業務等を記載した書面(電磁的方法を含む。)の交付に係る規定を設けることとする。 〔関係条項〕運送約款(第6条、第7条)、軽運送約款(第6条、第7条)、霊きゅう約款(第7条、新設)
(2)運賃・料金等の店頭掲示 法第11条において義務付けられている、運賃・料金等の店頭への掲示について、ウェブサイトにその内容を掲載する場合には、店頭にも掲示が必要である旨を明確化する。 〔関係条項〕運送約款(第32条)、宅配便約款(第8条)、引越約款(第18条)、軽運送約款(第32条)、軽引越約款(第18条)、霊きゅう約款(第16条)、標準信書便約款(第13条)、軽信書便約款(第13条)
施 行: 令和7年4月1日

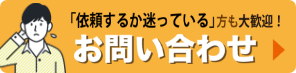




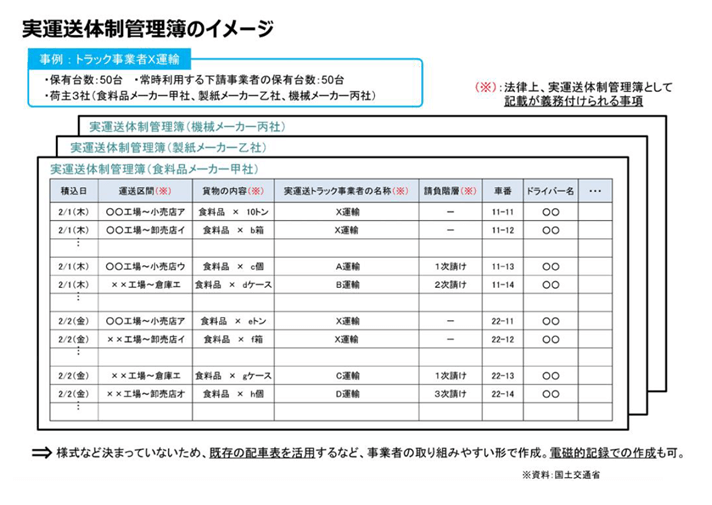
-67bd41db1a30d.jpg)