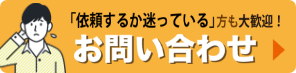一般貨物自動車運送事業の車両の選び方
緑ナンバーをつけられるトラックには要件があります。地域によってもその条件は変わります。トラックの大きさ、構造、車種、所有形態のなど、トラクタ・トレーラの際の注意点について解説します。

 【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」
神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】
【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」
神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】こんなご要望・お悩みはありませんか?
・緑ナンバーをつけられるトラックを探したい!
・自分が買おうとしているトラックはちゃんと緑ナンバーつくのだろうか?
・軽貨物トラックでも緑ナンバーつくのだろうか?
・年式が古いトラックでも大丈夫?
・リース車両でも緑ナンバーつけられるの?
・排ガス規制(NOx・PM)は気にする必要あるの?
・ナンバー返納しているトラックでも緑ナンバー付けられるの?
・新車でいきなり緑ナンバーって付けられるの?
そんな疑問にお答えします。
トラックの要件
車両は積載量があるトラックであれば1,4、8ナンバーのいずれかであれば大丈夫です。
4ナンバーの小さいバン車でも問題ありません。
ロードサービス用車両など特種な車両については、車検証上で最大積載量の記載があっても運輸支局が疑義を呈してくる場合があります。写真を提出させられることもあります。緑ナンバーが付けられるか事前に確認が必要です。
霊柩車は積載量がゼロですが問題ありません。
(霊柩車の要件については「霊柩車の定義」をご覧ください)
軽自動車は一般貨物自動車運送事業ではなく、黒いナンバーの貨物軽自動車経営届になるので、こちらの許可の車両としては使用できません。
もちろんオートバイも使用できません。
軽自動車とオートバイ(125cc超)は貨物軽自動車経営届(黒ナンバー、オートバイは緑ナンバー)の範囲になります。
トラクタヘッド、トレーラは1セットで初めて1両カウントになります。
トレーラが1両もなくてトラクタヘッドがある、逆にトラクタヘッドはなくてトレーラがあるというのは台数のカウントにはなりませんが、それ自体は問題ありません。
所有形態
以前は新規登録から小型3年普通4年未満の車両しか使用できない(耐用年数の関係)、リース車両は使用できない、などの制限がありましたがすべてなくなっています。
リースはファイナンス・リース、メンテナンス・リース両方とも大丈夫です。
レンタカーでは登録できません。
あくまで自動車検査証(以後、車検証)の使用者欄に申請事業者が載ることが求められます。
割賦で所有権留保(ローン会社が所有者欄に載っている)の状態でも問題ありません。
申請時は自社が使用者に入っていなくとも申請できます。
抹消してるトラック、新車にいきなり緑ナンバー付けられるのか?
ナンバーを返納して一時抹消している車両は、中古新規登録と言って、車検を通してから車検証を発行してナンバーを取り付けます。
新車も通常は検査ラインを通してから車検証を発行してナンバーを取り付けます。
その際、事業用自動車等連絡書があればいきなり緑ナンバーが付けられます。
一度、白ナンバーを付けなければならないということはありません。
白ナンバーで一旦納車される場合もあるでしょうから、その場合は事業用自動車等連絡書を持って運輸支局・登録事務所にて「番号変更」の手続きをすれば事業用の車検証に書き換わって緑ナンバーが付きます。
NOx・PM規制

NOx・PM規制をクリアしていないトラックはNOx・PM規制対象地域内では登録できませんので車検証備考欄にて必ず確認してください。
新車登録から9年しか使えないと思っている方もいますが、それはNOx・PM規制法施行時の適用の話であり、車両ごとに異なります。
心配であればあらかじめ運輸支局や登録検査事務所の検査部門にて車検証を見せて確認してください。
基準緩和車両
基準緩和車両は緩和申請が必要な場合があります。
個別緩和、一括緩和、既に緩和が不要で緩和を外す車両等、複雑です。
緩和申請は約1カ月かかるので並行して進めないと許可が下りても緑ナンバーが付けられない、という状況に陥ってしまいます。
備考欄に基準緩和の旨が書いてある車両については、必ず運輸支局や登録検査事務所の検査部門にてどのような緩和申請が必要なのか確認してください。
通行許可が必要な車両もある
特殊車両通行許可を取得しなければならないような大きな車両もあります。
緑ナンバーが付いてから特殊車両通行許可申請をするとそこから審査が始まってしまい、通行許可について違法状態になってしまいます。
国土交通省は車検証ができてない状態でも事前審査を受け付けてくれるようなので通行許可が必要な車両(基本は長さ12m、幅2.5m、高さ3.8m、車両総重量20tのいずれかを超えている車両)は新規許可申請と並行して通行許可の準備をしておいてください。
申請時が乗用車でも申請できる?
現在が3、5、7ナンバー乗用車でも構造変更で1、4ナンバーにできるのであれば一般貨物自動車運送事業の計画車両として計画に入れることができます。
専門家のサポートを受けたい方へ
緑ナンバー取得に向けてトラックの選び方について理解できたでしょうか。
トラックのルールもたくさんあるので覚えるのは結構大変です。
運送業許可を取得して緑ナンバーを付けるまでにはやることやクリアすることが盛りだくさんです。
トラサポでは全国で運送業新規許可の実績が多数ございます。
トラックの中古販売事業者やリース会社のパートナーも組んでいるのでトラック選定についてもサポートが可能です。
ぜひ一度、緑ナンバートラックについてお気軽にご相談してみてはいかがでしょうか?