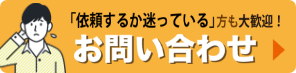会社の合併自体の全体的な流れは弁護士の先生や会計士の先生がメインで進めていくと思います。その中で意外と忘れられるのが、営業許可のことです。2か月後に合併登記かけます、と言って営業ナンバーの合併はどうすればいいか、とそのタイミングでご相談が来ることも少なくありません。登記の前に合併認可が下りていなければならないのです。よく、合併登記のあとに一般貨物自動車運送事業許可の合併認可をすると思っている人がいますが、全然逆なのです。事業許可の認可が完了しないと登記ができないのです。合併認可は申請してから3か月はかかると思います。従って、2か月前から合併認可申請をかけても認可はおりないでしょう。合併登記の日付自体を移すという選択肢もあると思いますが、もう動かせないという場合もあるでしょう。その場合は特別な手続きがあるのでご相談ください。
カテゴリー: 許可認可要件について
譲渡譲受申請では、営業所や車両などの設備や従業員もすべて一緒に引き継がなければいけないのでしょうか
そういうことが実際には多いと思いますが、特にそのような要件はありません。必ず引き継ぐのは営業ナンバー許可だけで、他の営業所、車庫、車両、従業員は新会社のオリジナルの事業計画で譲受するのもまったく構いません。
譲渡譲受申請では新会社に旧会社関係者が最低一人は役員もしくは従業員として所属しなければならないのでしょうか
そういうことが実際には多いと思いますが、特にそのような要件はありません。
譲渡譲受申請でも役員法令試験は合格しなければならないのでしょうか
譲渡譲受申請でも役員法令試験はクリアしなければなりません。新規許可申請と試験実施日のルールが若干違うので注意が必要です。申請日によっては、思っているよりずいぶん早く受けなければならなくなることもあります。
譲渡譲受申請でも資金要件の審査のために残高証明の提出が必要でしょうか
譲渡譲受申請でも残高証明で資金要件をクリアすることは必要なので、提出が求められます。
新規許可申請と譲渡譲受のメリットとデメリットを教えて下さい
最終的に新会社にて一般貨物自動車運送事業の許可が持てるというゴールは一緒です。そもそも事業許可の譲渡というのは法律で本来は禁止されています。運送事業はその中でも珍しく「譲渡」という手続きが存在します。ふつうは分割をしたりするわけです。譲渡譲受の方が、「審査期間は少し短いかもしれません」、「登録免許税12万円が不要です」、「社会保険未加入だとしても新会社で緑ナンバーがつけられます」、「古い(もともとの)許可番号が引き継がれます」。大きくはそういうところの違いがあります。しかし、申請書類は譲渡譲受の方がかなりボリュームが多くなります。旧会社の債務を新会社で引き継がないためには、官報への公告等が必要かもしれません。
一般貨物事業者でも純資産が300万円なければ利用運送とれないのでしょうか
意外にそんなことはありません。第一種貨物利用運送事業の登録を受ける場合は当然300万の純資産が求められますが、一般貨物自動車運送事業の中の利用運送を取る場合はほとんど問題になる要件はありません。
運送の仕事を仲介や紹介だけする仕事(求貨求車システムなども)等の運送取次事業は届出が必要なのでしょうか
紹介するだけの取次は、貨物利用運送事業法の成立時にその届出義務がなくなりました。今は自由に行えます。
貨物自動車運送事業は貸切バス等と同じく、運賃が認可制で守られていますか
今はなにも守られていません。自由な運賃設定が可能です。だからこそ、値下げしようとするといくらでも値下げする業者もいると思います。値引き競争に巻き込まれないで済むためにはいろいろな工夫と勉強や交渉をしていくことが必要です。
大型ダンプはゼッケンをつけなければいけないが、建設業と運送業の許可を持っている会社は○建か○営のどちらでもつけられるのでしょうか
運送業許可を持っている会社の緑ナンバー車両は○営ゼッケンしかつけられません。
アルコールチェッカーは国土交通省認定機種でなければいけないのでしょうか
アルコールチェッカー義務化の導入時期はいろいろと検討されましたが、結局今のところは特別な要件はありません。車用品販売店の2000円くらいのものでもルール上は構いません。ただし、故障時のために2台は常備しておいてください。
分割認可申請したら分割元の会社の運送事業許可は消滅してしまいますか
これは意外と消滅しないとすることもできます。運送事業部門の一部を分割するということで、分割前の会社にも許可を残すことができます。そこの分割契約書や分割認可申請の細かい方法は運輸局とも相談しながら進めてください。
車庫や建物の賃貸借契約書が転貸契約書の場合でも問題はないでしょうか
転貸借契約自体は構いません。しかし、運輸局からは元契約(もともとの大家さんとまんなかの転貸者)は求められます。そこに、「転貸禁止」と書いてあったら認められません。その場合は、大家さんから一般貨物自動車運送事業車庫としての使用承諾書などをもらわなくてはいけません。
車庫の中で、警察に車庫証明を申請している自家用自動車スペースがあるが、そこも一般貨物の車庫として申請して構わないのでしょうか
一般貨物自動車運送事業の車庫の要件として「他の用途と明確に分けられていること」が求められています。従って、警察の車庫証明用のスペースは一般貨物自動車運送事業の車庫として認められません。それとは別に、従業員の自家用車がトラックと入れ替えで止めることは完全にOKかと言われると明確な判断は難しいですが、現実問題は特になにも言われないと思います。
役員法令試験は2か月に1度実施されているので、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請前に受験することも可能なのでしょうか
役員法令試験は確かに奇数月に開催していますが、あくまで一般貨物自動車運送事業の新規許可申請をした事業者の役員だけが受ける試験です。事前に受かってから安心して新規許可申請したい、という気持ちはわかりますが、そういうことは残念ながらできないのです。
リース車両で登録する場合の必要書類はなですか?
所有者をリース会社にする場合、リース会社の印鑑証明、委任状が必要です。事業者としての書類は委任状と事業用自動車等連絡書です。事業者は使用者としてのみ車検証に載る場合、印鑑証明・法人謄本は不要です。リース会社へはある程度余裕を持ったタイミングで委任状等を依頼しておくのがよいでしょう。
リース車両だと営業ナンバー取れないと聞きましたが本当でしょうか
昔はそういう時代もありましたが、今はファイナンスリース、メンテナンスリースいずれでも許可取得が可能です。
最低5台の車両は小型5台でも許可を取れるでしょうか
軽自動車はだめですが、4ナンバー小型トラック(ADバン、サニーバンなど含む)は大丈夫です。実際に小さいトラックだけで仕事をするのであれば、それで構いません。
営業所名には必ず”営業所”という文言を入れなければならないのでしょうか
営業所名には特にルールはありません。「関東配送センター」と”営業所”という言葉を入れなくても全然認められます。
登録免許税の支払済書はコピーでなく原本を運輸局に輸送する必要があるのでしょうか
運輸局から来る手紙には「納付後、原本を送ってください」とあります。そうすると経費処理のときに大丈夫か、と心配になるかもしれません。しかし、原本を送って大丈夫です。コピーを控えておいてください、それで税務署もなんにも言いません。
整備管理者の実務経験はトラックを整備点検した実務経験が必要なのでしょうか
本来はそうあるべきかもしれませんが、そのルールが少し緩みました。今は「バイク以外」と「バイク」にわかれているだけです。乗用車専門の整備工場で働いていたとしても、整備管理者選任前研修さえ修了していればトラック運送事業の整備管理者として選任可能です。(参考:関東運輸局「整備管理者制度の解説」)
整備管理者になるには整備士の国家資格が必要なのでしょうか
もちろん国家資格があれば万全です。しかし、国家資格の整備士でなくても、整備管理者選任前研修を受ければ、2年以上の整備点検等の実務経験があれば、整備管理者として選任することができます。
霊柩事業のドライバーは2種運転免許が必要でしょうか
これもよくある勘違いです。ご遺体はもうお亡くなりになっているので、法的にはあくまでモノです。だから一般貨物自動車運送事業の許可、すなわち”貨物”という扱いになるのですね。だから2種免許は旅客すなわち生きている人間を乗せるための資格なので霊柩事業では不要です。
霊柩事業で許可を取る場合でも運行管理者は必要でしょうか
車両が4台以下であれば不要です。5台にするには運行管理者と整備管理者の選任届を整備担当部署に提出してからでないと5台目の増車はできません。
産廃収集運搬の許可事業者は1台でも許可が取れると聞きましたがそうなのでしょうか
これもよくある勘違いです。1台でも認められるのは「一般廃棄物」の収集運搬事業者です。産業廃棄物収集運搬事業者が緑ナンバーをつけたい場合はあくまで5台の車両が必要です。
5台の計画車両には軽貨物車両も含めることができるでしょうか
軽貨物自動車は一般貨物自動車運送事業の車両数にはカウントできません。軽貨物自動車は貨物軽自動車経営で、黒ナンバーになります。
営業所などの賃貸借契約書の相手側の記名押印は代表者の押印でなければ認められないのでしょうか
営業所長や担当事業部長などでも、その決裁権のある肩書の人であれば法的に契約は問題ないので、運輸局に出す書類としても問題ありません。
営業所の面積は10平米以上なければならないのでしょうか
運輸局によっては、そのように読める公示を出しているところもありますが。面積の要件はありません。実際に仕事ができればもし6平米しかなくても実際に認められたケースもあります。
新規許可申請時の役員法令試験合格者が役員から抜けた場合は、他の役員が改めて役員法令試験に合格しなければならないのでしょうか
意外とそんなことはありません。本来は役員のいずれかが役員法令試験合格者でなければいけないような気もしますが、最初に合格すれば社長が交代しても、次の社長は受ける必要はありません。
申請時に法人謄本目的に「貨物自動車運送事業」等の文言が入っていない場合、登記完了してからでないと申請を受け付けてもらえないのでしょうか
意外とそんなことはありません。まずは定款目的変更の臨時株主総会議事録を作成し、そのコピーを添付して申請すればよいです。その後、登記完了の法人謄本を差し替え提出すればいいでしょう。
申請会社の社長が他の会社の役員に登記されている場合、その会社の役員から抜けなければ専業とみなされないのでしょうか
別にそう決まっているわけではありません。一人の人間が複数の会社役員になっていることもあるでしょう。運輸局と相談して、一般貨物の申請会社の選任であることを証する書面を添付して申請すればいいでしょう。両方の会社の代表取締役の場合は難しいかもしれませんね。
役員が運行管理者とドライバーを兼任するということであれば、総勢最低5人でも許可は下りるでしょうか
これは難しい問題ですね。法律で運行管理者と運転者の兼任を明確に禁止しているわけではありませんが、じゃぁ実際その運転者の対面点呼は誰がやるんだ、という話になります。たとえば、別の運転者が運行管理者補助者であり、その運行管理者兼任運転者の対面点呼をする、ということであれば、理論的にはルールは守れます。しかし、毎日、その二人は同じ時間に営業所にいて、お互いを点呼しなければならないわけです。それをずっと続けられるのかどうかという問題もあるでしょう。運輸局に相談してみてください。
貸借対照表の純資産の部がマイナスであると、経営状況が芳しくないのでプラスになるまで増資しなければ許可されないのでしょうか
今も添付書類の中に貸借対照表はありますが、純資産の部を見ることはありません。あくまで残高証明の金額で資金要件は判断します。平成25年11月30日申請までは増資しなければなりませんでした。
定款の目的が「一般区域貨物自動車運送事業」だと目的変更しなければ許可とならないのでしょうか
これは難しい問題ですね。たまに、昔の運送会社の定款目的をそのまま「これと同じにして」と注文を受けた行政書士や司法書士が本当にそのままお客様の言う通りに定款を作るとこのような事態に陥ります。最終的には運輸局と相談になるでしょうが、今は「一般貨物自動車運送事業」が正式な名称です。修正させられる場合もあるでしょう。その場合は当然、法務局の登録免許税がかかってしまいます。法人設立もトラサポにご依頼いただければ安心して一般貨物自動車運送事業許可が取れる法人が設立できます。
トラクタとトレーラのセットで申請する場合、トレーラにも必ず任意保険はかけなくてはいけないのでしょうか
トレーラの任意保険加入は必須ではありません。損保会社さんと、トラクタの任意保険でカバーできることを確認してい入れば、トレーラの任意保険は未加入でも現実問題も許認可上も問題ありません。
現在、賃貸期間が過ぎていても自動更新条項があればなにもしなくても認められるのでしょうか
基本的には自動更新契約であれば、使用権原を示す書類としては問題ありません。ただ、一応現在も賃貸しているという自認書的なものは求められるかもしれませんね。
現在、賃貸期間が過ぎていても自動更新条項があればなにもしなくても認められるのでしょうか
同じ部屋を分け使うのは、その区分けの方法については運輸支局と要相談でしょうが、大丈夫です。ただ、車庫と同じで同じ区画を兼用することはできません。
同じ空間の部屋を複数の事業者で営業所として分割利用することは認められるのでしょうか
同じ部屋を分け使うのは、その区分けの方法については運輸支局と要相談でしょうが、大丈夫です。ただ、車庫と同じで同じ区画を兼用することはできません。
車庫は親子会社や社長が同じ会社の関係であれば同じスペースを共用しても大丈夫でしょうか
同じ敷地内で分けて使うのは構いませんが、その中の同じ区画を複数事業者で利用はできません。
1つの敷地を複数の事業者で車庫に分割利用できるのでしょうか
別に構いません。ただ、駐車場から出るまでの通路を確保しなければならないので、もし手前と奥に使用区域が分かれるのであれば、奥の事業者の分の通路を手前側の区域に確保しなければなりません。手前側の事業者は手前すべての面積を車庫としては利用できないということになりますね。
営業所と休憩施設の間にはパーティションなど物理的な仕切りが必要なのでしょうか
担当官によりますが、法令ではそのような要件は求められていません。過度な要求には疑問をぶつけるべきでしょう。
残高証明はすぐに使えるお金でなければいけないので当座預金はカウントできないのでしょうか
別に口座種別は問いません。
運行管理者は最低一人は役員でなければいけないのでしょうか
そんなことはありません。ただ、運行管理者は責任ある立場なので、会社の言うなりではなくしっかり意見を言える権限を与えておくことが求められています。
金融機関の残高証明では必要資金が足りないのですが方法はありませんか
運輸局によってですが、流動資産を加算できる場合があります。売掛金などが認められることもありますので、相談してみてください。ただ、この方法は新規法人では売掛金がないので使えない方法ですね。すでになにかしらの事業で売り上げが立っている事業者さんは検討してみてください。
第一種貨物利用運送事業をもっている事業者が、一般貨物自動車運送事業を新規許可申請すると、もともと持っている第一種貨物利用運送事業許可が消えてしまうと聞きましたが本当でしょうか
本当です。しかし、利用運送専業事業者を利用する(外注する)事業者として、運輸支局に届けている場合は残ります。要するに、実運送事業者を外注として利用する場合は、一般貨物自動車運送事業許可の範囲でやるべきなので、第一種貨物利用運送事業はいらないでしょ、という理屈で消されてしまうということです。
5ナンバー乗用車でも許可後に貨物自動車に構造変更するということであれば申請車両に含むことは可能なのでしょうか
可能です。許可がおりて、そのあと構造変更検査で貨物自動車として合格していただき、緑ナンバーがつくことになります。検査については事前に検査担当に相談しておいてくださいね。
許可が下りたらすぐに増車できるのでしょうか
許可下りて、「運行管理者と整備管理者の選任届」を出して、「運輸開始前確認」出して、「申請時の車両すべてに緑ナンバーをつけ」て、「運輸開始届」を出して、はじめて増車などができます。
運輸開始届は許可から1年以内に提出しなければせっかく取った許可も条件の通りに自動で無効となってしまうのでしょうか
実際はそんなことはありません。でも1年以内に運輸開始届を出せない場合は、事前に運輸支局に連絡を入れておくべきでしょう。許可条件には、1年以内に運輸開始届を出すことが明記されているので、本当であれば自動でなくなってもおかしくないのかもしれないわけですから。
社会保険や雇用労災保険は申請時点で加入していなければいけないのでしょうか
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請としては、加入していなくとも構いません。運輸開始前確認のときまでには入っていてください。しかし、法人(株式会社等)であればそもそも社会保険加入していなければいけないのでそれはそれで確実に行っておいてくださいね。
車庫はデッドスペースも求積図の面積としてカウントしてよいのでしょうか
そもそも実際に前後左右50cmの余裕をもって全車両を収納できることが必要です。その上で、デッドスペースが面積にカウントされるかどうかは運輸局の判断になります。面積から除外されるように指導されることも多いです。